【SPI言語を完全対策】頻出分野や例題・対策のコツは?頻出語句もご紹介
ES・選考対策公開日:2025.07.16
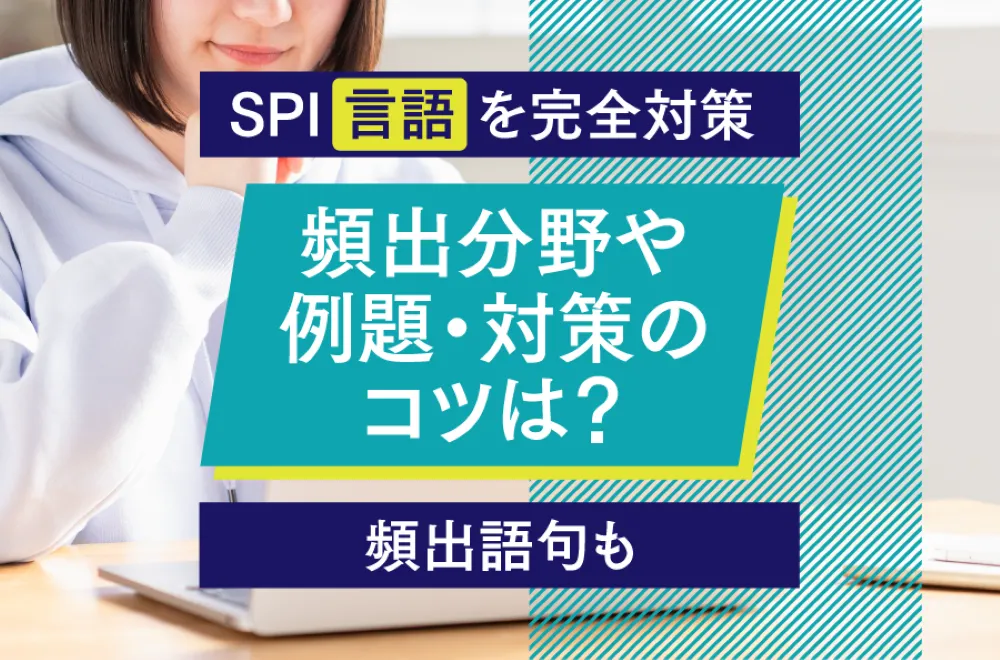
SPIの言語のテストでは語彙力や熟語の知識、長文読解力が問われるため、頻出分野の練習問題や例題を繰り返し解くことが高得点のカギとなります。時間制限も厳しいため、模試や問題集で本番を意識した対策が重要です。この記事ではSPI言語の特徴や頻出語句、効率的な勉強法、対策のコツを詳しく解説します。
そもそもSPIとは?
SPIとは、企業が採用選考時に応募者に対して行う適性検査の1つです。リクルートマネジメントソリューションズ社が開発した検査で、正式名称は「Synthetic Personality Inventory」です。応募者の能力や性格を測るために多くの企業で新卒採用の選考に採用されており、特に「SPI3」が主流となっています。
SPIの受検方法は以下の4つです。通常、この中からいずれかを企業から指定され受検することになります。
テストセンター:企業指定の会場で専用のパソコンから受検する
WEBテスティング:自分などのパソコンからオンラインで受検する
ペーパーテスティング:企業指定の会場で紙とペンを使って受検する
インハウスCBT:企業のオフィス内・指定の会場で専用のパソコンから受検する
SPIについてさらに詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
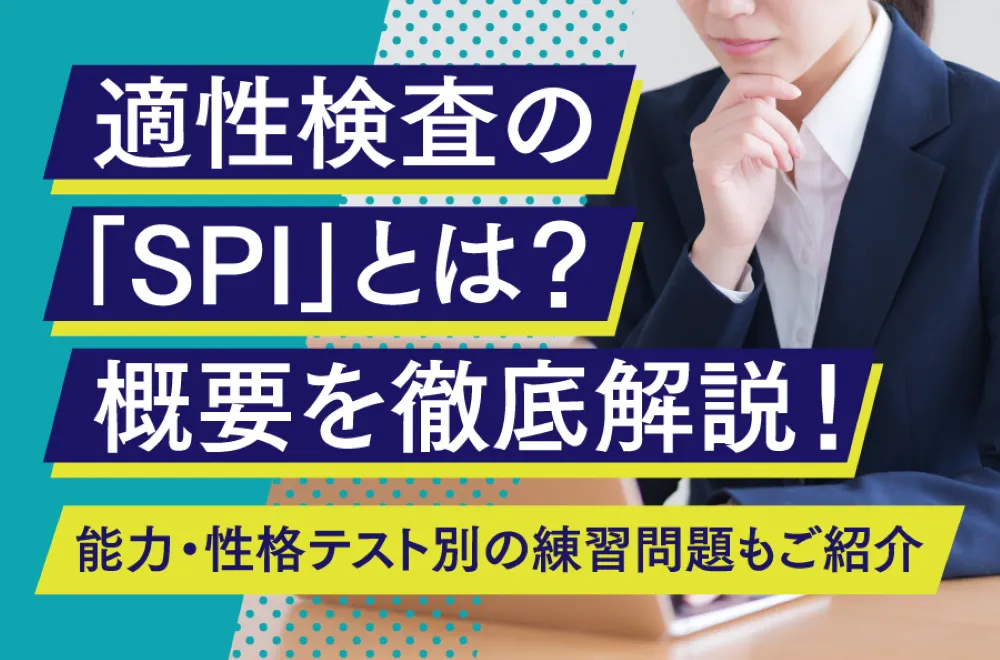
適性検査の「SPI」とは?概要を徹底解説!能力・性格テスト別の練習問題もご紹介
新卒就活の選考に多く採用されているSPIですが、「そもそもSPIとは?」「どんな問題が出る?」などわからない方もいらっしゃると思います。本記事では、SPIの基本的な概要から受検方法、性格検査・能力検査のそれぞれの問題も…
SPI言語とは?

SPI言語はSPIの能力検査の一部で、主に日本語の語彙力や論理的思考力を測るテストです。出題内容は国語の試験に似ており、語句の意味や用法、二語の関係、熟語の成り立ち、文の並び替え、空欄補充、長文読解などで構成されています。
SPIは、テストセンターやWEBテスティング、ペーパーテスティングなど、受検方法によって制限時間や出題数、出題範囲が異なる点に注意が必要です。また、全体的に1問あたりの解答時間が短く、スピードと正確さが求められるため、事前の確認・対策が欠かせません。
SPI言語の特徴
SPI言語は、ビジネスの場で必要となる「伝える力」「読む力」「理解する力」を評価することを目的としています。出題形式は決まっており、語彙や長文読解、論理的思考力など、多様な日本語力が問われるのが特徴です。以下で詳しく解説していきます。
■語彙・語句の知識が問われる
SPI言語では、語彙力や語句の知識が問われるのが大きなポイントです。特に、同義語や反義語、熟語の成り立ちや意味を正確に理解する力が求められます。
語彙力を強化するには、日常的に新聞やビジネス書を読む習慣をつけておくことが大切です。また、頻出語句をリストアップして覚えるのもよいでしょう。
■長文問題も含まれる
SPI言語には、長文読解の問題も含まれており、文章全体の構成や要旨を素早く把握する力が問われます。筆者の主張や文章のテーマを正確に読み取る必要があるため、集中力と高い読解力が不可欠です。
対策としては、普段から速読や要約の練習を重ね、限られた時間内に要点を見抜く力を養うことが重要です。
SPIで長文読解の問題が出ない場合もある?
SPIは正答率によって出題内容が変動するため、長文問題が出ないケースもあります。長文問題は言語分野で難易度が高いとされているので、出題されればこれまでの解答の正答率が高いと考えられるでしょう。ただし、テスト形式や企業によっては言語問題が省略されるケースもあるため1つの参考程度に留めることが大切です。
■時間制限が厳しい
SPI言語は、30分程度の短い時間で40問を解く必要があり、問題数を制限時間で割ると1問にかけられる時間の目安は1分程度です。正確さとスピードの両立が求められます。
普段から時間を意識した問題演習を行い、各問題にかけるべき時間を判断する力を身につけることが重要です。
模擬試験を活用して実際の試験に近い環境で練習し、時間配分の感覚を身につけておきましょう。
【出題分野別】SPI言語の例題と対策ポイント
SPI言語では、特に「二語の関係」「熟語の成り立ち」「語句の用法」「文の並び替え」「空欄補充」「長文理解」の6分野がよく出題されます。それぞれ異なる日本語力や論理的思考力が問われるため、幅広い対策が必要となります。
各分野の出題傾向や形式を理解し、特徴に応じた対策を行いましょう。
| 分野 | 出題内容 |
|---|---|
| 二語の関係 | 提示された2つの語句の関係性を考え、同じ関係にある語句の組み合わせを選ぶ |
| 熟語の成り立ち | 二字熟語の構成や、漢字同士の関係を見極める |
| 語句の用法 | 設問文中の語句と同じ意味や使い方をしているものを選ぶ |
| 文の並び替え | バラバラに並んだ語句や文節を、意味が通るように正しい順序に並べ替える |
| 空欄補充 | 文章中の空欄にもっとも適切な語句を選ぶ |
| 長文理解 | 長文を読み、内容の要点や筆者の主張、正誤を判断する |
※表をスクロールしてご覧ください
| 分野 | 出題内容 |
|---|---|
| 二語の関係 | 提示された2つの語句の関係性を考え、同じ関係にある語句の組み合わせを選ぶ |
| 熟語の成り立ち | 二字熟語の構成や、漢字同士の関係を見極める |
| 語句の用法 | 設問文中の語句と同じ意味や使い方をしているものを選ぶ |
| 文の並び替え | バラバラに並んだ語句や文節を、意味が通るように正しい順序に並べ替える |
| 空欄補充 | 文章中の空欄にもっとも適切な語句を選ぶ |
| 長文理解 | 長文を読み、内容の要点や筆者の主張、正誤を判断する |
■二語の関係
二語の関係問題では、与えられた2つの語句がどのような関係性をもつかを見抜く力が問われます。それぞれの語がどのように結びついているかを文章化して考える必要があるため、単語の意味や使われ方を正確に理解することが重要です。
頻出パターンを繰り返し練習し、素早く正答にたどり着く力を身につけましょう。
例題:
「大学:教育機関」と同じ関係にあるものを、次の選択肢から選びなさい。
ハサミ:( )
A:カッター
B:やすり
C:切る
D:文房具
解答:
D:文房具
解説:
「大学」は「教育機関」の一種であり、包含関係にあります。同様に「ハサミ」は「文房具」の一種なので、Dの「文房具」が正解です。SPIの二語の関係問題では、設問の語句同士の関係を文章化し、選択肢の語句にも同じ関係が成立するかを確認することがポイントです。
■熟語の成り立ち
熟語の成り立ち問題では、複数の漢字や単語が組み合わさって1つの意味を形成する仕組みを理解することが求められます。頻出する熟語やその構成パターンを覚えることはもちろん、意味だけでなく文脈や使われ方も意識して学習することで、応用力が身につきます。日常的に多くの熟語に触れることが得点力向上のカギです。
例題:
次のうち、対義語の組み合わせでできている熟語を選びなさい。
A:上下
B:山林
C:友情
D:高速
解答:
A:上下
解説:
「上下」は「上」と「下」という、意味が反対の漢字が組み合わさってできている対義語の熟語です。ほかの選択肢は、意味が似ているものや、組み合わせによって新たな意味をもつ熟語ですが、対義語の組み合わせではありません。
■語句の用法
語句の用法問題では、特定の語句がどのような場面や文脈で使われるのかを正しく判断する力が求められます。単語の意味を知っているだけではなく、使い方やニュアンス、ほかの語句との組み合わせ方まで理解しておく必要があります。
文脈に合った語句を選ぶためには、さまざまな例文に触れ、実践的な知識を積み重ねることが大切です。語句の使い分けや微妙な意味の違いを意識することで、より正確に解答できるようになります。
例題:
下記の下線部の語ともっとも近い意味で使われているものを1つ選びなさい。
「彼はその場の空気を読むのが得意だ」
A:本を読む
B:新聞を読む
C:相手の気持ちを読む
D:メールを読む
解答:
C:相手の気持ちを読む
解説:
例文の「読む」は、文字を解読するという意味ではなく、「状況や雰囲気を察する」「相手の意図を理解する」という比喩的な意味で使われています。選択肢の中で同じ意味で使われているのはCの「相手の気持ちを読む」です。
■文の並び替え
文の並び替え問題では、バラバラに提示された文や文節を論理的に組み立てて、意味の通る文章を完成させる力が問われます。文章全体の流れや各文の役割を把握し、接続詞や指示語、前後関係に注意しながら並べ替えることがポイントです。
論理的思考力や文章構成力を養うためには、日ごろからさまざまな文章を読み、構造を意識して要約や並び替えの練習を重ねることが効果的です。正しい順序で文章を組み立てる力は、ほかの問題にも応用できます。
例題:
次の(ア)~(オ)の文を、意味が通るように並べ替えたとき、(ウ)の次にくるのはどれか選びなさい。
(ア)そのため、友人と相談することにした。
(イ)彼は最近、仕事に悩みを抱えている。
(ウ)自分ひとりでは解決できないことも多い。
(エ)友人からは、思いがけないアドバイスをもらった。
(オ)そのおかげで、気持ちが楽になった。
解答:
(ア)そのため、友人と相談することにした。
解説:
(ウ)の「自分ひとりでは解決できないことも多い。」のあとに続くのは、その理由や状況を受けて「どうしたのか?」という行動や結果を述べる文が自然です。(ア)「そのため、友人と相談することにした。」は、「自分ひとりでは解決できない」という状況を受けて、「だから友人に相談した」という行動を説明しています。したがって、(ウ)の次に(ア)をもってくるのが日本語の文章としてもっともスムーズです。
■空間補充
空欄補充問題は、文章中の空欄にもっとも適切な語句や文節を選び、意味の通る文章を完成させる形式の問題です。前後の文脈を的確に読み取り、文章全体の流れや論理を把握した上で、空欄にふさわしい語句を予測する力が求められます。
多くの例題に取り組み、文脈判断力や語彙力を高めることが得点アップのポイントです。空欄の前後だけでなく、文章全体を俯瞰して考える習慣をつけると、より正確な解答ができるようになるでしょう。
例題:
次の文の( )に入るもっとも適切な語句を選びなさい。
「彼の主張は一見すると独創的だが、実は過去の学説を( )しているにすぎない。そのため、専門家の間ではあまり評価されていない。」
A:超越
B:発展
C:批判
D:模倣
解答:
D:模倣
解説:
文の後半に「専門家の間ではあまり評価されていない」とあるため、否定的なニュアンスであることがわかります。したがって、「表面的には新しいアイデアのように見えるが、実際は過去のものをまねているだけである」という意味になる「模倣」が文脈にもっとも合致します。
■長文理解
長文理解問題は、長い文章を読み、その内容や構成、筆者の意図を正確に把握する力が問われます。文章の要点や論旨を素早く見抜き、設問に対して的確に答えるためには、高い読解力と集中力が必要です。
文章全体の流れや論理構造を理解し、重要な情報を抽出するトレーニングを日常的に行うことで、限られた時間内でも正確な理解力を発揮できます。要約や速読の練習も効果的です。
例題:
人間の「記憶」は非常に不確かである。自分でははっきりと覚えているつもりの出来事が、実際とは異なっているということは珍しくない。特に、感情が強く動いた出来事ほど、その記憶は( )されやすい傾向にある。これは、脳が経験を単なる事実の記録としてではなく、意味づけされた物語として処理するためだと考えられている。
このような記憶の特性は、証言の信頼性を問題にする場面で重要な意味をもつ。たとえば、事件の目撃者が「確かにそうだった」と語ったとしても、それが真実である保証はない。それによって無実の人が罪に問われることも実際に起きているのである。
こうした問題に対処するためには、人間の記憶の性質を理解した上で、複数の情報源を組み合わせて判断する視点が必要である。科学的な知見に基づいたアプローチが、今後ますます求められていくだろう。
(1)文中の空所( )に当てはまるもっとも適切な言葉はどれか。
ア 記録
イ 強調
ウ 誤解
エ 改変
オ 保管
(2)筆者が記憶を「物語として処理する」と述べた理由として適切なものはどれか。
ア 記憶が感情の影響を受けやすいため
イ 記憶が完全に再現できるため
ウ 脳が意味のない情報を排除するため
エ 目撃者が話を盛る傾向にあるため
オ 証言が必ず正確であるわけではないため
(3)文中のそれが指している内容としてもっとも適切なものはどれか。
ア 人間の記憶の不確かさ
イ 事件の目撃証言
ウ 感情が強く動いた出来事
エ 意味づけされた物語
オ 記憶の改変
(4)筆者が伝えたいこととして適切なものはどれか。
ア 感情を伴う出来事ほど記憶に残りやすい
イ 目撃証言は常に信頼すべきである
ウ 科学的知見によって記憶の正確さを保証できる
エ 記憶には限界があるため、多角的な検証が必要である
オ 人の記憶は事実と一致するように脳が補正している
(5)本文の内容と合致するものはどれか。
ア 記憶はしばしば事実と異なる
イ 記憶の性質を理解することは司法にも重要である
ウ 目撃証言は真実を保証するもっとも有効な方法である
A アだけ B イだけ C ウだけ D アとイ E アとウ F イとウ
解答:
(1):エ 改変
(2):ア 記憶が感情の影響を受けやすいため
(3):ア 人間の記憶の不確かさ
(4):エ 記憶には限界があるため、多角的な検証が必要である
(5):D アとイ
解説:
(1):文中では「感情が強いほど、記憶の内容が事実と異なってしまう」ことを述べています。「改変」は「元の形が変わる」という意味なので、ここでは「記憶が感情の影響で変わってしまう」ことを表しており、エが文脈にもっとも適しています。
(2):文中では感情や個人の意味づけによって記憶が変化することを示しています。「感情の影響」が記憶の変容に影響するため、アがもっとも適しています。
(3):それが原因でえん罪が生まれるという意味になります。直前に「証言が真実である保証はない」という文があり、その根本的な原因は「人間の記憶の不確かさ」のため、アがもっとも適しています。
(4):本文の結論部分で「複数の情報源を組み合わせて判断する視点が必要」と述べられており、人間の記憶は完全ではないという立場を筆者はとっています。したがって、記憶に依存しすぎず多角的に検証すべきという、エが筆者の主張としてもっとも適しています。
(5):
ア「記憶はしばしば事実と異なる」→ 文中では繰り返し記憶の不確かさが述べられています。
イ「記憶の性質を理解することは司法にも重要である」→文中では目撃証言がえん罪に関係することが記述されており、司法での重要性が示されています。
ウ「目撃証言は真実を保証するもっとも有効な方法である」→ 本文では目撃証言は不確かであると主張されています。
したがって正解は D(アとイ)です。
SPI言語試験の対策のコツ

SPI言語試験で高得点を狙うには、計画的な対策と基礎力の強化が不可欠です。ここでは、効率的に得点力を伸ばすための具体的な勉強法やポイントをご紹介します。
■頻出語句を暗記する
SPI言語の対策では、頻出語句の暗記が欠かせません。よく出る語句はリストアップし、フラッシュカードなどを活用して隙間時間に繰り返し確認しましょう。単なる暗記にとどまらず、例文を作成して実際の使い方を意識することで、知識の定着と応用力が高まります。
| 頻出語句 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 折半 | せっぱん | 半分に分けること |
| 看破 | かんぱ | 見破ること |
| 標榜 | ひょうぼう | 主義主張などを掲げて公然と示すこと |
| 漸次 | ぜんじ | 次第に |
| 披瀝 | ひれき | 心の中の考えを包み隠さず打ち明けること |
| 齟齬 | そご | 意見などが食い違い一致しないこと |
| 斡旋 | あっせん | 交渉や商売などで間に入って両者をうまく取りもつこと |
| 軋轢 | あつれき | 仲が悪くなること |
| 伝播 | でんぱ | 伝わり広がっていくこと |
| 折衷 | せっちゅう | それぞれのよい点を取り合わせて1つにまとめること |
※表をスクロールしてご覧ください
| 頻出語句 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 折半 | せっぱん | 半分に分けること |
| 看破 | かんぱ | 見破ること |
| 標榜 | ひょうぼう | 主義主張などを掲げて公然と示すこと |
| 漸次 | ぜんじ | 次第に |
| 披瀝 | ひれき | 心の中の考えを包み隠さず打ち明けること |
| 齟齬 | そご | 意見などが食い違い一致しないこと |
| 斡旋 | あっせん | 交渉や商売などで間に入って両者をうまく取りもつこと |
| 軋轢 | あつれき | 仲が悪くなること |
| 伝播 | でんぱ | 伝わり広がっていくこと |
| 折衷 | せっちゅう | それぞれのよい点を取り合わせて1つにまとめること |
語彙力の強化はSPI言語対策の基本です。新聞や雑誌のコラムを日常的に読むようにし、知らない単語に出会ったらすぐに辞書で調べる習慣をつけましょう。語彙力が上がれば、長文問題の読解力・対応力も自然と高まります。
■問題集1冊を徹底して解く
SPI言語の対策では、自分に合った問題集を1冊選び、その1冊を徹底的に取り組むことが効果的です。複数の問題集に手を広げるよりも、まずは1冊を繰り返し学習しましょう。
問題集にはSPIで頻出する形式や知識が網羅されているため、何度も解くことで出題傾向やパターンを自然と身につけることができます。また、間違えた問題や解けなかった問題は必ず解説を読み込み、できなかった原因も分析して理解を深めましょう。
時間を計って本番さながらに取り組むことで、時間配分や解答スピードも鍛えられます。
下記の記事でSPI対策におすすめの本や、自分に合った問題集の選び方も解説しているので参考にご覧ください。
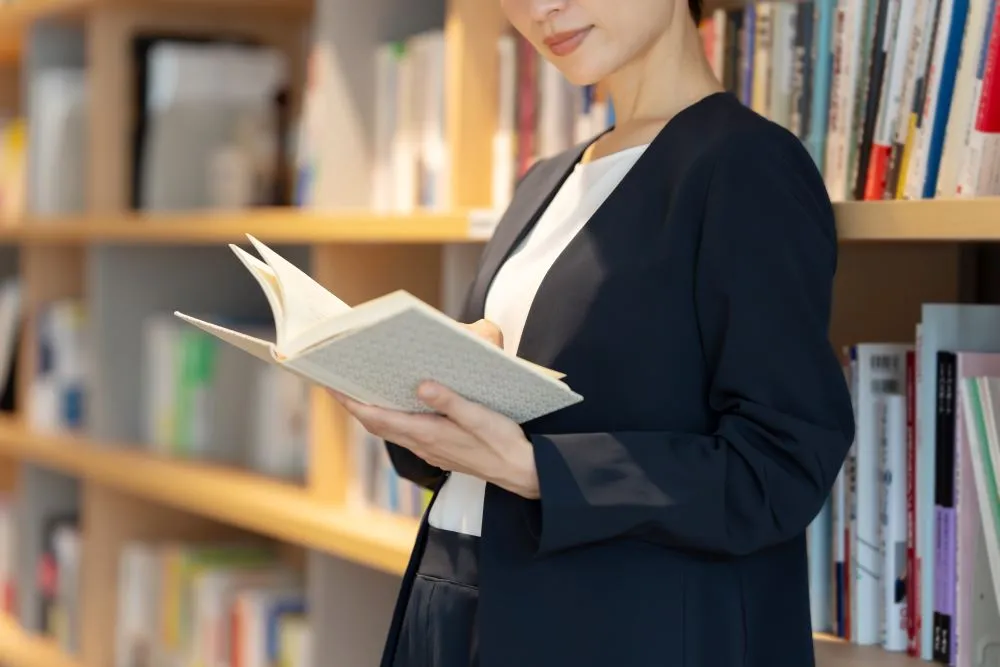
SPI対策におすすめの本12選!選ぶときのポイントも解説
就活の第一関門として重要な「SPI」。どのように対策すればとよいかわからない方も多いでしょう。特に大手企業や人気企業を希望している場合は、入念な対策が欠かせません。
この記事では、効果的にSPI対策できるおすすめの本を…
■模試試験を受けて本番の雰囲気に慣れておく
模試試験は本番と同じ出題形式や制限時間で実施されるため、問題の難易度、時間配分を体感できる機会です。特に初めてSPI試験を受ける場合は、試験の流れを把握するためにも受けておいたほうがよいでしょう。
模擬試験の活用は、自分の弱点や時間がかかる問題の把握や、効率的な学習計画を立てる上でも役立ちます。定期的に模試を受け、実践力と自信を養い、本番での実力発揮につなげましょう。
『キャリタス就活』では、WEBテストを手軽に体験できるコンテンツや、「SPI」「玉手箱」の模試を受けられるコンテンツをご提供しています。WEBテスト対策としてぜひご活用ください。
【お試し!WEBテスト】
「お試し!WEBテスト」は、WEBテストやテストセンターなど、パソコンで受検する環境を再現したコンテンツです。「言語問題」5問と「非言語問題」10問が用意されており、制限時間も設定されているため、よりリアルな環境でチャレンジできます。
本番さながらの緊張感の中で練習することで、本番では心の余裕をもって検査を受けることができます。
【キャリタス模試】
キャリタス模試では「SPI形式問題」「玉手箱形式問題」「一般常識問題」が受けられます。月に1回、10日間の受検期間を設けて模試を実施しており、全国順位や全国平均点と比較して自分の実力を測ることができます。
実施期間終了後は過去問として模試を受けられます(順位は出ません)。
■苦手分野を反復しておく
模擬テストや練習問題の活用により、自分の苦手分野が明確になったら、そこを重点的に繰り返し学習することで効率よく弱点を克服できます。
苦手な分野はつい避けてしまいがちですが、意識的に反復練習を積めば、知識や解答スピードが着実に向上します。定期的に自分の理解度をチェックし、学習計画を柔軟に見直すことも大切です。
■受検企業の出題形式や問題の傾向を確認する
SPIは、企業ごとに受検方法や出題形式が異なるため、まず自分が受検する企業がどの適性検査を採用しているのかをしっかり調べることが重要です。テストセンターやWEBテスティング、ペーパーテスティングなど、受検方法に応じた対策をしましょう。
就職情報サイトや企業の採用サイトで最新の傾向を調べたり、実際にSPIを受けた先輩や友人から体験談を聞いたりすることも効果的です。
『キャリタス就活』の「ES・選考対策を探す」では、実際に応募者が体験した選考内容やSPI対策の工夫など、リアルな体験談を閲覧できます。企業ごとの就活情報とあわせて、SPI対策や本番前の準備に役立つ情報を効率よく収集できるので、ぜひ活用してください。

キャリアアドバイザーからの一言
SPI言語の対策は、できるだけ早めにはじめることが成功のポイントです。試験の2~3カ月前から問題集や頻出語句の暗記、模擬試験による実践練習などに取り組みましょう。早期から準備を進めることで、苦手分野の克服や時間配分の感覚も身につき、自信をもって本番に臨めます。
SPI言語に関するよくある質問
■Q.SPI言語の合格ラインは?
A.SPI言語の評価基準は企業によって異なりますが、一般的には大手企業で7割、中小企業で6割程度の正答率が目安とされています。人気企業や競争率の高い企業では8割以上の正答率が求められるケースもあるため、合格ラインは企業によって異なることを理解しておきましょう。
■Q.SPI言語の実施時間は?
A.SPI言語の実施時間は受検形式によって異なります。テストセンター、WEBテスティング、インハウスCBTでは、言語と非言語をあわせて約30分となっています。ペーパーテスティングの場合、言語のみで約30分実施されます。
企業や受検方法によって若干の差があるため、事前に案内を確認しておきましょう。
■Q.SPI言語が難しいと感じる理由は?
A.SPI言語が難しいと感じる理由は、出題形式が多様で語彙や読解、論理力など幅広い能力が問われるためです。また、問題数が多く短い制限時間内に解答する必要があるため、時間管理能力も求められます。
さらに、SPIは受検者の正答率に応じて問題の難易度が変化する仕組みが特徴です。そのため正解が続くと問題の難易度が上がり「急に難しくなった」と感じる場合があります。
■Q.SPI言語の対策はどのくらいの時期にはじめる?
A.SPI言語の対策は、本選考に向けて行う場合、一般的に大学3年生の10月からはじめるのが理想です。早めに問題集や模試を活用して基礎力を固め、苦手分野の克服や時間配分の練習を重ねることで、安定した得点力を身につけることができます。
なお、インターンシップ・キャリアの選考対策としては、3年生の5月ごろを目安にはじめましょう。

インターンシップの選考とは?本選考との関係や受かるポイントも解説!
インターンシップの選考を受ける方の中にはインターンシップの選考はどんな対策をすればいい?本選考に影響はある?など、不安に思う学生さんも多いでしょう。本記事では、インターンシップ選考の対策を徹底解説します。インターンシッ…
■Q.SPIが制限時間内に問題を解き終わらない場合はどうなる?
A.WEBテスティングやテストセンターでは1問ごとに制限時間があり、時間切れで自動的に次の問題へ移行します。また、問題を飛ばしたり、前の問題に戻ったりすることができないため注意が必要です。
一方、ペーパーテスティングは全体の制限時間内で自由に時間配分できるため、わかる問題から進めることも可能です。
SPI言語対策は出題形式の把握と計画的な学習がポイント
SPI言語試験で高得点を目指すには、二語の関係や語句の用法など多様な出題形式を理解し、問題集や模試で繰り返し練習することが大切です。限られた時間内で確実に得点するためには、苦手分野の把握と効率的な時間配分も重要となります。語彙力や文法力の強化も意識し、常に本番を意識した対策を積み重ねていきましょう。
『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE
キャリタス就活編集部
『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。










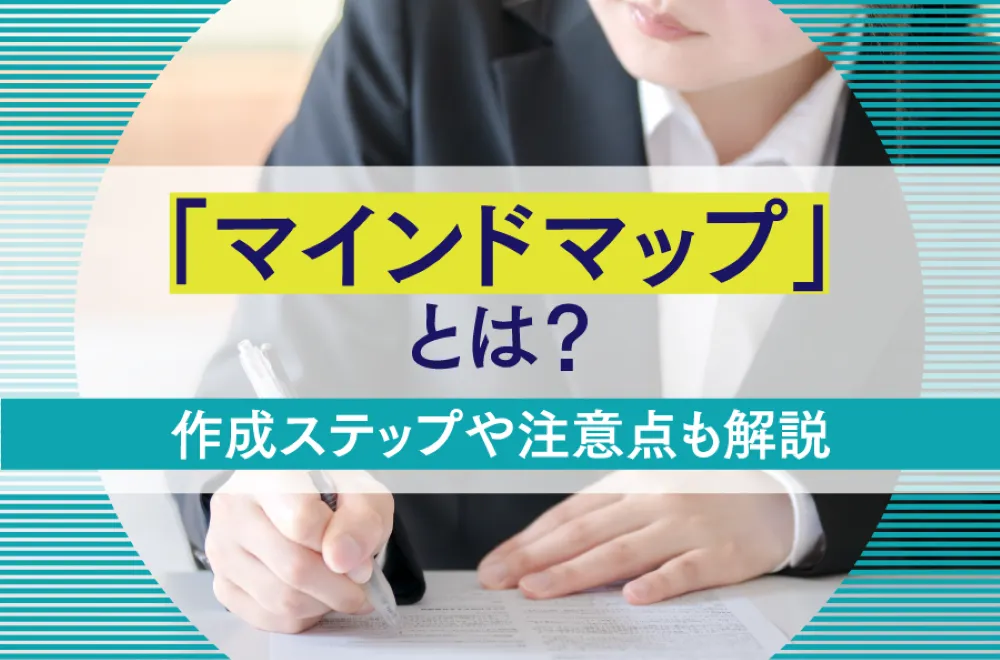
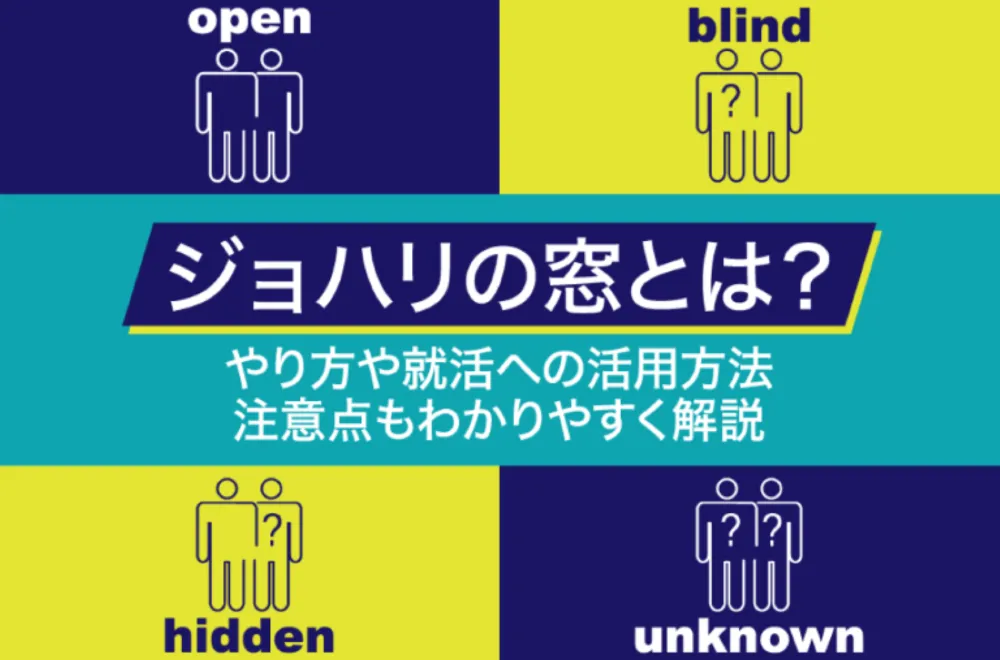






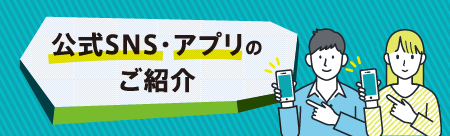
 LINE
LINE
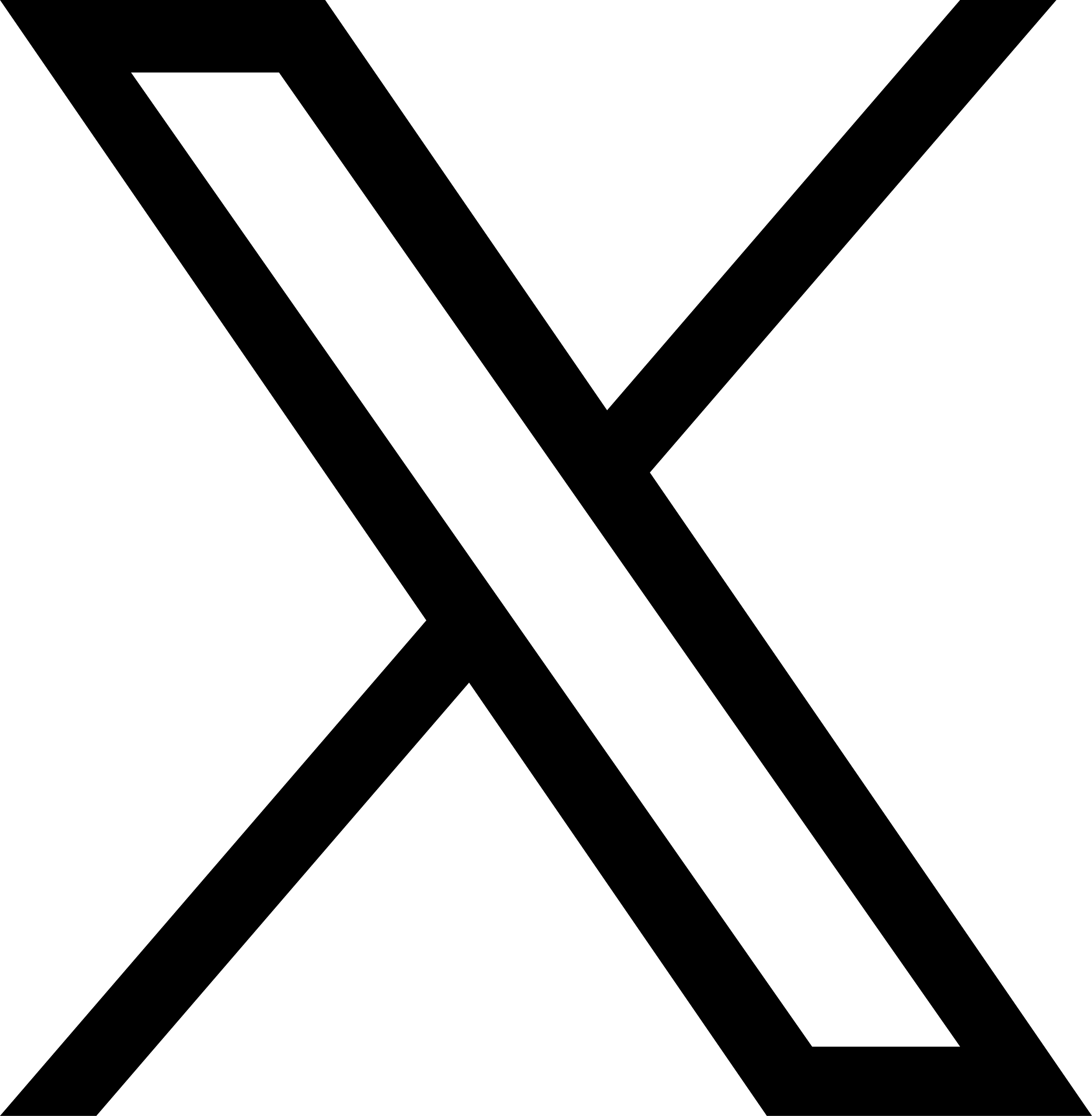 X
X
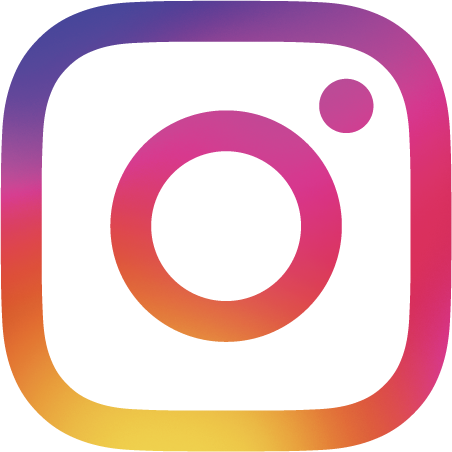 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube