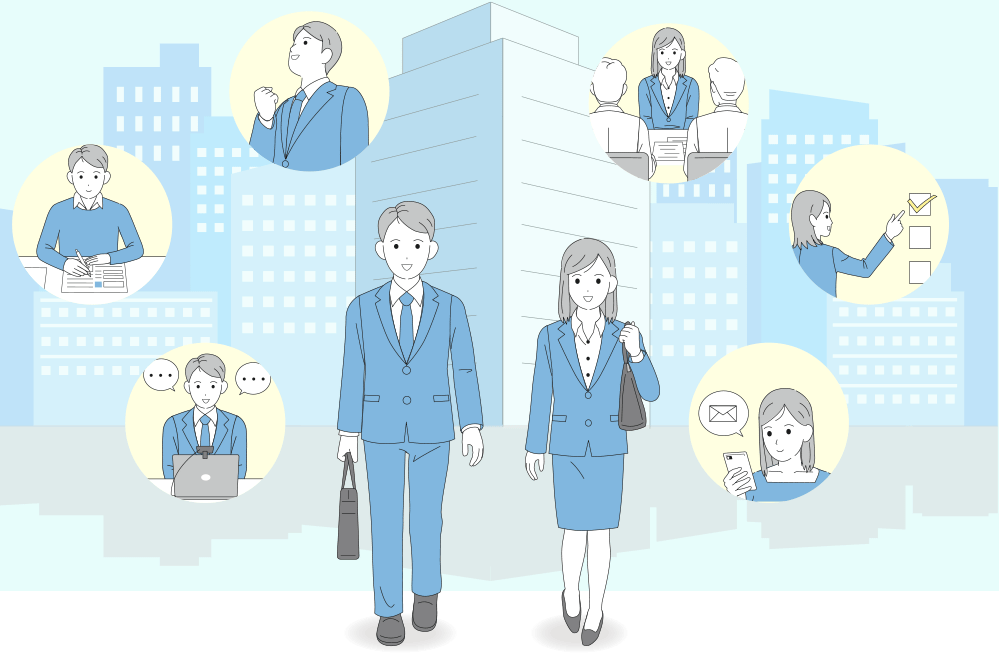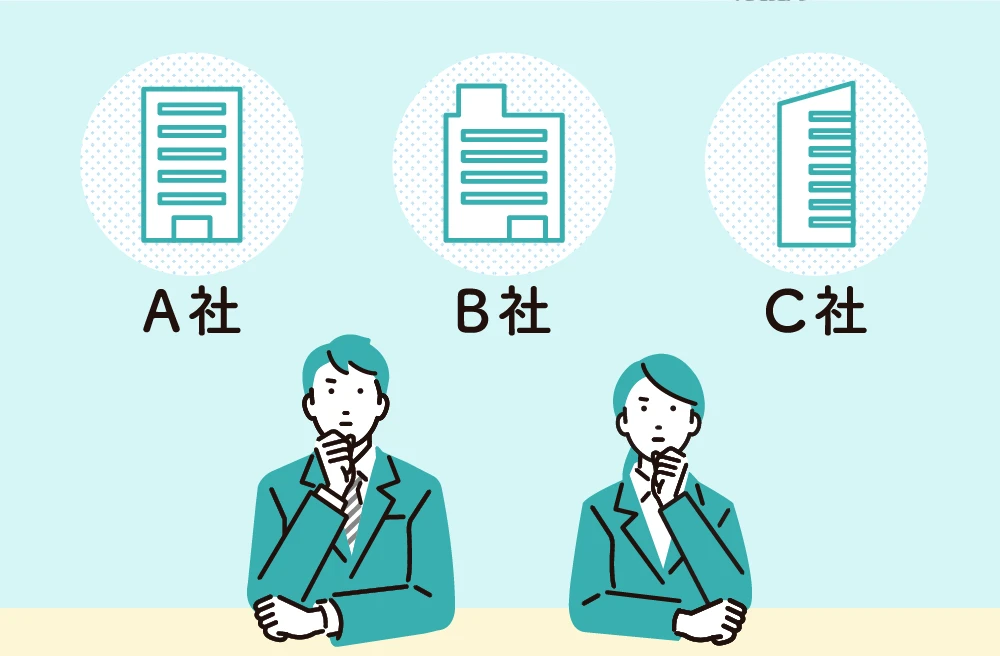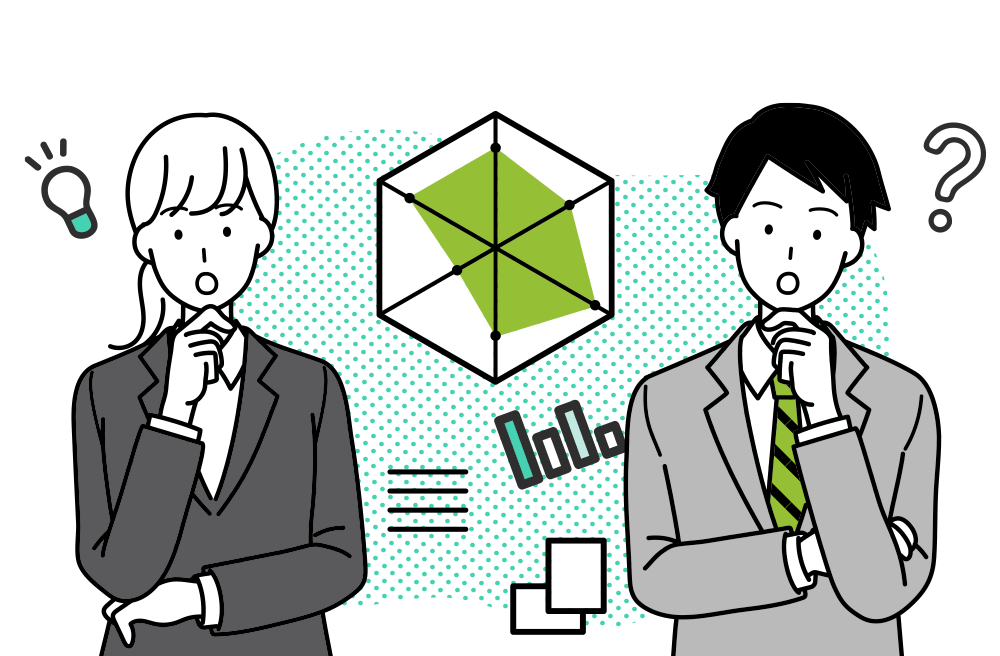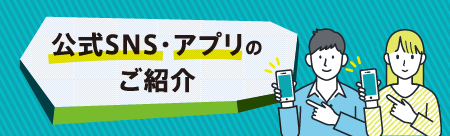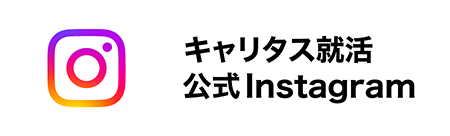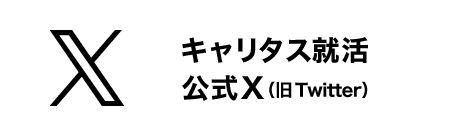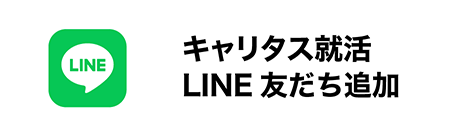グループディスカッション攻略術!役割理解と振り返りのコツ
就活ノウハウ公開日:2023.12.19

就職活動におけるグループディスカッション(通称「グルディス(GD)」)は、皆さんのコミュニケーション力や協調性、課題解決力が試される選考方法のひとつですね。その成功の鍵は、単なる話術や自己主張だけではありません。各役割の理解、適切な準備、そして採用担当者が見ているポイントを押さえ、対策をしていくことが重要です。また、終了後の振り返りをすることでさらなるレベルアップが期待できます。この記事では、グルディスにて自身の魅力を最大限に発揮し、次に繋げるためのポイントを詳しく解説します。
そもそもグループディスカッション(グルディス)とは
グルディスとは、大学や学年(学部生と院生が混ざる場合もあります。)などの異なる学生を5~6人程度にグループ分けし、テーマを与えて30分程度のディスカッションをさせ、その様子を観察することで評価を行う選考方法のことです。最後に結論のプレゼンを求められることも多いです。
そもそも企業は、なぜグルディスを選考に取り入れているのでしょうか。それはズバリ、あなたの「入社後の仕事ぶり」をイメージするためです。会議や日常のコミュニケーションでどのように他者と関わるか、グループ(組織・チーム)の目標達成に向けて、どのように貢献するのか、を見ようとしているのです。
またグルディスのポイントになるのは「合意形成」。単なる多数決や表面的な話し合いで安易に結論を出そうとすることはNGです。全メンバーが自分の考えや思い、関心事項を出し合い、全員の合意のもとで結論を導き出す前向きな話し合いが高評価の鍵になります。
一般に、グルディスは以下のような流れで進められます。
1.自己紹介:
初対面のメンバーと早期に和やかな雰囲気と関係性を作りましょう。笑顔で大学名と名前を伝える程度で十分です。
2.役割決め:
司会、タイムキーパー、書記、発表者など、主要な役割を決めます。
3.テーマの吟味:
提示されるテーマを確認し、曖昧な部分や受け取り方によって齟齬が出そうな部分があれば、あらかじめすり合わせを行います(「今回は、この言葉を『○○○』という意味で用いることにしましょう」など)。使う言葉が同じでもイメージする内容や意味が違っていては話が噛み合いません。メンバーが同じ認識を持てるように、枠組みを作りましょう。
4.個人ワーク:
テーマについて個人の意見をまとめる時間です。
※もし設けられた時間が短い場合は省略
5.ディスカッション:
個人ワークも踏まえながら、メンバーで意見を出し合い、話し合います。
6.まとめ:
グループとしての意見をまとめ、発表の準備をします。
短い時間内で、初めて会った人々とこれだけのことをしなければならないので、大変ですよね。でも、大丈夫。しっかり準備すれば、対応可能です!
グルディスには様々な「役割」が存在します。有名なのは、司会者、タイムキーパー、書記でしょうか。多くの就活生は、司会をはじめとするこれら3役だけが「役割」だとか、これら3役を取れなければ目立つことができないなどと考えがちですが、実はそうではありません。
メンバー一人ひとりが「自分の得意分野で能力を発揮して、グループにどう貢献できるか」を考えてグルディスに臨む、つまり自分ならではの「役割」を果たすことで、ディスカッションはより円滑に進行し成果も上がるのです。
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
【あわせて読みたい】
ずばり人事の本音を聞いてみた「グループディスカッション、司会じゃないと受かりませんか?」 株式会社三井住友銀行
■さまざまな役割
司会:
メンバーの意見を引き出し、まとめる。力で引っ張るのではなく、みんなの力をうまく利用し、前に進む力に変える「ファシリテーター」として活躍すると高評価。
タイムキーパー:
時間の流れをうまく利用して、制限時間内に結論を導けるようにグループ全体に働きかけていく。司会と協力してディスカッションを運営する重要な役割。
書記:
メモを取るだけではなく、必要な時には議論の推移や今までの総括を行い、メンバーの状況や議論の現在位置を明らかにする。
発表者:
グループで出した結論とその経緯を、決められた時間内で論理的に発表する。
また上記の役割が与えられなかった人でも、ディスカッションが本題からずれたことに気づき、皆に呼びかけて軌道修正を促したり、発言や質問などを積極的に行い、ディスカッションを活性化させるムードメーカー的な役割も大事です。
その日のメンバーがどんな人たちなのかをしっかり観察して、「このグループに対して自分が貢献できそうなこと」を探して、ディスカッションの質の向上するためには何をすれば良いのかを意識しましょう。
採用担当者はどこを見ている?
担当者は、単にグループディスカッションの結果だけを評価するわけではありません。参加者のコミュニケーション能力、論理的思考力、リーダーシップ、チームワークのスキルなど、様々な点を評価しています。また、自分の役割を理解し、課題解決に向けた努力をすることで、あなたの魅力や能力をアピールすることができます。
また、基本的な社会人マナーも非常に重要です。日頃から意識して身につけていきたいですね。
■マナーのポイント
・他者の意見を尊重し、受け入れる姿勢を大切に。攻撃的な態度はNG。
・予想外の状況や問題に対しては、冷静に対処。感情的になることはNG。
・社会人を意識した言葉遣いを意識しよう。
・姿勢や表情、声のトーンなど、非言語のマナーにも気を配ろう。
グルディスの事前対策はできるの?
グルディスは、直前にならないと議論のテーマや課題が明らかにならないことも珍しくありません。そんな状況に翻弄されず、自分の実力をしっかりとアピールするための対策は必須です。
しかし、具体的なテーマがわからない中で、どのように準備すれば良いのかわからない方も多いでしょう。そんな時は以下のようなテクニックをおさえておくと、未知なる課題にでも臆することなく挑むことができます。
1.意見の整理方法を習得:
限られた時間での意見整理のテクニックやフレームワーク(例:SWOT分析)を習得しておく。
※SWOT分析:外部環境と内部環境をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素で要因分析すること
2.他者の意見を聴き取る力の養成:
他者の意見を正確に理解し、それに基づいて返答や提案を行う能力を向上させる。
3.即興に対する対応力:
プレゼンテーションやスピーチの練習を通じて、即興での発言能力を養成する。
4.役割の柔軟性:
複数の役割を経験しておき、どの役割になっても柔軟に対応できるようにする。
5.時間管理能力:
限られた時間内での意見の整理や進行に伴う軌道修正や時間のコントロールを練習する。
6.ボディランゲージの意識:
非言語的なコミュニケーションも重要。適切な身振り手振りや視線の使い方を意識する。
その他、以下のようなポイントを押さえて、グルディスに臨むとよいですね。
・多様性を受容する姿勢を持とう。異なる視点や考え方を受け入れることで、思わぬアイディアを思いつくことも!
・共感力を強化しよう。他者の意見や立場に共感することで、コミュニケーションが円滑に。
・批判より建設的意見を出そう。他者の意見を単に批判するのではなく、建設的な提案を添えることでディスカッションのレベルが大きくアップ。
・「全員参加」を皆で作り上げていく気持ちを持とう。自分が意見を言ったら、必ず他の人に振ることを心がけるとよい。
・具体的な話(エピソードや体験)をできるだけ盛り込もう。
・意見を出せなくても、うなずきや合いの手は入れられる。常に参加している姿勢を、態度で示そう。
・人に伝える上でわかりやすい内容、スピードを意識しよう。
ディスカッション終了後の振り返り方法
グルディスが終了した後は、振り返りを行うことがとても大切です。グルディスの流れに沿って自分の発言や行動を振り返り、どの部分が良かったのか、どの部分に改善が必要なのかを考えてみましょう。
一人でやるのが難しければ、大学のキャリアセンターや友達、ご家族など人の力を借りて、話しながら振り返るとよいですよ。他者からのフィードバックを柔軟に受け入れる練習にもなりますね。
振り返りの結果は、必ず記録に残しておきましょう。自分で気がついた点、他者と話してフィードバックしてもらったことなどをメモしておけば、次回の参考にしたり改善状況をチェックしたりするのに大変役立ちます。
グルディスを振り返ることは、自分の強みや課題を客観的に捉える能力を継続的に磨いていくことに他なりません。振り返りをすることで、次回のグルディスの評価がアップすることはもとより、社会人になってからチームで業務を進める上で必須の能力に磨きをかけることもできます。
「グルディス=成長の機会」と捉えて、前向きに取り組んでいきましょう!

PROFILE
濱野 裕貴子
キャリアコンサルタント・公認心理師・ワークショップデザイナー
大学卒業後、教育系出版社に入社。通信教育の先生方のマネジメントを中心に、キャリアインタビューや機関誌の編集などに携わる。業務を通じて感じた「同じ仕事をしているにも関わらず働く理由や価値観の違いが出るのはなぜか」という問題意識から、「キャリア」に興味を持つように。14年間の勤務後独立し、以後、大学ではキャリアカウンセラーや非常勤講師、企業では研修講師として、学生や若手社会人のキャリア支援に当たってきた。演劇や落語、お笑いなどのパフォーミングアーツに触れることが大好きで、身体表現を使った自己理解のワークショップなども手掛けている。筑波大学人間総合科学研究科生涯発達専攻カウンセリングコース博士前期課程修了(カウンセリング修士)。