【SPI非言語を完全対策】頻出分野や例題・対策のコツは?公式一覧も
ES・選考対策公開日:2025.07.30
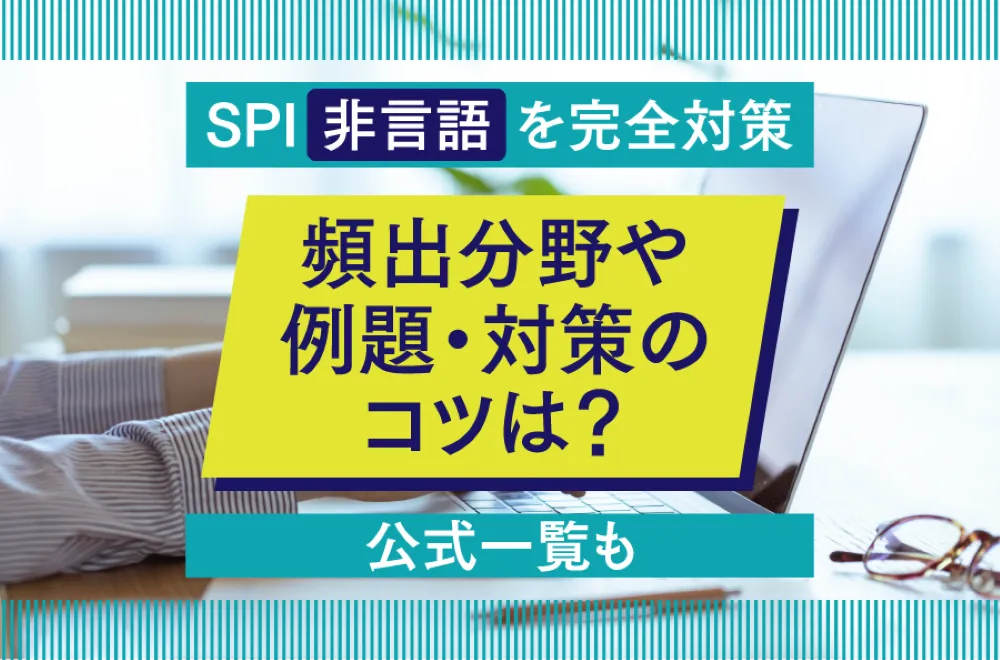
SPI非言語では、推論や確率、割合など中学・高校数学の知識が幅広く問われます。出題される問題数が多い上に制限時間が短いため、公式や解法パターンをしっかりと身につけておくことが大切です。本記事ではSPI非言語の特徴、分野別の出題内容を解説するほか、おさえておきたい公式一覧や対策のコツもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそもSPIとは?
SPIとは、企業が採用選考時に応募者に対して行う適性検査の1つです。
リクルートマネジメントソリューションズ社が開発した検査で、正式名称は「Synthetic
Personality Inventory」です。応募者の能力や性格を測るために多くの企業で新卒採用の選考に採用されており、特に「SPI3」が主流となっています。
SPIの受検方法は以下の4つです。通常、この中からいずれかを企業から指定され受検することになります。
テストセンター:企業指定の会場で専用のパソコンから受検する
WEBテスティング:自分のパソコンなどからオンラインで受検する
ペーパーテスティング:企業指定の会場で紙と鉛筆を使って受検する
インハウスCBT:企業のオフィス内・指定の会場で専用のパソコンから受検する
SPIについてさらに詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
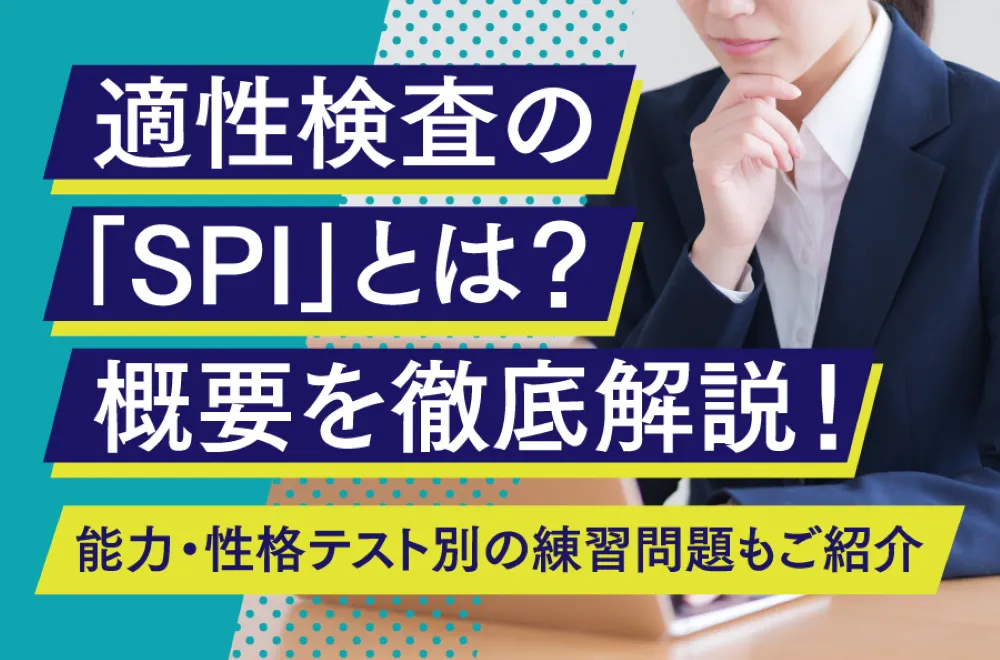
適性検査の「SPI」とは?概要を徹底解説!能力・性格テスト別の練習問題もご紹介
新卒就活の選考に多く採用されているSPIですが、「そもそもSPIとは?」「どんな問題が出る?」などわからない方もいらっしゃると思います。本記事では、SPIの基本的な概要から受検方法、性格検査・能力検査のそれぞれの問題も…
SPI非言語とは?

SPI非言語とはSPIの能力検査の一部で、主に論理的思考力や数的処理能力を測るテストです。出題内容は中学・高校レベルの数学に似ており、推論・確率・割合など幅広い分野で構成されます。難易度はそれほど高くなく、対策をしっかり行えば高得点を狙うことは十分可能です。
なお、下記の記事ではSPI言語について詳しく解説しているので、参考にご覧ください。
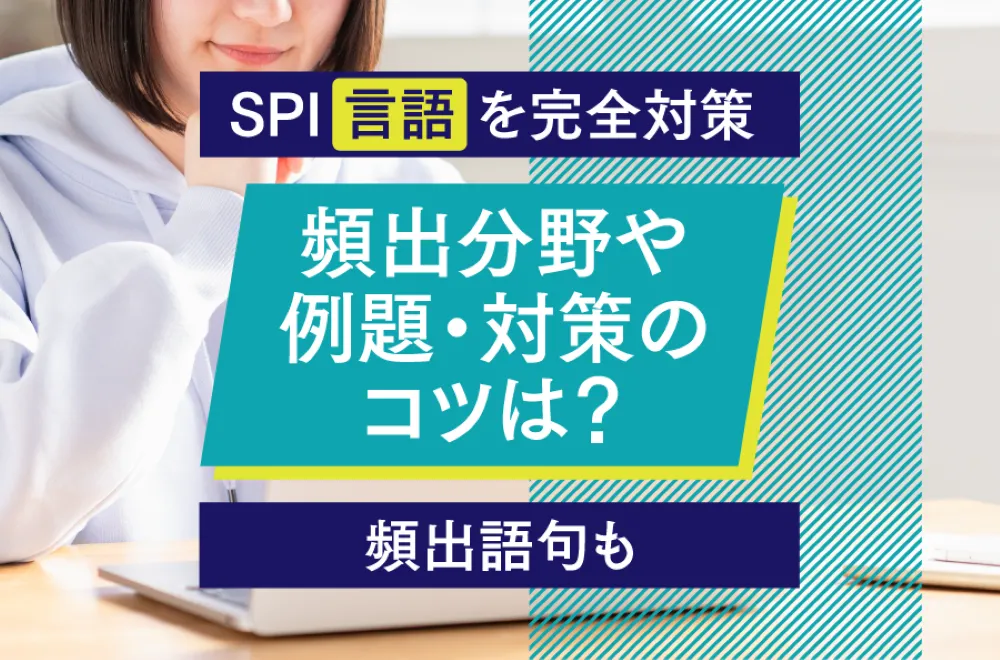
【SPI言語を完全対策】頻出分野や例題・対策のコツは?頻出語句もご紹介
SPIの言語のテストでは語彙力や熟語の知識、長文読解力が問われるため、頻出分野の練習問題や例題を繰り返し解くことが高得点のカギとなります。時間制限も厳しいため、模試や問題集で本番を意識した対策が重要です。この記事ではS…
SPI非言語の特徴
SPIの能力検査を簡単に解説すると、SPIの言語分野が国語、非言語分野は数学に近い位置づけになります。ここではその非言語の特徴についてみていきましょう。
■中学・高校で習う数学が出題範囲
SPI非言語は、主に中学・高校レベルの数学の問題が出題されます。基本的な公式や解法パターンをしっかり理解していれば十分に対応可能です。
ただし、出題範囲が広いため、すべての分野をバランスよく対策する必要があります。直前の短期集中の学習だけですべてを網羅するのは難しいため、早めに対策をはじめることが重要です。
■解答時間が短く、問題数が多い
SPI非言語では、限られた時間で多くの問題を解く必要があります。1問あたりの解答時間は約1分と非常に短いため、正確な計算力と素早い判断力が欠かせません。
ただ早く解くだけではミスが増えてしまうため、問題演習を重ね出題パターンに慣れ、効率よく解く力を養うことが大切です。
■合格ラインの目安は6~7割以上
SPI非言語の合格ラインは、企業や選考基準によって異なりますが、一般的には6~7割以上の正答率が目安とされています。特に大手企業や人気企業では、より高い得点が求められる傾向があります。
まずは、7割以上の得点を目指し、基本的な対策を徹底することが重要です。安定して7割以上を獲得できるように幅広い分野を満遍なく対策しましょう。
【出題分野別】SPI非言語の例題と対策ポイント
SPI非言語の頻出分野は、以下の9つです。これらの分野から幅広く出題されるため、バランスよく学習する必要があります。ここでは、各分野の出題傾向や形式を理解していきましょう。
| 分野 | 出題内容 |
|---|---|
| 表の読み取り | 表やグラフから必要な数値を読み取り、計算や比較を行う |
| 推論 | 与えられた条件や情報を基に、論理的に結論や関係性を導き出す |
| 集合 | 複数のグループや条件を整理し、重複や除外に注意しながら該当する人数や数を求める |
| 場合の数 | 並べ方や組み合わせの総数を求める |
| 確率 | ある事象が起こる確率を求める |
| 金額計算 | 割増・割引や損益など、金額に関する計算を行う |
| 分担計算 | 複数人で作業を分担したり、分割払いした際の計算を行う |
| 速度算 | 速さ・時間・距離の関係を利用して、追い越す時刻や出会う時刻などの計算を行う |
| 割合 | 全体に対する割合や比率を求める |
※表をスクロールしてご覧ください
| 分野 | 出題内容 |
|---|---|
| 表の読み取り | 表やグラフから必要な数値を読み取り、計算や比較を行う |
| 推論 | 与えられた条件や情報を基に、論理的に結論や関係性を導き出す |
| 集合 | 複数のグループや条件を整理し、重複や除外に注意しながら該当する人数や数を求める |
| 場合の数 | 並べ方や組み合わせの総数を求める |
| 確率 | ある事象が起こる確率を求める |
| 金額計算 | 割増・割引や損益など、金額に関する計算を行う |
| 分担計算 | 複数人で作業を分担したり、分割払いした際の計算を行う |
| 速度算 | 速さ・時間・距離の関係を利用して、追い越す時刻や出会う時刻などの計算を行う |
| 割合 | 全体に対する割合や比率を求める |
■表の読み取り
表の読み取りは、表やグラフに記載された数値やデータを基に、必要な情報を抽出して問いに答える問題です。限られた時間内で適切なデータを見つけ、正確に計算する力が求められます。
特に割合や増加率の計算問題が頻繁に出題されるため、公式や基本的な計算方法をしっかりと覚えておくことが大切です。また、効率的に情報を探す練習を繰り返しましょう。
例題:
次の表は、ある企業の第2四半期(4月~6月)における3つの店舗の売上(単位:万円)を示しています。

このとき、以下の問いに答えなさい。
問:第2四半期(4月〜6月)の累計売上がもっとも高い店舗はどこか。
1.A店
2.B店
3.C店
4.3店舗すべて同じ
解答:1.A店
解説:
各店舗の4月〜6月の売上を合計すると以下のようになります。
A店:120 + 130 + 125 = 375万円
B店:110 + 115 + 120 = 345万円
C店:100 + 105 + 110 = 315万円
したがって、累計売上がもっとも高いのはA店です。
■推論
推論は、与えられた情報から正しい順序や内訳を導き出す問題です。公式が存在せず、論理的な思考力や情報整理力が問われるため、やや難易度が高いとされています。
推論問題は複数の出題パターンがあり、それぞれに応じた解き方を身につけることが大切です。まずは問題文を丁寧に読み取り、論理的に正しい選択肢を選ぶ練習を積みましょう。
例題:
A、B、Cの3人が、ある日の昼食について次のように発言しました。
A:今日の昼食はカレーだった。
B:今日の昼食はカレーかパスタだった。
C:今日の昼食はパスタだった。
3人のうち、1人だけがうそをついている場合、次の選択肢から正しいものを1つ選びなさい。
1.Aが正しければBも必ず正しい
2.Cが正しければAは必ず正しい
3.Bが正しければCも必ず正しい
解答:1.Aが正しければBも必ず正しい
解説:
Aが正しい(昼食はカレーだった)場合、Bの「昼食はカレーかパスタだった」も必ず正しくなります。Cの「昼食はパスタだった」はうそになるため、「1人だけがうそをついている」という条件を満たします。
■集合
集合は、記載された条件を基に、特定の要素や関係性を導き出す問題です。条件をベン図やカルノー表などの図に整理し、視覚的に理解することで解答しやすくなります。
出題パターンは限られているため、図の書き方や条件の整理方法をしっかりと身につけて、複雑な条件を整理できる力をつけておきましょう。
例題:
あるクラスの生徒40人に、サッカーと野球のどちらが好きかをアンケートしたところ、次の結果が得られました。
・サッカーが好き:25人
・野球が好き:18人
・どちらも好き:8人
このとき、サッカーも野球も好きでない生徒は何人か答えなさい。
解答:5人
解説:
「サッカーが好きな人数」と「野球が好きな人数」の和から「どちらも好きな人数」を引いた数が「どちらかが好きな人数」になります。
サッカーまたは野球が好きな人数は、25+18−8=35人です。
クラス全体は40人なので、どちらも好きでない人数は、40−35=5人となります。

■場合の数
場合の数は、与えられた条件から並べ方や組み合わせの数を求める問題です。対策テキストや対策サイトでは「順列」「組み合わせ」に分類されます。「並べる」「列」「順番」などの言葉が出てきたら「順列」、「選ぶ」「組み合わせ」「グループ」などの言葉が出てきたら「組み合わせ」と覚えておくとよいでしょう。
それぞれ「組み合わせ 順番あり」「組み合わせ 順番なし」の公式を使えるようにしておくことが重要です。
出題パターンはある程度決まっており、必要な公式を覚えることができればそれほど難しくはありません。問題演習に繰り返し取り組み、公式の意味や使い方をしっかりとおさえておきましょう。
例題:
A、B、C、Dの4人が一列に並んで写真を撮るとき、AとBが隣り合う並び方は全部で何通りあるか答えなさい。
1.6通り
2.12通り
3.24通り
4.36通り
解答:2.12通り
解説:
まず条件(AとBが隣り合う)と人数(A、B、C、D → 合計4人)を整理します。
条件を満たすにはAとBが隣り合うことが必要のため、AとBを1つのセットとして扱うと、「AB」または「BA」の2通りがあります。
AとBのセット(ABまたはBA)を1人分と考えると、全部で3人を並べることになります。
・AB(またはBA)のセット
・C
・D
つまり、3人(=3つのかたまり)を並べる場合と同じで、並べ方は3!(※)=6通りあります。
セット内の順番(ABとBAで2通り)も考慮して掛け算すると、6 × 2 で並べ方は 12通りとなります。
※「3!」(3の階乗)=「3×2×1」
「階乗(かいじょう)」とは、ある自然数から1までのすべての整数をかけ合わせたもの。階乗は、ものの並べ方(順列)や組み合わせ(組合せ)を求めるときによく使われる。
■確率
確率は、くじやサイコロ、コインなどの題材を基に、特定の事象が起こる確率を求める問題です。公式の意味や使い方をしっかりおさえておけば、比較的得点しやすい分野です。以下の5つの公式を覚えて、パターンに応じた練習を重ねましょう。
・組み合わせ
・確率の法則
・積の法則
・和の法則
・余事象の確率
例題:
AさんとBさんが、それぞれルーレットを1回ずつ回します。このルーレットは1から10までの数字が均等に出るものとします。出た数字の大きい方が勝ち、同じ数字なら引き分けです。このとき、AさんがBさんに勝つ確率を求めなさい。
1.9/20
2.11/20
3.13/20
4.7/20
解答:1. 9/20
解説:
AさんとBさんの出目はそれぞれ1~10の10通りで、全通り数は10×10=100通りです。AさんがBさんに勝つのは、Aさんの出目がBさんの出目より大きい場合です。
Bさんの出目を固定して考えると、Aさんが勝つ場合の数は以下のようになります。

上の表からAさんが勝つ場合の合計は、9+8+7+6+5+4+3+2+1+0=45通りとなります。
したがって、AさんがBさんに勝つ確率は、45/100=9/20です。
■金額計算
金額計算は、商品の値段設定や、企業の利益計算など日常生活やビジネスで頻繁に登場する金額の変動を求める問題です。定価と割引の関係、利益や損失の計算など、基本的な計算力が求められます。
金額計算の問題では、用語の意味や計算方法をしっかり理解しておくことはもちろん、基本的な計算力を高めることが重要です。以下の5つの用語と計算方法はしっかり覚えておきましょう。また、基本の公式として「料金の割引」「損益算」も要チェックです。
原価:商品やサービスを生産・仕入れるためにかかった費用
定価:販売者が決めた、商品やサービスの標準的な価格
売値:実際に販売する際の価格
利益率:売上高や売値に対する利益の割合
割引率:定価や売値からどれだけ値下げするかを示す割合
例題:
1個の原価が600円の商品を100個仕入れて、原価の2割の利益が出るように定価をつけました。しかし、70個しか売れなかったので、残りは定価の1割引きにしてすべて売り切りました。このとき利益の合計はいくらか答えなさい。
A.9,840円
B.12,000円
C.10,800円
D.11,400円
E.8,400円
解答:A.9,840円
解説:
まず、原価が600円の商品を100個仕入れた場合、商品を仕入れるのにかかったお金の合計は、600円×100個で60,000円になります。次に、この商品には原価の2割の利益を見込んで定価がつけられています。つまり、定価は600円の1.2倍=720円です。
実際にはこの定価で70個が売れました。定価で売れた分の売上は、720円×70個で50,400円です。
残りの30個は、定価の1割引きで売ることになりました。1割引きの価格は720円の0.9倍、648円です。この価格で売れた分の売上は、648円×30個で19,440円です。
全体の売上は、定価で売れた分と割引で売れた分を足して、50,400円+19,440円で69,840円になります。
ここから、仕入れたときの原価合計60,000円を引くと、利益の合計は9,840円となります。
■分担計算
分担計算は、複数人で作業する場合の所要時間や支払総額、手数料などを求める問題です。
出題パターンはある程度決まっており、「分割払い」や「仕事算」の2つに大別されます。分割払いは、旅行や食事の代金を人数で割るなど、お金や費用を分ける計算です。仕事算は、複数人で協力して作業するとき、かかる時間や進み具合を計算する問題です。
どちらも分数や割合の計算が多いため、条件を正確に整理して必要な情報を素早く見つける力が重要になります。
例題:
ある予備校のテスト採点をXさんとYさんの2人で行います。採点は2人で行うと6時間かかります。ある日の採点で、Xさん1人で2時間作業し、Yさん1人で残りの採点をしました。このときYさんは採点に12時間かかりました。この採点作業をXさん1人だけで行う場合、どのくらい時間がかかりますか。
A.5時間
B.10時間
C.12時間
D.18時間
解答:B.10時間
解説:
まず、全体の採点量を「1」とし、Xさんは1時間で「x」、Yさんは1時間で「y」の採点ができるとします。XさんとYさんが2人で一緒に作業すると6時間で終わるので、2人が6時間働いた量が全体の採点量「1」になります。つまり、以下の式で表せます。
6x+6y=1
また、Xさんが2時間、Yさんが12時間働いても全体の採点が終わるので、以下の式も成り立ちます。
2x+12y=1
この2つの式を比べます。上の式(6x+6y=1)を両辺2倍すると、12x+12y=2です。上の式から下の式を引くと、以下のようになります。
(12x+12y)−(2x+12y)=2−1
10x=1
x=1/10
これで、Xさんは1時間で全体の1/10の採点ができることがわかります。
Xさんが1人で全体の採点を終えるのにかかる時間を「t時間」とおきます。
1/10×t=1
t=10
つまり、Xさんが1人で全部の採点をする場合、10時間かかるということになります。
■速度算
速度算は、「速度」「時間」「距離」の関係式を基に、平均速度や移動時間などを求める問題です。出題パターンは「平均速度」「2人(または複数人)が出会う時刻」「後から追いつく・追い越す時刻」などにわかれます。
速度算は、公式の意味や使い方をしっかりと理解し、条件を整理してから計算に入ることがポイントです。「速さ・時間・距離」の公式を覚えておけば比較的簡単に解ける分野です。
例題:
RさんとSさんの歩くスピードは、Rさんが3.0km/時、Sさんが4.0km/時です。Rさんは駅から公園まで40分かかります。Rさんが駅から公園へ、Sさんが公園から駅へ向かって同時に歩きはじめた時、2人が出会うのは何分後か求めなさい。必要に応じて、最後に小数点第3位以下を四捨五入してください。
A.12分
B.15分
C.17分
D.20分
解答:C.17分
解説:
駅から公園までの距離は、Rさんが40分かかるので3.0×40/60=2.0kmです。RさんとSさんの速度の和は3.0+4.0=7.0km/時なので、2人が近づく速さは7.0km/時です。出会うまでの時間は2.0÷7.0≒0.286時間=約17.14分となり小数点第3位を四捨五入すると17分になります。
■割合
割合は、全体に対する一部の割合や比率を求める問題です。文章で状況が説明されるため、内容を正確に読み取り条件を図や表に整理する力がポイントとなります。
「割合」の公式や基本的な計算方法をおさえておけば、比較的得点しやすい分野です。その上で、問題文の条件を丁寧に読み取り、必要な情報を素早く見つける練習を重ねておきましょう。
例題:
あるカフェでコーヒーの価格を20%値上げしました。すると販売個数が10%減少しましたが、全体として売上は増えました。売上高は何%増加したか求めなさい。必要に応じて小数点第二位以下を四捨五入してください。
A.4.0%
B.6.0%
C.8.0%
D.10.0%
解答:C.8.0%
解説:
以前のコーヒー価格を10円、販売個数を100個と仮定すると以下のようになります。
以前の売上:10円 × 100個 = 1000円
値上げ後の価格:10円 × 1.20 = 12円
販売個数:100個 × 0.90 = 90個
値上げ後の売上:12円 × 90個 = 1080円
したがって、売上の増加率は、(1080円 − 1000円) ÷ 1000円 × 100 = 8.0%となります。

キャリアアドバイザーからの一言
SPI非言語試験では、誤謬率(誤答の割合)は評価されません。したがって、わからない問題でもとりあえず解答しておくことが大切です。時間配分を意識し、最後まで冷静に問題に取り組む姿勢が高得点につながります。
SPI非言語の公式一覧
例題でも解説した通り、SPI非言語では公式を覚え使えるようにしておくことが高得点を狙うために非常に重要です。以下で、SPI非言語の問題で主に必要となる公式を確認していきましょう。
| 問題 | 公式 |
|---|---|
| 集合 | 和集合:A ∪ B = A + B – A ∩ B 共通部分:A ∩ B = 両方に含まれる部分 補集合:A’ = 全体 – A |
| 料金の割引 | 割引後の価格 = 定価 × (1 – 割引率) |
| 損益算 | 原価 + 利益 = 売価 利益率 = (売価 – 原価) ÷ 原価 × 100 |
| 割合 | 全体 × 割合(%を小数に変換) 「は」÷「の」の法則 内項の積 = 外項の積 |
| 組み合わせ 順番あり | 順列:nPr = n × (n-1) × … × (n-r+1) |
| 組み合わせ 順番なし | 組み合わせ:nCr = n! ÷ (r! × (n-r)!) |
| 速さ・時間・距離 | 速さ = 距離 ÷ 時間 時間 = 距離 ÷ 速さ 距離 = 速さ × 時間 |
| 仕事算 | 1/A + 1/B = 1/T(A、Bはそれぞれの仕事時間、Tは全体の仕事時間) |
| 四捨五入 | 指定された位の次の位を四捨五入(例:小数点第2位で四捨五入) |
| 一次方程式 | ax + b = c → x = (c – b)/a |
| 連立方程式 | ax + by = c dx + ey = f (加減法や代入法で解く) |
| 平均世帯人数 | 平均世帯人数 = 合計世帯人数 ÷ 世帯数 |
| 通過算 | 速さ = (列車の長さ + トンネルの長さ) ÷ 通過時間 |
| 流水算 | 上り:静水時の速さ – 川の流れの速さ 下り:静水時の速さ + 川の流れの速さ |
| 確率 | 確率 = (該当する場合の数) ÷ (全事象の数) |
| 増加率 | 増加率 = (増加量 ÷ 基準値) × 100 |
| 年齢算 | 現在の年齢 ± 年数 = 未来または過去の年齢 |
| 濃度算 | 濃度 = (溶質 ÷ 溶液) × 100 |
※表をスクロールしてご覧ください
| 問題 | 公式 |
|---|---|
| 集合 | 和集合:A ∪ B = A + B – A ∩
B 共通部分:A ∩ B = 両方に含まれる部分 補集合:A’ = 全体 – A |
| 料金の割引 | 割引後の価格 = 定価 × (1 – 割引率) |
| 損益算 | 原価 + 利益 = 売価 利益率 = (売価 – 原価) ÷ 原価 × 100 |
| 割合 | 全体 ×
割合(%を小数に変換) 「は」÷「の」の法則 内項の積 = 外項の積 |
| 組み合わせ 順番あり | 順列:nPr = n × (n-1) × … × (n-r+1) |
| 組み合わせ 順番なし | 組み合わせ:nCr = n! ÷ (r! × (n-r)!) |
| 速さ・時間・距離 | 速さ = 距離 ÷ 時間 時間 = 距離 ÷ 速さ 距離 = 速さ × 時間 |
| 仕事算 | 1/A + 1/B = 1/T(A、Bはそれぞれの仕事時間、Tは全体の仕事時間) |
| 四捨五入 | 指定された位の次の位を四捨五入(例:小数点第2位で四捨五入) |
| 一次方程式 | ax + b = c → x = (c – b)/a |
| 連立方程式 | ax + by = c dx + ey = f (加減法や代入法で解く) |
| 平均世帯人数 | 平均世帯人数 = 合計世帯人数 ÷ 世帯数 |
| 通過算 | 速さ = (列車の長さ + トンネルの長さ) ÷ 通過時間 |
| 流水算 | 上り:静水時の速さ –
川の流れの速さ 下り:静水時の速さ + 川の流れの速さ |
| 確率 | 確率 = (該当する場合の数) ÷ (全事象の数) |
| 増加率 | 増加率 = (増加量 ÷ 基準値) × 100 |
| 年齢算 | 現在の年齢 ± 年数 = 未来または過去の年齢 |
| 濃度算 | 濃度 = (溶質 ÷ 溶液) × 100 |
SPI非言語試験の対策のコツ

SPI非言語の問題は、中学・高校レベルで難易度はそれほど高くないとはいえ、対策せずに臨むと合格ラインに届かない可能性もあります。ここでは、おさえておくべき試験対策のポイントをみていきましょう。
■公式や解法パターンを暗記する
SPI非言語の対策は、公式や解法パターンをしっかり暗記することが重要です。公式や解法パターンを理解しておくことで、解ける問題も多く、短時間で多くの問題を処理できるようになります。通学や休憩の合間などの時間を活用して、公式を徹底的に暗記しましょう。公式一覧はこちらを確認してみてください。
■練習問題を繰り返し解く
SPI非言語の対策は、練習問題を繰り返し解くことが基本です。難問よりも基本的な問題をミスなく確実に解くことが大切であり、解ける問題を確実に正解できるようにすることが高得点のポイントとなります。
一冊の問題集を何度も繰り返し解くことで、問題のパターンや出題傾向を理解しやすくなり、頻出問題にも強くなります。また、同じ問題を解き直していると、解法が自然に身につき、試験本番でも落ち着いて取り組めるようになるでしょう。
下記でおすすめのSPI対策本を紹介しているので、参考にご覧ください。
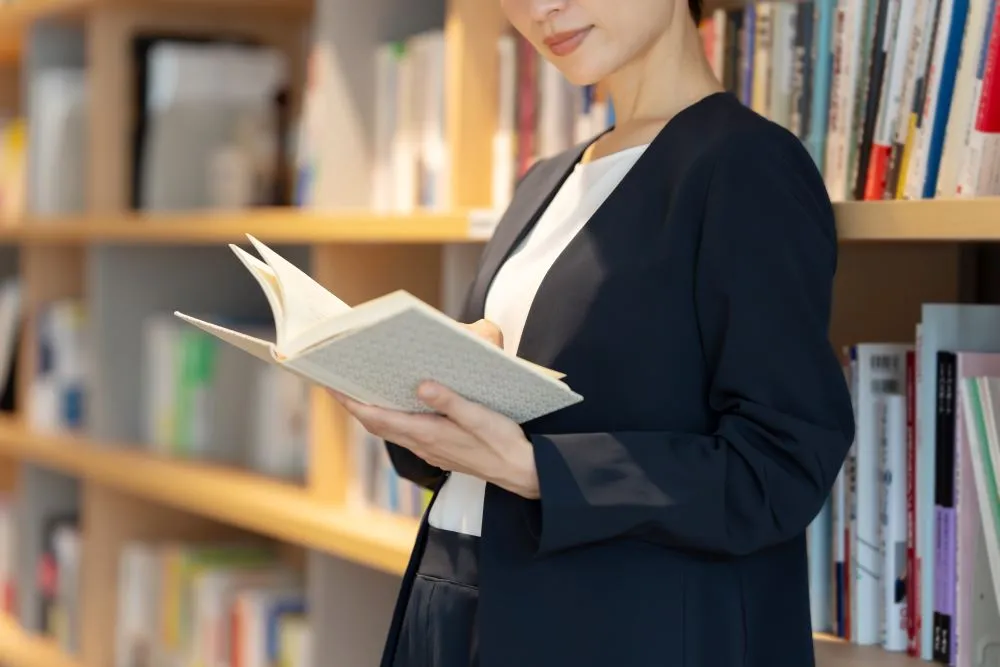
【27卒向け】SPI対策におすすめの本12選!選ぶときのポイントも解説
就活の第一関門として重要な「SPI」。どのように対策すればとよいかわからない方も多いでしょう。特に大手企業や人気企業を希望している場合は、入念な対策が欠かせません。この記事では、効果的にSPI対策できるおすすめの本をご…
■模擬試験を受ける
SPI非言語の対策は、模擬試験を活用し実際の試験形式に慣れておくことも大切です。模擬試験では、制限時間内に問題を解く感覚を養うことができるため、限られた時間内で多くの問題を解く必要があるSPIにおいては特に有効です。試験の流れや時間配分が自然と身につき、本番でもスムーズに解答できるようになります。
模試を受けたあとは、解けなかった問題や時間内に終わらなかった問題をしっかり復習しましょう。
『キャリタス就活』では、WEBテストを手軽に体験できるコンテンツや、「SPI」「玉手箱」の模試を受けられるコンテンツをご提供しています。
【お試し!WEBテスト】
「お試し!WEBテスト」は、WEBテストやテストセンターなど、パソコンで受検する環境を再現したコンテンツです。「言語問題」5問と「非言語問題」10問が用意されており、制限時間も設定されているため、よりリアルな環境でチャレンジできます。
本番さながらの緊張感の中で練習することで、本番では心の余裕をもって検査を受けることができます。
【キャリタス模試】
キャリタス模試では「SPI形式問題」「玉手箱形式問題」「一般常識問題」が受けられます。月に1回、10日間の受検期間を設けて模試を実施しており、全国順位や全国平均点と比較して自分の実力を測ることができます。
実施期間終了後は過去問として模試を受けられます(順位は出ません)。
■苦手分野を反復する
模擬テストや練習問題に取り組んでいると、自分がどの分野でつまずきやすいのかが自然と見えてきます。単に「たくさん問題を解く」だけでなく、苦手な分野に的を絞って反復学習することも非常に大切です。
間違えた問題や迷った問題は、ノートやメモにまとめておき、定期的にそのノートを見返しながら復習することで苦手意識を少しずつ減らしていけます。その際も、「なぜ間違えたのか」を意識して取り組むことで、より確実な実力アップにつながるでしょう。
■受検企業の出題形式や問題の傾向を確認する
SPIは企業によって出題形式や傾向が異なるため、まずは受検する企業の情報をしっかり確認しておくことが重要です。パソコンや筆記など受検方法の違いに応じて対策を進めましょう。
基本的にWEBテスティングでは電卓の使用が許可されている一方で、筆記や企業指定の受検方法(テストセンター・ペーパーテスティング・インハウスCBT)では電卓が使用できない場合が多いです。また、パソコンで受検する際はシステム上、一度解いた問題は戻れない形式が多いなど、操作面でも違いがあるため、それぞれの特徴に合わせて準備を進めることが大切です。
また、出題科目の傾向を把握しておけば、効率的な学習計画を立てられます。就職情報サイトで調べたり、実際にSPIを経験した先輩や友人から話を聞いたりするなどして情報収集しておきましょう。
『キャリタス就活』の「ES・選考対策を探す」では、実際に応募者が体験した選考内容やSPI対策の工夫など、リアルな体験談を閲覧できます。企業ごとの就活情報とあわせて、SPI対策や本番前の準備に役立つ情報を効率よく収集できるので、ぜひ活用してください。
SPI非言語に関するよくある質問
■Q.SPI非言語が「難しすぎる」「できない」と感じる。どんな対策がおすすめ?
A.SPI非言語が難しく感じる場合は、まずは基本公式をしっかり覚え、繰り返し練習問題を解くことが重要です。また練習問題も繰り返し解き、間違えた部分は必ず復習します。苦手分野がわかったら重点的に取り組みましょう。苦手意識をもつ分野こそ、基礎から丁寧に学習し、自信をつけることが合格への近道となります。
■Q.SPI非言語の合格ラインは?
A.SPI非言語には明確な合格点は設けられていませんが、SPI全体では一般的に正答率6~7割以上が合格ラインの目安とされています。企業や職種によって基準は異なり、大手企業や人気業界では7割以上、場合によっては8割以上の正答率が求められることもあります。まずは7割以上の得点を目指して対策を進めると安心です。
■Q.SPI非言語は電卓を使ってもいい?
A.SPI非言語は、WEBテスティングやインハウスCBTでは電卓の使用が認められていますが、テストセンターやペーパーテスティングでは使えません。電卓が使える場合も安心せず、普段から計算力やスピードを意識した練習が大切です。なお、電卓が使える試験では、問題の難易度が上がる傾向がある点にも注意しましょう。
■Q.SPI非言語の対策に必要な時間はどれくらい?
A.SPI非言語の対策に必要な時間には個人差がありますが、基礎からしっかり対策したい場合、少なくとも20~30時間ほどかけて準備するのが一般的です。頻出分野の公式や解法パターンを覚え、練習問題を繰り返し解くことで、効率的に実力を高めることができます。
SPI非言語の攻略は基礎固めと頻出分野の反復練習から
SPI非言語で高得点を目指すには、公式や解法パターンをしっかり身につけることが大切です。頻出分野の反復練習により、幅広い出題範囲にも柔軟に対応できるようになります。基礎をしっかり固めたら、苦手分野の克服に注力し、自信をもって本番に臨めるよう準備しましょう。
『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。
PROFILE
キャリタス就活編集部
『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。
「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。







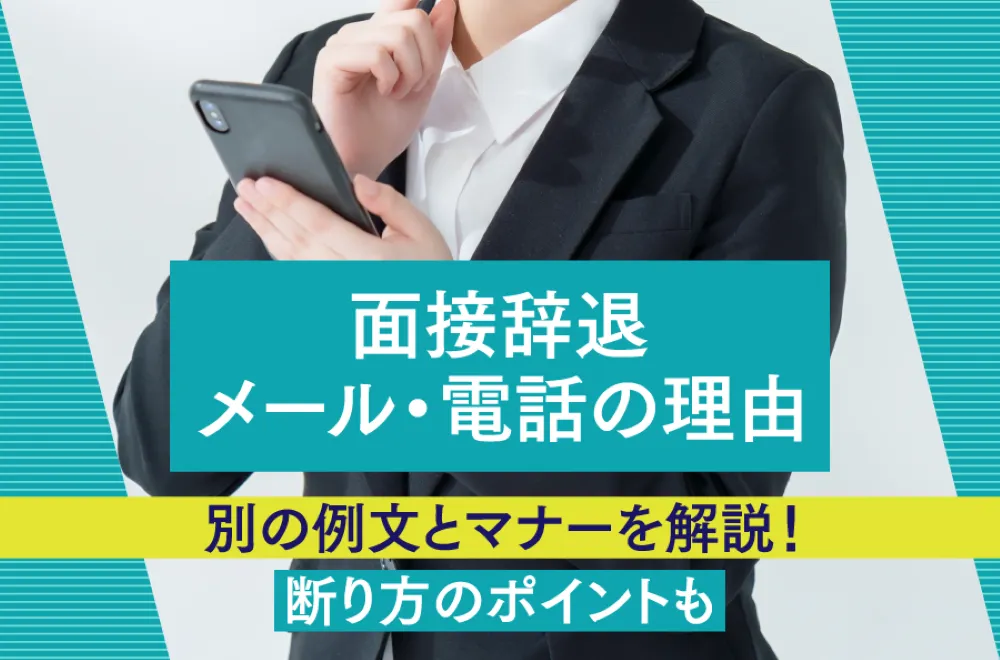








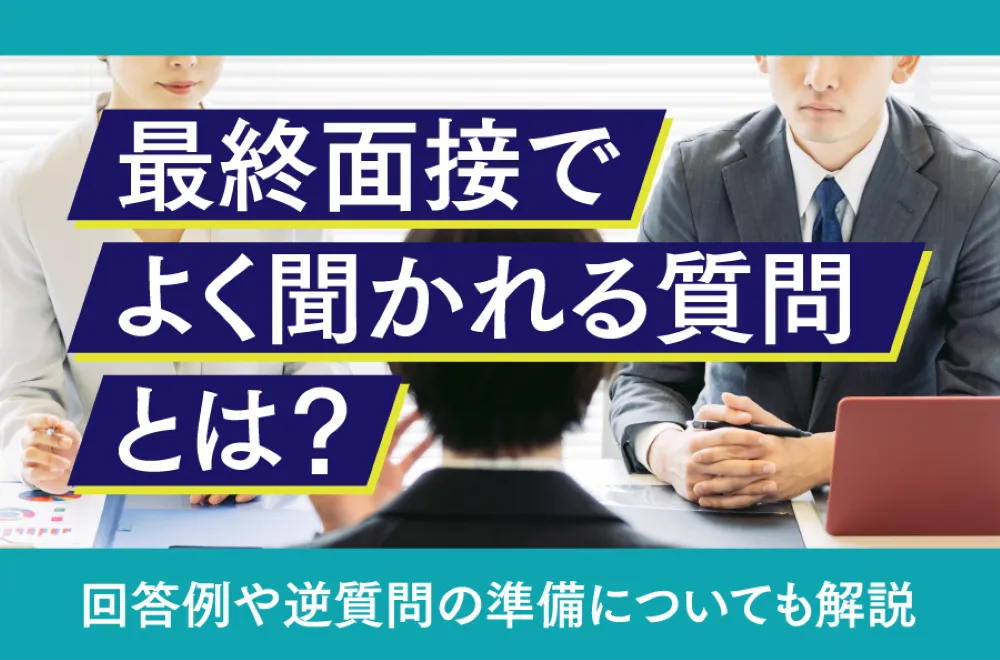
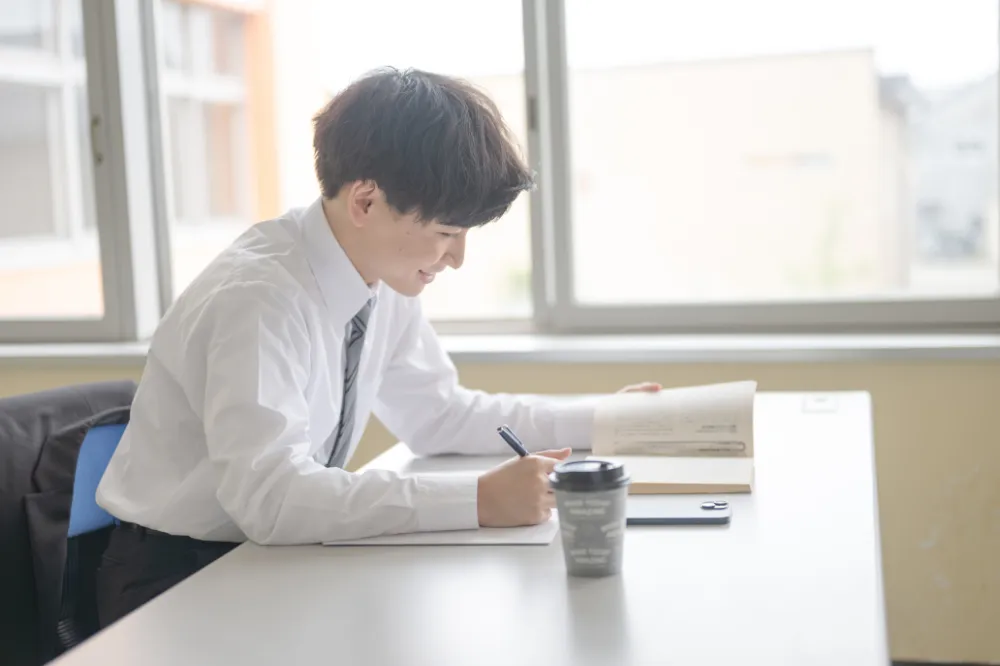
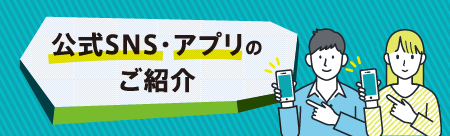
 LINE
LINE
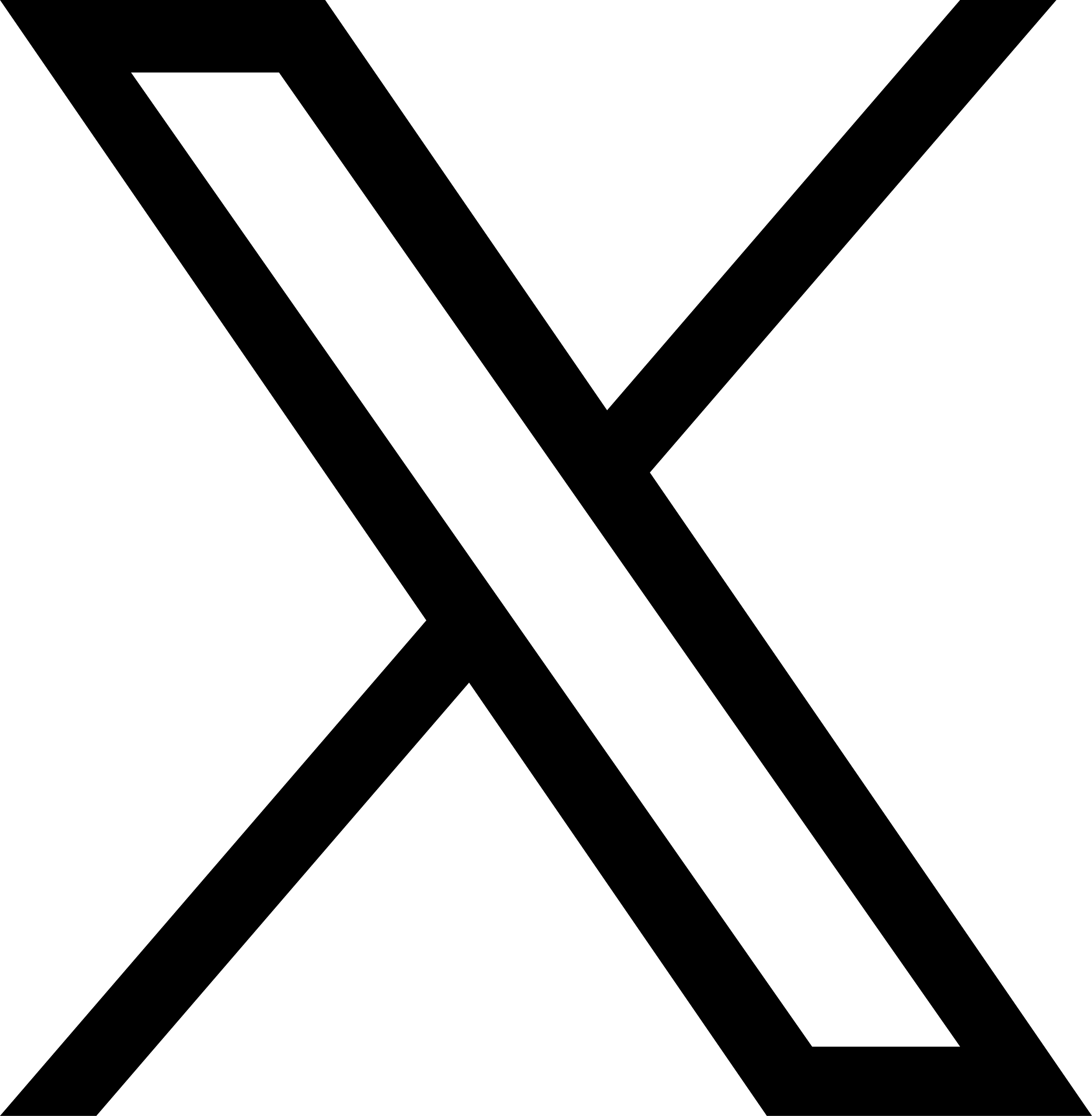 X
X
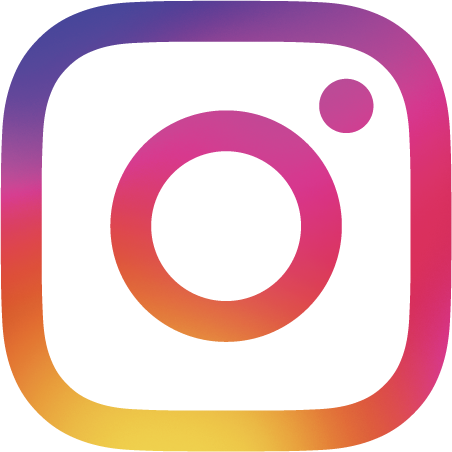 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube