グループディスカッションのテーマ一覧70選!就活で差がつく対策を解説
就活ノウハウ公開日:2025.10.08

この記事でわかること
- 企業は多くの就活生を効率的に評価するためにグループディスカッションを実施する
- グループディスカッションには「課題解決型」「資料分析型」などさまざまなテーマがある
- それぞれのテーマは評価ポイントや注意点が異なるため、事前の情報収集や対策が重要
グループディスカッションは、テーマが事前にわからないため自信がないと思う就活生も多いのではないでしょうか。しかし、しっかり対策して臨めば、自分の強みをアピールできる絶好の機会です。この記事では、基本的な流れからグループディスカッションのテーマ例、効率的な対策方法まで詳しく解説します。
そもそもグループディスカッションとは?
グループディスカッションとは、就活における代表的な選考方法の1つです。一般的には4~8人のグループで、約30~40分間にわたり与えられたテーマについて議論を行います。企業はグループディスカッションを通じて、学生さんのコミュニケーション能力や論理的思考力などを評価します。
発言の内容だけでなく、他者の意見を尊重する姿勢や議論をまとめる力も重要視されるため、事前の対策が重要です。
■企業がグループディスカッションを実施する目的
グループディスカッションは一次面接など初期の選考として実施されるケースが多いです。また、インターンシップ等の選考として実施されることもあります。
企業の目的は議論の過程を通じて多くの就活生を短時間で効率的に評価することです。グループディスカッションはコミュニケーション能力やチームワーク、問題解決力、論理的思考力といった、実際の業務でも重要なスキルを見極めるのに適しています。
企業は就活生の議論を通して能力や振る舞いを評価し、次の選考段階に進む候補者を絞り込んでいます。
■グループディスカッションの流れ
一般的なグループディスカッションの流れは以下のとおりです。

はじめに担当者から説明を受け、テーマ確認やグループ分けを行います。そのあと、グループごとに自己紹介や役割決めを行い、テーマに沿って意見を出し合いながら議論を進めます。最終的に、発表者がグループの結論を発表します。参加者には、協力して結論を導き出す姿勢が求められるため、段取りや役割の理解が重要です。
グループディスカッションの対策については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

グループディスカッション(GD)攻略のコツは?よく出るテーマや対策も解説
就活におけるグループディスカッションは、チームで働く上で必要な能力が試される選考方法の1つです。各役割を理解し、出題テーマや採用担当者が見ているポイントを押さえた事前対策をすることが重要です。本記事では、グループディス…
グループディスカッションのテーマ一覧!評価ポイント・注意点も
■「抽象的テーマ型(自由討論型)」のテーマ
■「課題解決型」のテーマ
■「資料分析型」のテーマ
■「ディベート型」のテーマ
■「フェルミ推定型、ケーススタディ型」のテーマ
■「選択型」のテーマ
■「企画立案型」のテーマ
グループディスカッションでは、どのようなテーマが出題されるのでしょうか。よくあるテーマの一覧を紹介し、評価されるポイントや注意点についても解説します。
■「抽象的テーマ型(自由討論型)」のテーマ
抽象的テーマ型では、具体的な答えのない抽象的なテーマについて議論します。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
・幸せとは何か?
・よい会社とはどんな会社か?
・よいリーダーの条件とは?
・社会人に求められる能力とは?
・働く理由は?
・10年後に新しく生まれる仕事は?
・100年後の日本の姿は?
・学生と社会人との差は何か?
・SNSで拡散されやすい投稿とは?
・AIで暮らしはどう変化するか?
この形式では「結論」もある程度重要ですが、メンバー同士でどう議論を展開し、論理的に考えを組み立てていったかという「過程」がより重視されます。
抽象的なテーマについて議論をはじめる際は、まず「〇〇とはこういうことだと考える」といった共通の定義づけをチームで行うことがポイントです。また、議論が脱線しやすいため、論点を整理しながら協力して意見をまとめる姿勢も求められます。
| 見られているポイント |
・議論の論点や意見を整理しながら、結論を導き出す力 ・役割遂行や発言などチーム内における貢献力 |
|---|---|
| 注意点 |
・自分の意見に固執せず、柔軟に対応する ・定義の認識を全員で一致させる |
| 企業例(※) |
・野村證券 ・NTTデータ |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
■「課題解決型」のテーマ
課題解決型では、提示された問題に対して話し合い、具体的な解決策を導き出します。特に、「なぜその問題が起きているのか」を分析し、原因を掘り下げた上で、実現可能かつ具体的な提案を行うことが求められます。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
・コンビニエンスストアの売上を2倍に伸ばすための策は?
・自社商品の認知度を向上させるためにはどうすればいいか?
・企業の残業時間を削減する効果的な対策は?
・環境問題を解決するために企業ができる具体的な取り組みは?
・少子高齢化による労働力不足を解消するには?
・外国人観光客の一人当たりの支出額を増やすアイデアは?
・若年層の車離れを食い止めるにはどのような施策が有効か?
・地方の過疎化に歯止めをかけるためにできることは?
・新商品の売上が伸びない問題に対しての改善策は?
・貧困に苦しむ国を支援するためにできる企業の取り組みとは?
この形式では斬新なアイデアよりも、実現性と具体性が重視される点がポイントです。原因を正確に把握し、筋道立てて論理的に提案する力に加え、説得力をもって結論を伝えることも評価につながります。テーマには時事問題が取り上げられることも多く、社会への関心も問われます。
| 見られているポイント |
・課題の原因を深く掘り下げていく力 ・原因に基づいた具体的な解決策の提案をする力 |
|---|---|
| 注意点 |
・解決策の根拠を明確に示す ・実現可能性を考慮したアイデアを出す |
| 企業例(※) |
・みずほフィナンシャルグループ ・日本アイ・ビー・エム |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
■「資料分析型」のテーマ
資料分析型では、与えられた資料を基にチームとしての提案をまとめるための議論を行います。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
・資料を読んで、とある地方都市に新規ショッピングセンターを開設すべきかどうか検討してください。
・過去5年間の売上推移を見た上で、新商品投入のタイミングを資料に基づき提案してください。
・消費者アンケートを分析して、当社の価格帯変更の妥当性を評価してください。
・大学の志願者データを基に、入学者数を増やす戦略を導き出してください。
・飲食チェーンの店舗別売上・稼働率データから、撤退すべき店舗を判断してください。
・施設利用者数推移を資料で確認し、施設活性化策を提案してください。
・労働時間・離職率の資料を分析して、社員満足度向上の施策を考えてください。
・競合他社との市場シェア比較資料を基に、自社の差別化戦略を検討してください。
・売上データから人気商品の傾向を読み取り、販売戦略を提案してください。
・架空のネットショップの広告データから、どの商品に広告費を多く使うべきかを考えてください。
まずは資料(データ、グラフ、記事など)を早く正確に読み取り、必要な情報を抽出しましょう。その上で、事実や数字、傾向など客観的な根拠に基づいて論理的な議論を展開します。推測に頼らず資料に基づく数字や傾向など事実を根拠にすることが重要です。
| 見られているポイント |
・資料を正確に読み取る力 ・客観的な情報を基に議論を進める力 |
|---|---|
| 注意点 |
・憶測で議論しない ・情報を整理して全体像を把握する |
| 企業例(※) |
・ロッテ ・関西電力 |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
■「ディベート型」のテーマ
ディベート型は、賛否が分かれるテーマについて2つのグループに分かれて討論する形式です。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
・消費税を廃止するすべきか否か
・日本は移民を受け入れるべきか否か
・救急車の無償化を撤廃すべきか否か
・SNSは現代社会において人々の幸福度を上げているか
・オンライン学習は対面学習より学習効果が得られるのか
・キャッシュレス決済は高齢者に対して利便性を向上させるか
・企業は社員の定時退社を徹底すべきか否か
・日本のコンビニエンスストアは24時間営業が必要か
・愛とお金どちらが大切か
・企業の副業解禁により社員は働きやすくなるか
このテーマでは、自分の立場を明確にし、根拠を示して論理的に主張する力が求められます。チームで意見を出し合いながら、最終的に全員が納得できる結論を導き出せるかが評価のポイントです。相手の反論を予想して対応策を準備しておくことで、議論を優位に進めやすくなります。
| 見られているポイント |
・相手の反論を予想しながら対応策を考える力 ・相手の意見を踏まえて反論や再主張をする力 |
|---|---|
| 注意点 |
・感情的に議論しない ・データや実例などの根拠を意識して話す |
| 企業例(※) |
・三井住友銀行 ・日本貨物鉄道 |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
■「フェルミ推定型、ケーススタディ型」のテーマ
フェルミ推定型では、限られた情報から仮定を立て、段階的に推測や計算を行い数値を導きます。
一方、ケーススタディ型では、実際のビジネス課題に対して背景や問題の本質を明確にしながら解決策を考えていきます。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
■フェルミ推定型のテーマ例
・日本にある電柱の本数は?
・大阪府内の全焼肉店の1日の売上は?
・東京都内を走っているバスの総数は?
・新宿駅内のトイレの1日の利用人数は?
・日本の全世帯が1年間に消費する電気代の合計金額は?
■ケーススタディ型のテーマ例
・売上が低下している店舗の改善方法
・客単価が低い店舗の改善施策
・顧客のリピート率が低い部門への改善施策
・ECサイトにおける商品トラブルの改善施策
・顧客満足度が低下しているホテルの改善施策
これらのテーマは論理的思考力が問われます。どちらも、メンバーとの意見交換を通じて多角的に問題を分析し、納得感のある提案を導くことが重要です。
| 見られているポイント |
・限られた情報や知識を基に状況に応じた意見を考える力 ・必要な情報を分解・整理する力 |
|---|---|
| 注意点 |
・チームで情報を出し合い協力する ・論理的に結論を導く |
| 企業例(※) |
・伊藤忠テクノソリューションズ ・三井住友カード |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
■「選択型」のテーマ
選択型のテーマでは、複数の選択肢から最適なものを選ぶための議論を行います。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
・「うどん」と「そば」世界に売り出すならどちらがよいか?
・地方創生のために重点的に取り組むべき施策は「観光振興」か「移住促進」か?
・子どもに今一番学ばせるべき習い事は「英語」か「水泳」か?
・「リモートワーク」と「出社勤務」どちらが生産性を高めるか?
・「家族」「恋人」「親友」「お金」の優先順位は?
・企業が大事にすべきは「利益」「社員」「社会貢献」のどれか?
・大学の授業は「WEB」か「対面」どちらがよいか?
・働く上でもっとも重要なのは「やりがい」「給料」のどちらか?
・「幸せな家庭」か「一生困らないお金」どちらが望ましいか?
・仕事の楽しさは「本人の努力」によって生まれるか、「職場の環境」で決まるか?
選択肢がある点はディベート型と共通していますが、必ずしも対立構造ではありません。最終的には多数決ではなく、全員が納得いく最適解が求められるため、合意形成や協調性が重視されます。各選択肢のメリット・デメリットを比較し、実現性や説得力を意識して結論を導くことが重要です。
その際、論理性だけでなくメンバーの多様な意見を丁寧に聞き取り、チーム全体で納得感のある答えを出す力も評価対象となります。
| 見られているポイント |
・自分の意見を明確に主張する力 ・状況に応じて妥協点を探る力 |
|---|---|
| 注意点 |
・相手の意見を尊重する ・自分の価値観を前提として押しつけない |
| 企業例(※) |
・野村総合研究所 ・大阪ガス |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
■「企画立案型」のテーマ
企画立案型のテーマでは、新たな企画やアイデアを生み出すための議論を行います。たとえば、以下のようなテーマが挙げられます。
・自社の強みを生かした新規事業を提案してください。
・自社が新商品を投入するなら、どのような商品がよいか提案してください。
・TV以外の広告手段を活用したプロモーション企画を立案してください。
・ショッピングモールの集客を増やす新施策を立案してください。
・SDGsに関連する自社の新しいサービスを立案してください。
・高校生や若年層向けに、健康意識を高める食品キャンペーンを企画してください。
・小売チェーンが導入するサブスクリプションサービスを提案してください。
・地方銀行が展開する地域振興型の新サービスを考案してください。
・若者が「つい選びたくなる」エコな飲料パッケージのコンセプトを考案してください。
・大学の図書館やカフェスペースを活用して、多くの週末に学生さんが集まるイベントを企画してください。
「誰のために、どの課題を解決するか」など、企画の目的を明確にすることが重要です。チームで意見を出し合い、現実的な視点と想像力をバランスよく活用して企画を練り上げましょう。発表時には、企画の背景・目的・内容・期待される効果を論理的に伝えることが評価のポイントです。
| 見られているポイント |
・提案内容を筋道立てて説明する力 ・新しいアイデアや独自性のある意見を出す力 |
|---|---|
| 注意点 |
・予算や期間など考慮し実現可能な提案をする ・出し合った意見を収束させ、結論に導く |
| 企業例(※) |
・アクセンチュア ・ダイキン工業 |
※企業ごとに出題されるテーマは毎年変わる可能性があります
『キャリタス就活』の「ES・選考対策を探す」では、就活生の体験談から、気になる企業のグループディスカッションで実際に出題されたテーマを確認できるケースがあります。選考に通過した先輩が実際に行った議論の進め方やアドバイスなど、詳細に記載されているので、効率的に対策するためにぜひご活用ください。
グループディスカッションの事前対策

■クチコミで情報収集して企業ごとのテーマの傾向を把握する
■企業研究を徹底する
■インターンシップに参加する
■企業が求める人物像を把握しておく
■ニュースをチェックする習慣をつける
■日ごろから自分の意見をもつ
■自分が貢献できる役割を見極める
グループディスカッションをどのように対策すべきか悩むケースも多いでしょう。選考を突破するための効果的なグループディスカッション対策について紹介します。
■クチコミで情報収集して企業ごとのテーマの傾向を把握する
グループディスカッションの対策として、先輩たちのクチコミの活用は非常に有効です。就職情報サイトやSNSを活用して、同じ企業の選考を受けた先輩たちの経験談をチェックしましょう。議論の形式やテーマの傾向を把握できれば、事前に効率的な対策ができます。
『キャリタス就活』の「ES・選考対策を探す」では、グループディスカッションで出題されたテーマや進行の様子を、体験談を通して参考にできます。事前に情報収集して万全の準備をしましょう。
■企業研究を徹底する
グループディスカッションの対策としては、企業研究を徹底することが欠かせません。実際に出題されるテーマの中には「自社の存在意義」「今後の市場展望」「なぜクライアントから選ばれるのか」といった、その企業を理解していなければ答えにくいものも少なくありません。
事業内容や強みを深く理解しておくことで、議論の方向性を現実的かつ具体的に示すことができ、説得力のある発言につながります。単なるイメージではなく、企業の特徴を踏まえた意見を出せるかどうかが評価の分かれ目になります。しっかり企業研究を行うようにしましょう。

【テンプレートつき】業界・企業・職種研究をやってみよう! 企業研究編
就活を始めてみたが「企業研究は必要?」「やり方がわからない」という方も多いでしょう。この記事では、企業研究の基本的な進め方からノートのまとめ方などを新卒向けに解説します!具体的に調べることや他社比較の方法、情報をまとめ…
■インターンシップに参加する
企業研究やグループディスカッションの練習としてインターンシップへの参加は非常に有効です。実際に仕事を体験できるだけではなく、選考やプログラムの中でグループディスカッションに挑戦する機会も多くあります。
役割分担や議論の進行を実際に体験することで、集団の中で意見を述べたり緊張感のある場に対応したりする力が養われ、本選考でも本来のパフォーマンスを発揮しやすくなります。グループディスカッションに苦手意識がある方こそ、インターンシップへの参加がおすすめです。
『キャリタス就活』の「インターンシップ・キャリアを探す」では条件を絞って自分に合った企業を見つけられるので、ぜひ活用してみましょう。
■企業が求める人物像を把握しておく
出題傾向だけでなく、企業が求める人物像を把握しておくことは、グループディスカッション対策として効果的です。単に発言量やアイデア力で評価されるわけではなく、企業が求める人物像に合致するかどうかも見られているためです。たとえば、主体性を重視する企業であれば積極的に意見を出す、チームワーク力を重視する企業であれば相手の意見を取り入れる姿勢を見せるのが効果的です。
事前に志望する企業が求める人物像を理解しておけば、自分の立ち回りを戦略的に考えられます。
■ニュースをチェックする習慣をつける
グループディスカッションでは、時事問題がテーマとして出題されることも多いため、日ごろからニュースをチェックする習慣をつけておくことが重要です。特に、社会的な課題や経済、国際情勢、最新トレンドに関する話題はおさえておきましょう。
さらに、志望する業界や職種に関するニュースも確認しておくことで、専門性のある意見を述べやすくなります。ニュースで得た知識は議論の際に説得力を高める材料となるため、日常的な情報収集を心がけることが大切です。
「日経の注目ニュース&リサーチ」では、業界研究に必須の業界別最新ニュースや業界解説動画を閲覧できます。「5分でわかる業界」では、最前線で取材する日経の記者が業界のいまを動画で解説します。そのほか、日本経済新聞電子版に掲載されたニュースのダイジェストも読めるので、最新ニュースを効率的にチェックすることができます。ぜひご活用ください。
※ニュースや動画を閲覧するには、会員登録(無料)またはログインが必要です。
■日ごろから自分の意見をもつ
グループディスカッションでは、自分の意見をもって適切に伝える姿勢が重要です。そのためには、日ごろからニュースや社会問題に触れた上で、自分なりの意見を形成する習慣をつけましょう。
意見が思いつかないからと発言を控えると、ほかの参加者や担当者から消極的な印象をもたれる可能性があります。自分の考えを言語化する練習を積み重ねることで、発言に自信がもてるようになります。
■自分が貢献できる役割を見極める
グループディスカッションでは、議論をスムーズに進め質の高いアウトプットを目指すために、参加者で役割を決めることが推奨されています。その際に重要なのが、自分がもっとも貢献できる役割を見極めることです。たとえば、リーダーシップを発揮したいなら司会役、プレゼンテーションに自信があるなら発表者など、自分の強みに応じた選択が効果的です。
人数の関係で役割がない場合でも、ほかのメンバーのサポートや積極的な意見出しを通じて十分に貢献できます。
役割ごとの特徴や具体的な立ち回り方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

キャリアアドバイザーからの一言
グループディスカッションの対策では、知識を得るだけでなく「実際に話す練習」が非常に効果的です。たとえば、友人と模擬練習をしたり、自分の議論の様子を録画して振り返ったりしてみましょう。大学のキャリアセンターや就活イベントでグループディスカッション体験を行っていることも多いので、機会があれば積極的に参加することがおすすめです。特に、他大学の学生さんと実践できるイベントでは本番に近い環境で体験できるので有効です。
また、AIと対話形式で練習することで、実践を通して自分の話し方や立ち回りの改善点に気づけるでしょう。
下記記事ではグループディスカッションの事前対策についてより詳しく解説しています。評価されるためのコツやNG行為まで網羅的に説明しているので、グループディスカッションを完全対策するためにぜひご覧ください。

グループディスカッション(GD)攻略のコツは?よく出るテーマや対策も解説
就活におけるグループディスカッションは、チームで働く上で必要な能力が試される選考方法の1つです。各役割を理解し、出題テーマや採用担当者が見ているポイントを押さえた事前対策をすることが重要です。本記事では、グループディス…
グループディスカッションの当日に意識すべきこと
しっかり事前対策をしていても、グループディスカッションの当日は緊張してしまうものです。そこでグループディスカッションの当日に意識するとよい3つのポイントについて解説します。
■フレームワークを意識し、簡潔に話す
フレームワークとは、物事を整理・分析・判断するための思考の枠組みや構造のことです。主に、議論を論理的に進めるために使われます。フレームワークを意識すると、議論の方向性が明確になり、効率的な意見の交換が可能です。
たとえば、「結論→理由→具体例→結論」(PREP法)の流れを意識することで、自分の考えを論理的に示すことができます。それぞれの場面に応じてフレームワークを使い分けましょう。
フレームワークの例
・PREP法(結論→理由→具体例→結論):意見を論理的に伝えられる
・3C分析(顧客・競合・自社の観点から分析):取り組むべき課題が見えてくる
・4P分析(製品・価格・流通・販促の視点から分析):サービスや製品の強み・弱みを洗い出せる
・SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威の要素を組み合わせて分析):効果的な事業戦略の立案ができる
など
■明るくハキハキと話す
グループディスカッションで明るくハキハキと話すことで、面接官に積極性を印象づけられます。また、声のトーンや表情が明るいと、ほかの参加者に安心感も与えられ、意見交換がスムーズに進みやすくなります。発言の内容だけでなく、伝える姿も評価の対象になるため、相手が聞き取りやすい話し方を意識しましょう。
■積極性と傾聴のバランスをとる
グループディスカッションでは、積極的に役割を担ったり発言する姿勢が評価されますが、それと同時に他者の意見を傾聴する姿勢も重要視されます。相手の考えを理解した上で、自分の意見を述べることで、協調性と積極性の両方を示しましょう。積極性と傾聴のバランスを意識することで、議論がスムーズに進みやすくなり、面接官に好印象を与えられます。
グループディスカッションのテーマに関するよくある質問
グループディスカッションで詳しくないテーマが出されたときの対策法は?
グループディスカッションで詳しくないテーマが出されたときは、議論の最初に全員の事前知識を確認しましょう。
「このテーマについてどれくらい知っているか」「どんな視点があるか」をグループ内で共有します。知識の有無だけで合否が決まる場合はほとんどないので、知ったかぶりで無理に話すことは控えましょう。
知識が不足していても、わかる範囲の情報で論理的に整理すること、投げ出さずに冷静に結論まで導くことが重要です。
グループディスカッションは1人でも練習できる?
グループディスカッションは1人でも練習可能です。
身近なテーマで「こんな議題が出たら自分はどう答えるか」を考えたり、模擬的に意見を声に出してみたりするだけでも思考力や表現力が鍛えられます。また、AIと対話形式で練習するのもおすすめです。日常的な訓練として取り入れることで本番でも自信をもって発言できるようになります。
就活のグループディスカッションのおもしろいテーマは?
グループディスカッションのおもしろいテーマの例として、「タイムマシンがあったら未来と過去どちらに行くべきか?」、「無人島にもっていくならナイフかライターか?」などが挙げられます。
こうしたテーマはユニークで話し合いが盛り上がりやすく、参加者の個性やアイデアが自然に表れます。企業は議論を通じて、その人らしさや柔軟な考え方を見極めようとしています。
就活のグループディスカッションのテーマはいつ知らされる?
グループディスカッションのテーマは、基本的に当日、ディスカッション開始直前に提示されます。
事前にテーマを調べる時間はないため、日ごろから時事問題や業界知識など幅広い分野にアンテナを張っておくことが重要です。準備の積み重ねがテーマへの理解力や柔軟な対応力につながります。
グループディスカッションは効果的な対策をすれば怖くない!
グループディスカッションは効率的な対策を行えば、自分の強みをアピールできる貴重な場になります。そのためには、日ごろからニュースや企業情報を収集したり、自分の意見をもつ習慣をつける姿勢が大切です。また、自分が貢献できる役割を見極め、テーマに沿った模擬練習を繰り返すことも有効です。この記事で紹介したテーマ例や対策法を活用してしっかり準備を進めましょう。
『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。
PROFILE
キャリタス就活編集部
『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。
「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。




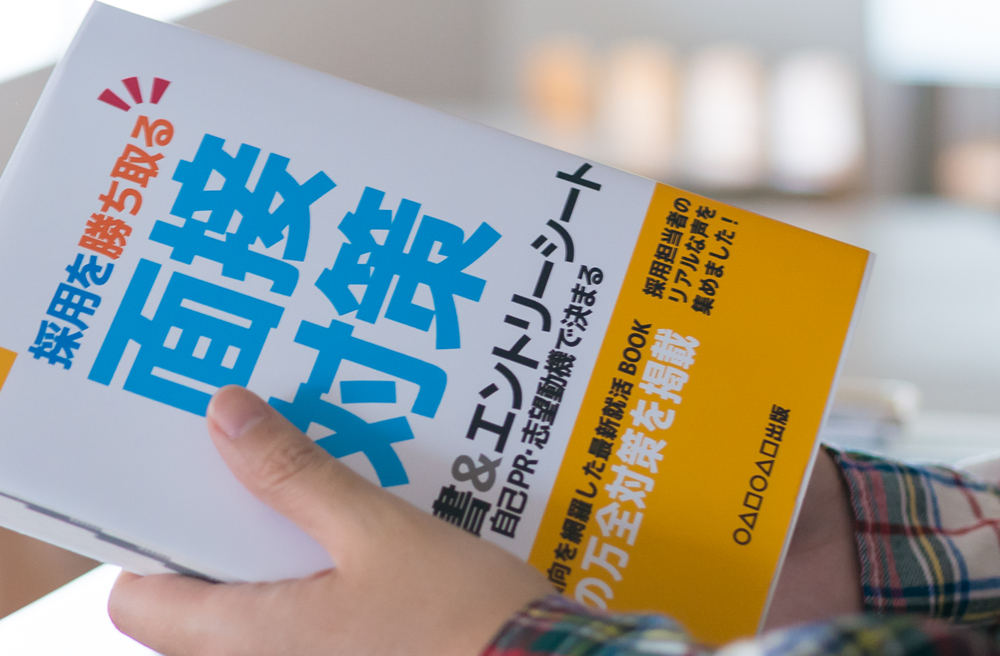











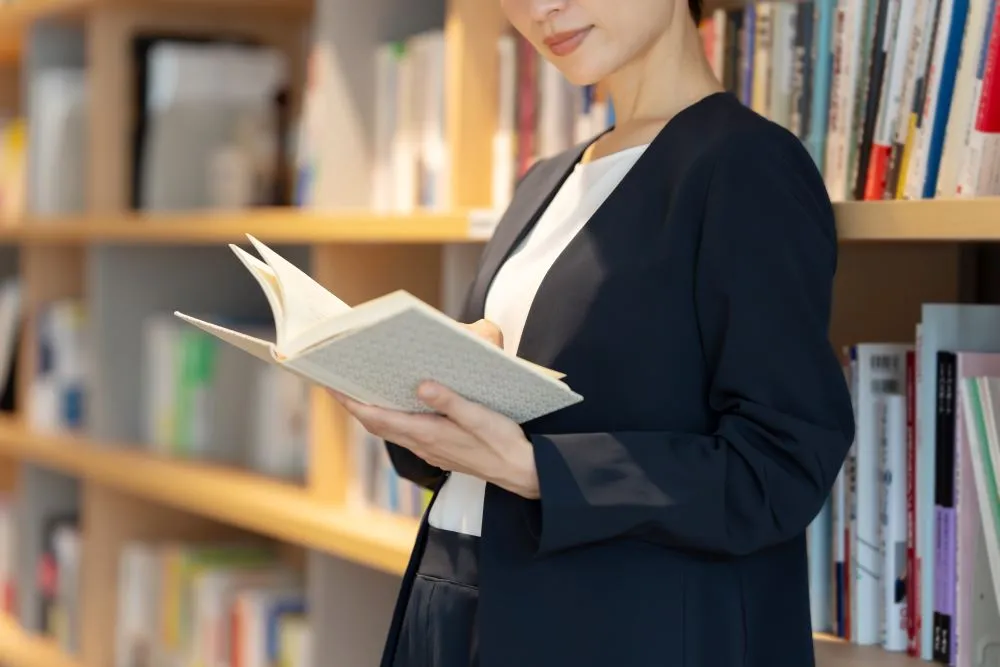
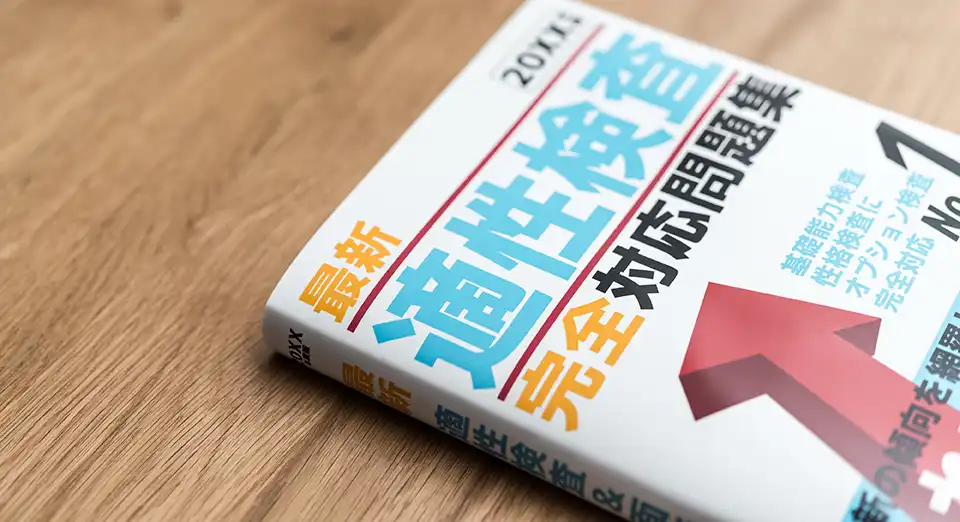


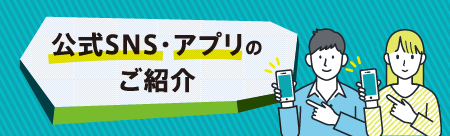
 LINE
LINE
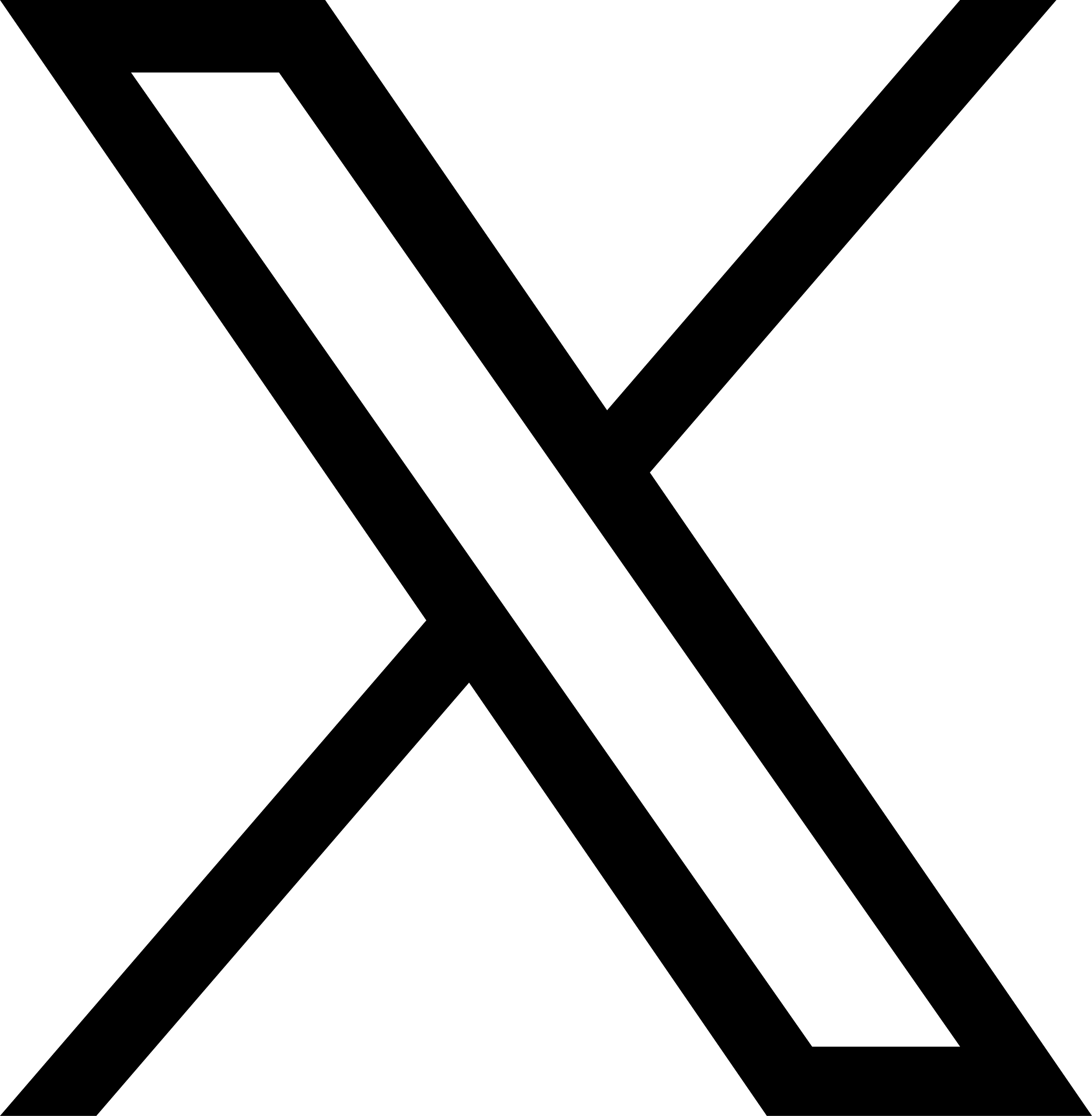 X
X
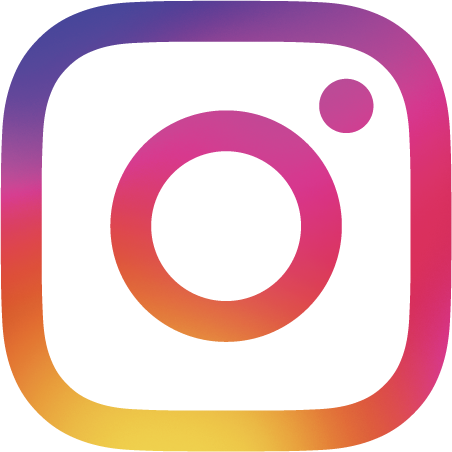 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube