就活セクハラとは?実態と加害者への法的措置について【弁護士が答えます】
就活ノウハウ公開日:2025.04.02

皆さんは「就活セクハラ」という言葉を聞いたことはありますか。これは就職活動の場で受ける性的なハラスメントを指し、実際に受けてしまうと自分だけでは対処が難しいのが実態です。本記事では、弁護士の視点から、加害者への法的措置、企業への対処方法、そして未然に防ぐための予防策についてわかりやすく解説します。万が一のときに備え、正しい知識を身につけ、安心して就職活動に取り組みましょう。
就活セクハラとは?
就活セクハラとは、インターンシップ等や就職活動中に受けるセクシャルハラスメントの略称です。
具体的には、選考への影響や内定等をほのめかし性交渉を強要したり、性的な発言や行動を繰り返すことを指します。
就活セクハラの例
就活セクハラは大きくわけて「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2つに分類されます。それぞれにおける特徴と例を紹介します。
■対価型セクハラとは
対価型セクハラとは、性的な要求に応じるかどうかで採用や評価に影響させるハラスメントを指します。
〇対価型セクハラの例
・採用担当者が内定をちらつかせ、不適切な関係を強要する。
・面接にて「この質問に答えたら評価を上げる」といい、就活とは関係のないプライベートな質問をする。
■環境型セクハラとは
環境型セクハラとは、性的な発言や行動によってインターンシップ等や就職活動の環境が不快なものになり、能力の発揮に悪影響が生じるハラスメントを指します。
〇環境型セクハラの例
・交際関係についてしつこく聞いてくる。
・懇親会やインターンシップ中に身体的接触や不快にさせる発言をする。
就活セクハラの実態
セクハラは加害者と被害者に力関係の差があるほど起こりやすく、就活においては採用者という立場を悪用して残念ながらこのようなトラブルが発生してしまっているのが現状です。
厚生労働省が2023年に男女1,000名に実施した
「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると就活中に一回以上ハラスメントを受けたと回答した人の割合はなんと30%以上に上ることがわかりました。
インターンシップやOBOG訪問など就活中に従業員から性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘いを受けたという内容が多い結果になりました。
これら就活セクハラは悪質な場合には性犯罪として刑事罰を受けるケースもあり、世間の認知度は徐々に高まっているように思います。
この状況を受け、厚労省は、就職活動の際のセクハラを防止するため、就活面談のルール策定や相談窓口の設定を企業に義務付ける方針を固めたようです。
就活時のセクハラ防止のためのルールが策定され、予防措置が講じられるならば、これは喜ばしいことです。ただ、具体的なルールが策定されるまでにはまだ時間がかかります。
現時点での法制度を前提に、就活セクハラに関してどのような措置を講じることができるのかを解説いたします。
この状況を受け、厚労省は、就職活動の際のセクハラを防止するため、就活面談のルール策定や相談窓口の設定を企業に義務付ける方針を固めたようです。
就活時のセクハラ防止のためのルールが策定され、予防措置が講じられるならば、これは喜ばしいことです。ただ、具体的なルールが策定されるまでにはまだ時間がかかります。
現時点での法制度を前提に、就活セクハラに関してどのような措置を講じることができるのかを解説いたします。
セクハラ加害者への法的措置
まず問題となるのは、セクハラ加害者に対する法的措置です。自らセクハラをした当事者なのですから、加害者が法的責任を負うことは当然です。問題は、どのような法的責任を問えるかです。
①民事上の責任
セクハラは、被害者の性的自由を侵害する行為です。このような権利侵害に関しては、「不法行為」(民法709条に定められています)を理由とする責任追及ができます。
ここでいう責任追及とは、損害賠償、つまり、あくまでも金銭的な賠償に限られます。セクハラを受けて精神的苦痛を被れば、適切な慰謝料を請求することができます。また、心療内科等に通院した場合には、治療費等の実費を請求することもできます。
②刑事上の責任
民事上の責任とは別途、刑事上の責任を追及することも考えられます。
セクハラの内容にもよりますが、加害者は、不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交罪(刑法177条)といった罪により、しかるべき刑事罰を受ける可能性があります。
③社内での責任
民事・刑事上の責任のほか、セクハラ加害者には、社内での懲戒処分による制裁も考えられます。
採用担当者が就活生にセクハラをした場合、会社にとっては、自社の信用が揺らぐ由々しき事態です。加害行為の悪質性などを考慮し、けん責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇(右に行くほど重い処分です)を科すことになるでしょう。
■会社に対する法的措置
セクハラ加害者は当然のこと、加害者を雇用する会社も無傷ではいられません。
採用担当が就活生と接することは、会社の業務の一環です。会社の業務を執行する過程で従業員が不法行為をした場合、会社は、使用者としての責任を負います(これは、民法715条に定められた「使用者責任」です)。
セクハラ被害を受けた人は、加害者が勤務する会社に対しても損害賠償請求をし得ることになります。
抜本的な予防措置への期待
セクハラ被害に関する法的措置は前記した①民事上の責任、②刑事上の責任のとおりですが、お読みいただくとわかるとおり、これらの措置は、「被害を受けてしまった後の回復措置」です。言うまでもなく、被害を受けた後に損害の回復を考えるよりも、被害自体が予防されることがベストです。
就活セクハラの被害予防措置については、これまで十分なルールが策定されていませんでした。そうであるからこそ、厚労省が就活面談のルール策定や相談窓口の設置義務化など具体的なルール策定に向けて歩を進めたわけです。
皆さんは就職活動の真っ只中だと思いますが、就活の中で「あれ?おかしいな?」と思うことがあれば、会社のハラスメント窓口や大学のキャリアセンターに相談をしてみるのもひとつの手です。
もっと気軽に相談したい方は「キャリタス就活
あんしん相談」がおすすめです。就活に関する悩みや相談に対してプロの就活アドバイザーや弁護士が回答します。キャリタス就活はあなたの就活を全力でサポートします。
ぜひこの機会にお気軽にご利用ください。
※「キャリタス就活 あんしん相談」のご利用にはキャリタス就活の会員登録が必要です。会員登録はこちら
PROFILE
定禅寺通り法律事務所
下大澤 優弁護士
退職代行、残業代請求、不当解雇、パワハラ・セクハラなど、数多くの労働問題を取り扱っています。これまでにも、発令された配転( 転勤) 命令の撤回、未払残業代の支払など多くの事例を解決しています。










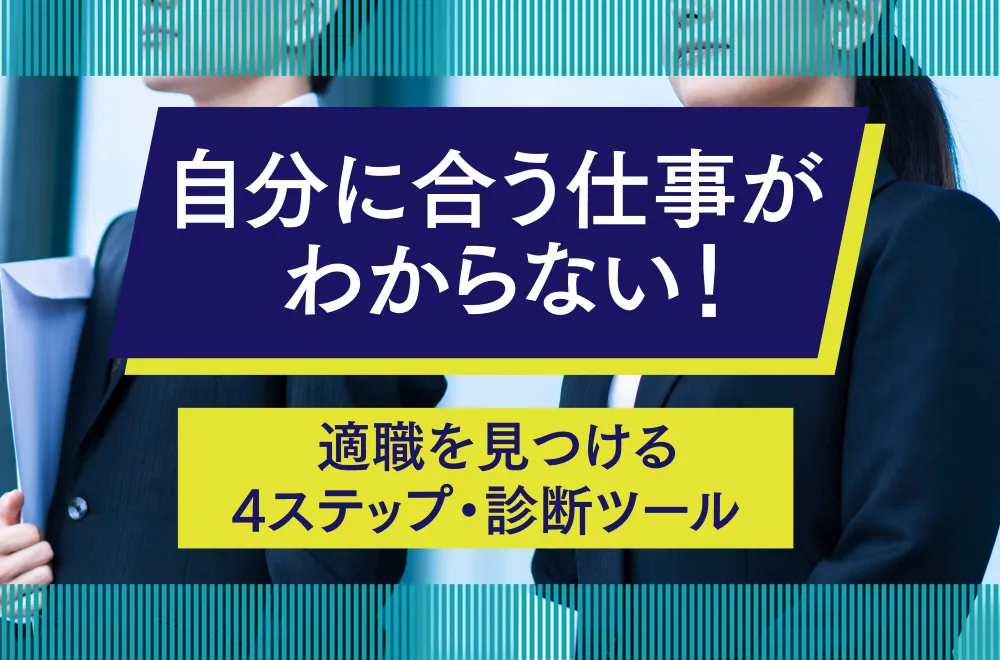

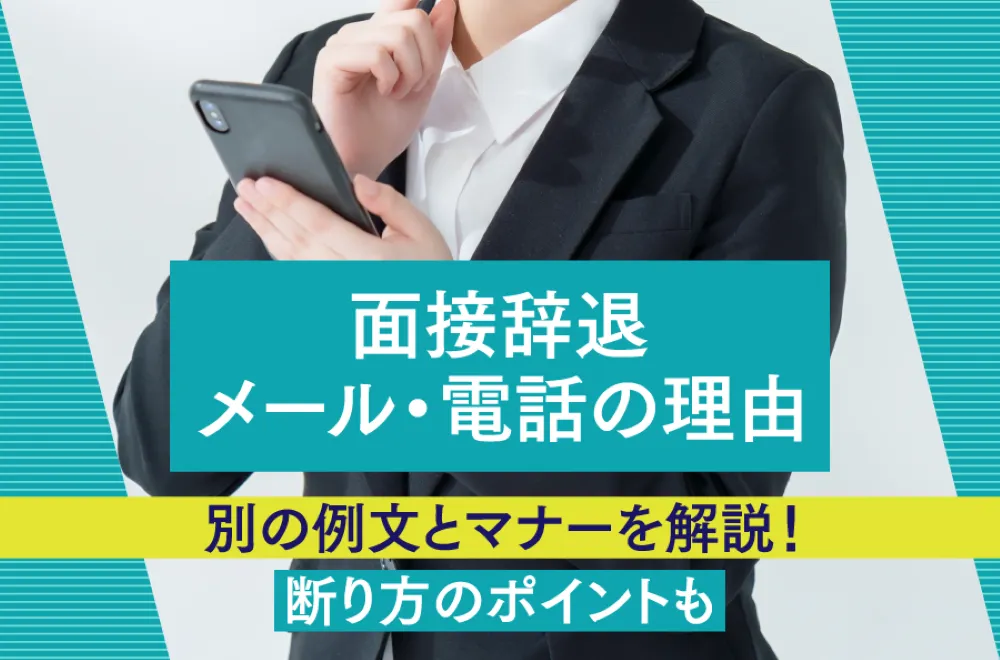





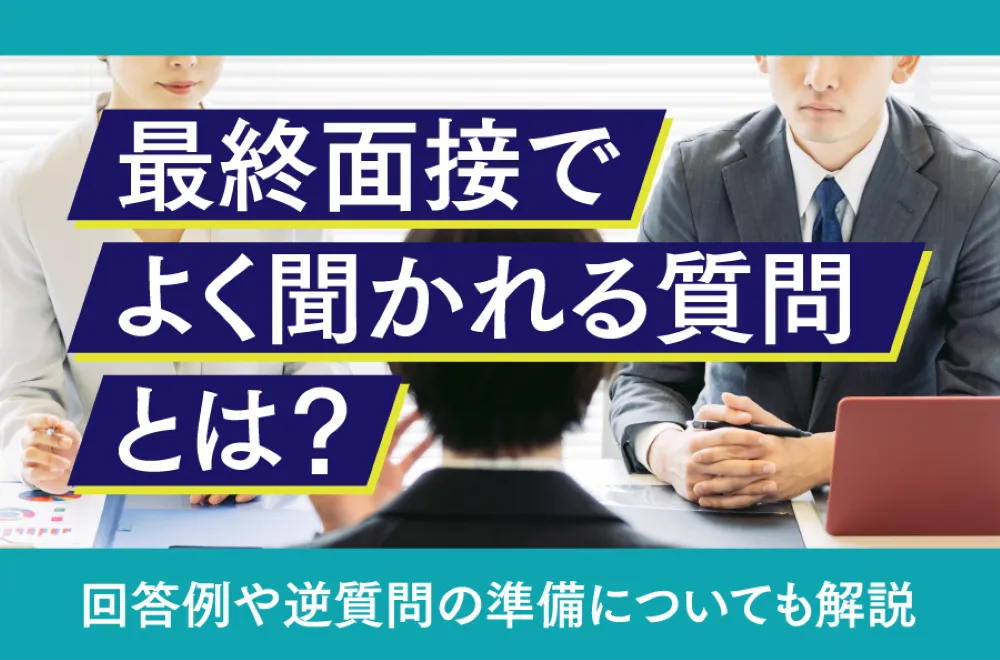
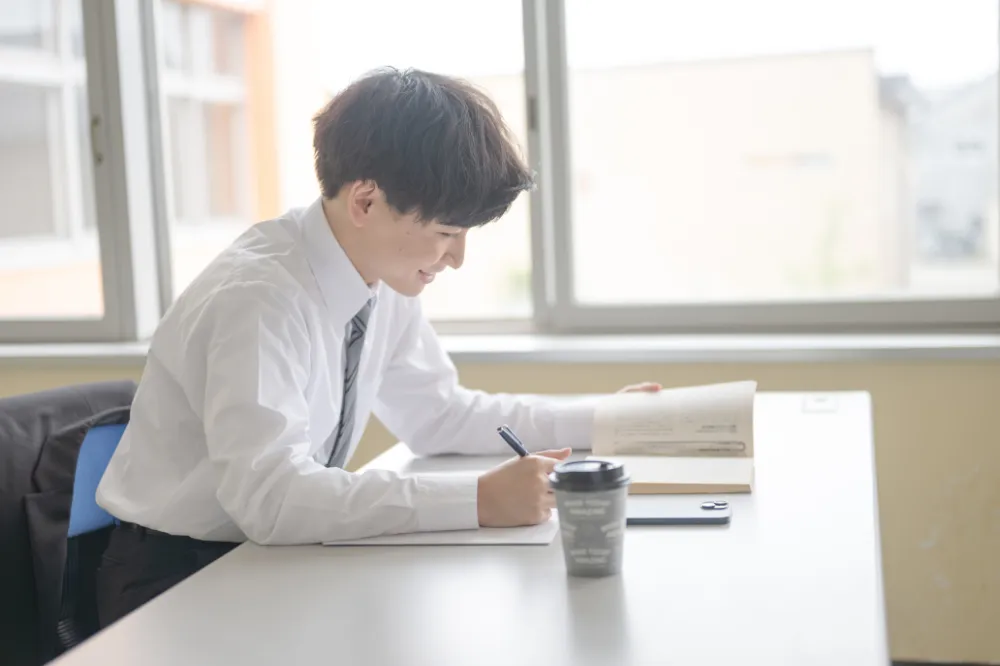
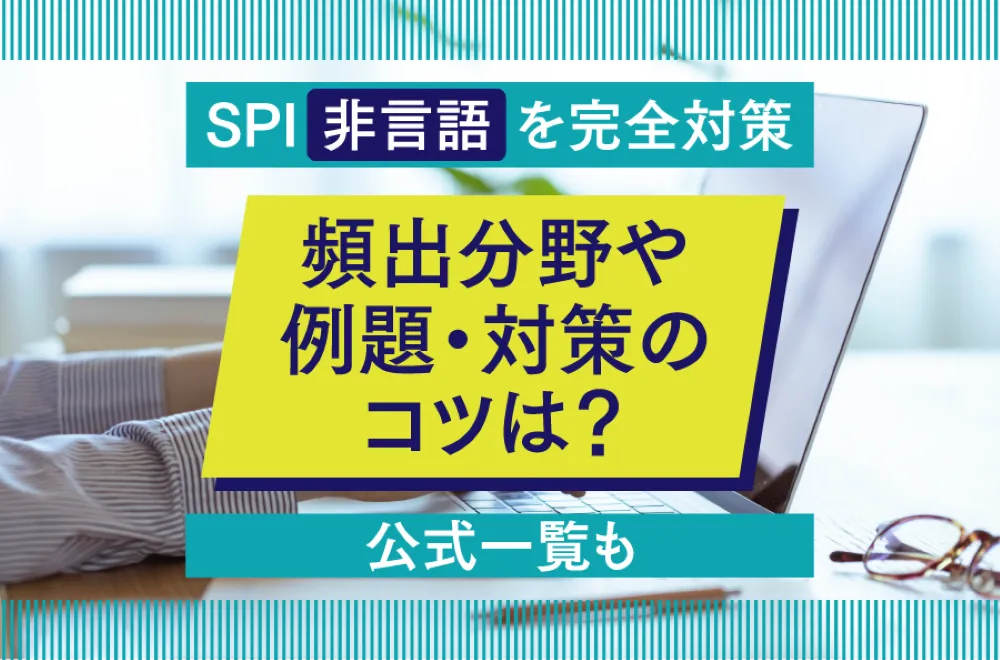
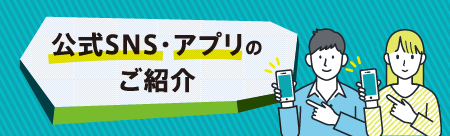
 LINE
LINE
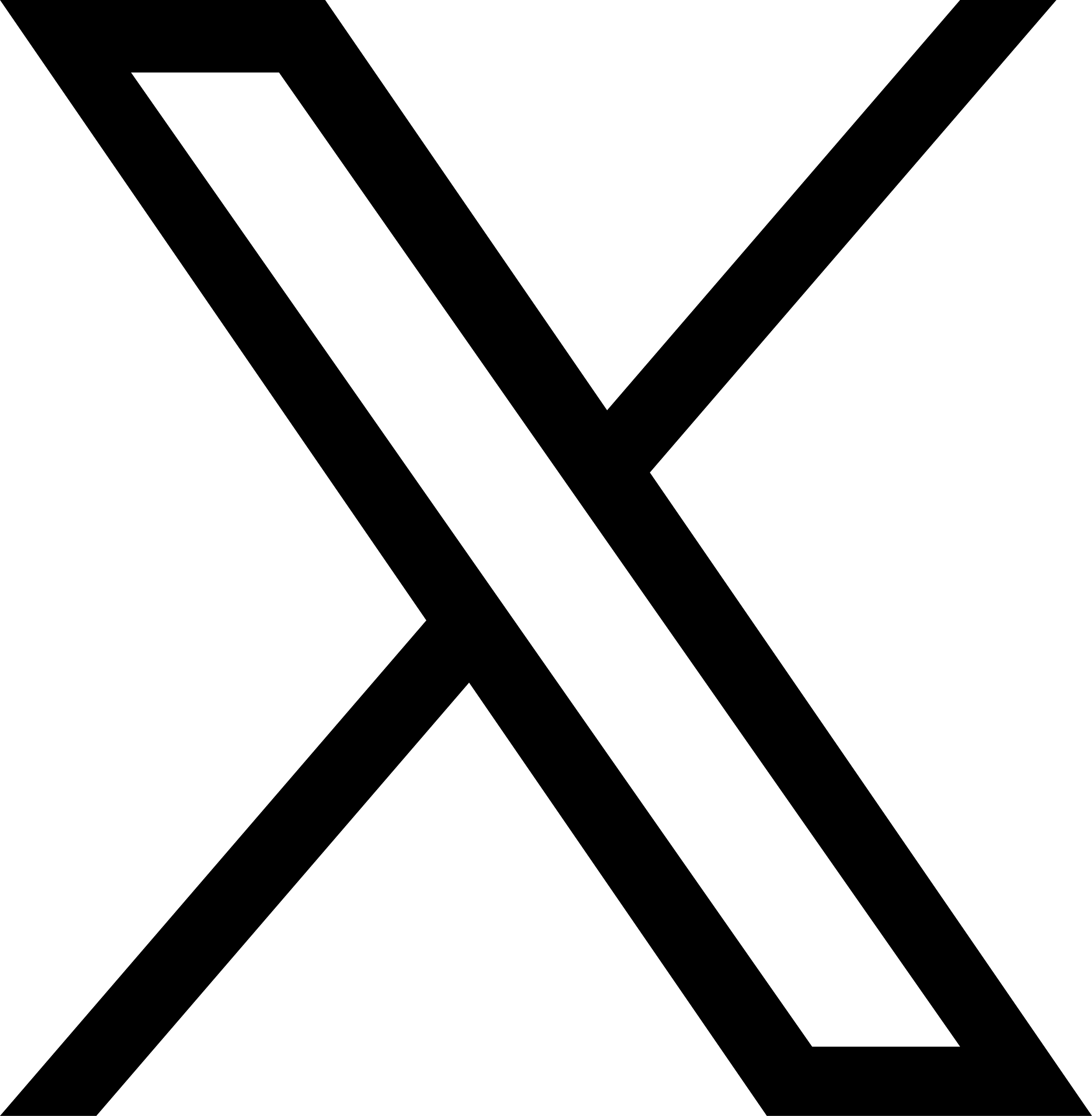 X
X
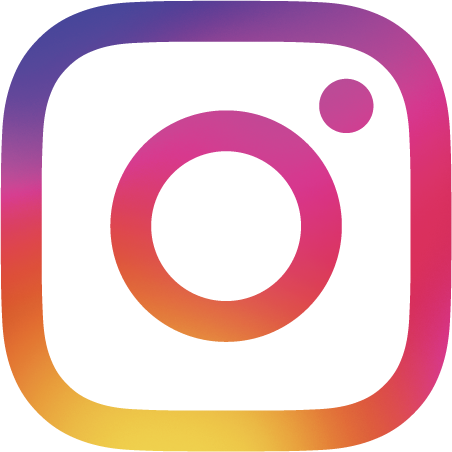 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube