新卒のボーナスはいつから?いくらもらえる?学歴や業界別の平均額を解説
就活ノウハウ公開日:2025.11.26

この記事でわかること
- 新卒では冬のボーナスから支給されるケースが多い
- 新卒のボーナスは学歴や企業規模によって差が見られる
- ボーナスは景気や社会変化の影響を受けることもあるため、景気動向を確認しておこう
これから社会人になる皆さんにとって、ボーナスはいつからもらえるのか、平均はいくらくらいなのかはとても気になる話題かと思います。この記事では、新卒1年目のボーナスの目安や学歴・企業規模・業界別によるボーナスの支給額の違いまで詳しく解説します。ボーナス手取り額のシミュレーションや、新卒入社後にボーナスをアップさせる方法も紹介します。
新卒はボーナスをもらえない?いつから?
ボーナスとは、企業が従業員の業績や企業の業績に応じて支給する一時金のことです。一般的には夏と冬の年2回支給されますが、評価期間や計算方法を含め企業によって形式は異なります。特に、現在就活をしている方にとって気になるのは、新卒でもボーナスが支給されるのか、またいくらくらいなのかという点でしょう。ここではボーナス事情について詳しく見ていきましょう。
■夏のボーナスは寸志程度が相場
一般的に4月入社の新卒社員が初めて受け取る夏のボーナスは、感謝の気持ちとして支給される少額の一時金、「寸志」に留まることが多いです。新卒1年目の社員は、入社してから支給までの期間が短く、査定期間が十分に確保できないからです。
5~10万円程度と具体的に金額を規定している企業もありますが、支給自体がない企業もあります。
■冬のボーナスは基本給の1~2カ月分が相場
通常、新卒1年目の社員も冬のボーナスからほかの社員と同じように支給されはじめます。入社後の実績や貢献度が査定に反映されますが、多くの企業では基本給(固定残業代などは含まない)の1~2カ月分、金額にして20~50万円程度が相場です。ただし、企業によっては、業績や個人の成果に応じて支給額が変動する場合もあります。
なぜ夏と冬でボーナスに違いがあるのか?
夏と冬のボーナスに差が出る主な理由は、査定期間の違いにあります。
ボーナスの査定期間は企業によって異なりますが、一般的に夏のボーナスは前年度の10月から3月までの業績を基準に支給されるため、新卒の社員は査定期間に在籍していないため支給対象外になる傾向にあります。
一方、冬のボーナスはその年の4月から9月までの企業の業績や社員の勤務実績が評価される傾向があるため、査定期間全体が対象となり夏より高額になるケースが多いです。
新卒就活で理解しておきたいボーナスについての基礎知識

これから就活する皆さんにとって、新卒1年目のボーナスの有無や金額は初任給とあわせて気になるポイントでしょう。社会人になる前に知っておきたい基礎知識をまとめました。
■ボーナスがあるかどうかは企業の規定による
そもそもボーナスの支給は企業の裁量に委ねられており、法律で義務づけられているものではありません。一般的には企業の経営状況や慣例に基づいて支給額が決まり、新卒1年目は支給されない、あるいはボーナス支給自体がない企業もあります。
また、ボーナス支給がある場合も毎年必ずもらえるとは限りません。業績不振の場合には、支給額が減ることもあります。これまで毎年支給されていたのに、突然支給がなくなるということもあるでしょう。
業界による違いもあり、景気や社会変化の影響を受けやすい業界へ就職を考えている場合、日ごろから景気動向を確認しておくことが重要です。
■ボーナスには査定期間がある
ボーナスは、一定の査定期間に基づいて支給されます。査定期間とは、社員の業績や勤務態度を評価する期間のことです。企業によって異なりますが、一般的には半年から1年程度とされています。
査定期間中の働き方がボーナスに直結するため、日々の業務で目標達成やスキルアップを意識しましょう。また、上司や同僚との良好な人間関係を築くことも、評価を高めるポイントです。
■ボーナスから税金を納める必要がある
ボーナスも給与と同様に、支給額から所得税や社会保険料などが差し引かれます。社会保険料とは、具体的にいうと健康保険料、厚生年金保険料などのことです。控除額は個人の所得によって変わるため、最終的な手取りがいくらになるかは各自で確認する必要があります。
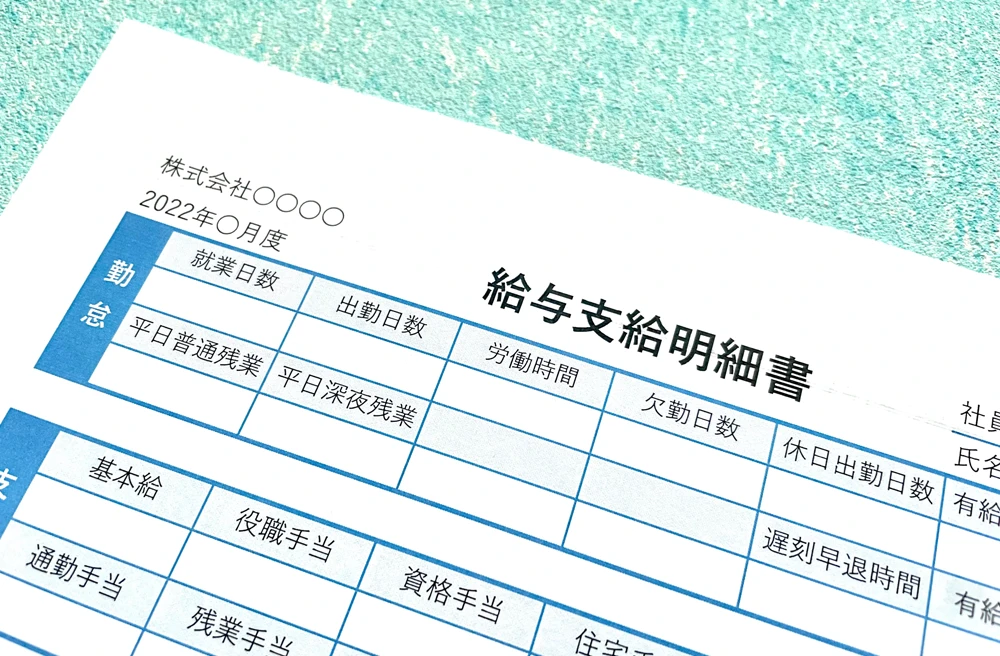
「給与」と「給料」の違いを説明できますか?意外と知らない給与の仕組み
就職活動を始める学生の皆さんにとって、「給与」はひとつの大きな関心事ですよね。初めての給与というものは、自分の労働の価値を金銭的に反映したものであり、新たなキャリアの始まりを象徴しています。本記事では、「意外と間違えや…
ボーナスの手取り額の計算方法
ボーナスの手取り額に影響する要素
・社会保険料:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険(40歳以上)
・所得税
一般的に、ボーナスの手取り額は支給額の70~80%程度になることが多く、新卒の場合は80%前後がほとんどです。手取りを計算する際には、社会保険料や所得税などいくつかの要素を考慮する必要があります。
社会保険料には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険(40歳以上)が含まれます。それぞれ法律で定められた割合で計算され、足し合わせた額を支給額から差し引いて手取り額を算出します。
所得税は、ボーナスの支給額に応じて異なる税率が適用されます。
■ボーナスの手取り額のシミュレーション
| ボーナス支給額 | 手取り額 |
|---|---|
| 10万円 | 8万円 |
| 20万円 | 16万円 |
| 30万円 | 24万円 |
| 40万円 | 32万円 |
| 50万円 | 40万円 |
| 60万円 | 48万円 |
| 70万円 | 56万円 |
| 80万円 | 64万円 |
| 90万円 | 72万円 |
| 100万円 | 80万円 |
上記は、ボーナスの手取り額を支給額の80%として計算した場合の金額をまとめた表です。ボーナスの支給額から、どのくらいの金額が手元に残るのかイメージしてみましょう。
【学歴別】新卒のボーナス事情
新卒のボーナスは、学歴によって支給額に差が出ることがあります。ここでは、令和6年時点の新卒の年間ボーナスの平均額を学歴別にまとめました。学歴による違いをみていきましょう。
■高卒の場合
高卒の新卒(~19歳)の年間ボーナス平均額は189,900円(※)です。一部の企業では、初年度は寸志程度に留まる場合もあります。
年齢を重ねて20代前半になると平均支給額は60万円程度、20代後半には65万円程度(※)にアップします。ただし、一部の企業では、初年度は寸志程度に留まる場合もあります。
■大卒の場合
大学卒の20~24歳の年間ボーナス平均額は368,900円(※)です。このデータには入社2年目以降の社員も含まれますが、新卒のボーナス事情の参考値としてご覧ください。
20代後半になると平均支給額は90万円程度(※)にアップします。ただし、企業の業績や個人のパフォーマンスによって支給額は変動するため、必ずしも同額とは限りません。
■院卒の場合
院卒の25~29歳の年間ボーナス平均額は1,070,500円(※)です。このデータには入社2年目以降の社員も含まれますが、新卒のボーナス事情の参考値としてご覧ください。
30代前半になると、平均支給額は160万円程度(※)までアップします。院卒の場合、専門性の高い技術職などに就くケースが多いため、平均値が高くなっていると考えられます。
※出典:e-Stat「令和6年賃金構造基本統計調査」
【企業規模別】新卒のボーナス事情
ボーナスの支給額は、企業の規模によっても差があります。大企業、中小企業それぞれの新卒の年間ボーナスの平均額をみてみましょう。
■大手企業の場合
従業員数1,000人以上の大企業では、大卒の20~24歳の年間ボーナス平均額は404,100円(※)です。このデータには入社2年目以降の社員も含まれますが、新卒のボーナス事情の参考値としてご覧ください。
20代後半になると平均100万円(※)を超えます。大企業は安定した業績や大規模な経済活動を行っている場合が多く、中小企業よりボーナスが高くなる傾向があります。
また、ボーナスだけでなく住宅手当や退職金制度、各種保険など福利厚生が充実していることも多く、待遇全体での魅力が大きいのも特徴です。
■中小企業の場合
従業員数100~999人の中小企業では、大卒の20~24歳の年間ボーナス平均額は370,100円(※)です。このデータには入社2年目以降の社員も含まれますが、新卒のボーナス事情の参考値としてご覧ください。
20代後半になると、平均90万円程度(※)に達します。企業規模が比較的小さく、業績の安定度や資金力が大手ほど大きくないため支給額はやや低めです。
一方で、中小企業にはアットホームな雰囲気や柔軟な働き方、社員一人ひとりの裁量が大きい点など、給与面以外の魅力もあります。長期的にキャリアを積む上で、仕事を通した成長機会の有無を見定めることが大切です。
※出典:e-Stat「令和6年賃金構造基本統計調査」
【業界別】新卒のボーナス事情
新卒のボーナスは、業界によっても支給額や傾向がさまざまです。主要な業界ごとに、年間ボーナスの平均額や特徴をご紹介します。
■ボーナスが低い傾向がある業界
ボーナスが低い傾向にある業界としては、生活関連サービス業、飲食業、介護・福祉業界(※)などが挙げられます。利益率が比較的低いことや、景気の影響を受けやすいことなどが主な要因と考えられます。
たとえば、飲食業は売上変動が激しく、家賃や人件費など固定費の割合も高いため、賞与原資に余裕が少なくなる傾向があります。介護・福祉業界も機械化できる部分が少なく人件費が中心なことに加え、専門職を多く配置する必要があり、給与設定が高いためボーナス支給額が抑えられることが多いです。
こうした業界への就職を考える際は、ボーナス以外の待遇やスキル習得機会に目を向けてみましょう。
■ボーナスが高い傾向がある業界
ボーナスが高い傾向にある業界としては、インフラ業界、IT・ソフトウェア・通信業界、建設業界(※)などが挙げられます。これらの業界は収益が安定的に上がりやすく、市場競争も激しいため、優秀な人材を確保する目的でボーナスが高く設定されることが多いです。
特に、公共インフラを提供するガス・電気などの分野では、安定した需要と高い収益に支えられており、ボーナス支給額も高くなる傾向があります。また、IT・ソフトウェア・通信業界は、法人・個人を問わず幅広いサービス展開で収益性が高く、新卒でもボーナスが比較的高めに設定されやすいのが特徴です。
※出典:e-Stat「令和6年賃金構造基本統計調査」
新卒のボーナスの使い道

「初めてのボーナスは何に使ったらいい?」と迷う方も多いでしょう。ここでは、ボーナスの代表的な使い道をご紹介します。自分に合う使い方を見つける参考にしてみてください。
■貯金や投資に使う
新卒のボーナスを、将来の安心につながる貯金や投資に回すことは将来への大きなステップです。たとえば、貯金は緊急時の備えや大きな買い物、旅行の資金として活用できます。株式や投資信託など投資に充てれば、時間を味方につけて資産を増やすことが可能です。
無理のない範囲で手取りの一部を貯金や投資に回すことで、資産運用を学ぶよい機会にもなるでしょう。
■家族へのプレゼントを購入する
家族へ日頃の感謝を込めてプレゼントを贈るのも素晴らしい使い道です。普段お世話になっている両親や兄弟姉妹に心のこもった品を選ぶことで、家族との絆を深められます。相手の好みやライフスタイルに合わせて選ぶとより喜ばれるでしょう。自分のがんばりを家族と共有する意味でも意義があります。
■スキルアップのために自己投資をする
ボーナスをスキルアップのための自己投資に使うのもよい選択です。資格取得のための講座やセミナー、書籍やオンライン学習などに充てれば、将来的なキャリア形成や昇給・転職のチャンスにつなげられます。
社会人になりたての時期に学びの習慣を身につけておけば、知識や経験の蓄積が早くなり、長期的に大きなリターンを得やすくなります。スキルアップのための補助金制度を設けている企業も多いため、事前に確認して有効活用しましょう。
新卒入社後にボーナスをアップさせる方法
新卒入社後にボーナスをアップさせるには、企業の業績への貢献や自己成長を意識した働き方が重要です。
まず評価されるポイントを理解し、重点的に取り組むことが効果的です。配属された部署や個人で設定された目標をしっかり達成することは基本ですが、チームや企業全体にプラスの影響を与える提案や改善活動を積極的に行うと評価につながります。
また、資格取得や専門知識の習得など、スキルアップに努めることも昇給・ボーナスアップの材料になります。セミナーや研修参加を自己投資ととらえ、専門知識や能力を磨くことで、将来的にボーナスアップが期待できるでしょう。
新卒のボーナスに関するよくある質問
新卒のボーナス支給の有無や支給額を確認する方法は?
新卒のボーナスについて知るには、まず企業の労働契約書や就業規則をチェックしましょう。
ボーナス制度の詳細や支給基準が記載されています。労働組合がある場合は、組合協約も参考になります。
就職情報サイトで情報公開されているケースもあります。『キャリタス就活』の「企業を探す」から賞与に関する情報が調べられることがあります。気になる企業のページを開き、「採用情報」のタブの「募集要項」を確認してみましょう。
もし労働契約書や就業規則を確認しても判断が難しい場合は、内定後の面談やメールで確認するとよいでしょう。その際は、「入社後の生活設計やキャリアプランを考える上で参考にしたいため、初年度の賞与の支給時期や支給金額について教えていただけますか」など前置きを添えて質問することで、前向きに情報収集をしていることが伝わります。
新卒のボーナスは何カ月分ですか?
新卒のボーナスは、一般的に基本給(固定残業代などは含まない)の1~2カ月分とされています。
金額の目安としては、20万~50万円程度です。支給額は企業の業績や個人の評価によって変わるため、必ずしもこの限りではありません。また、初年度は勤務期間が短いため、夏のボーナスは寸志程度に留まる場合もあります。
2年目以降のボーナスは増える?
2年目以降は、ボーナスが増えるケースが多いです。
これは、1年目に比べて夏・冬ともに査定期間全体を対象として計算されることや、勤務実績や評価が反映されることが理由です。ただし、企業の業績や個人の評価によって増減する場合もあり、必ずしも毎年増えるわけではありません。
国家公務員・地方公務員の新卒のボーナスはどのくらい?
国家公務員のボーナス(勤勉手当)は、人事院の勧告で標準の支給基準(年間4.6カ月分)が定められていますが、入社1年目は在職期間が短いため満額支給とはなりません。
4月入社の場合、6月支給(夏季ボーナス)は在職期間が2カ月となるため、ボーナスの支給額割合は支給基準の30%となります。
地方公務員のボーナスも国家公務員に準ずる形となるため、大きな差はありません。ただ、各自治体で定める給料の条例が異なるため、多少の金額に変動が生じます。
夏、冬ボーナスは何月に支給される?
一般的に民間企業では夏は5月下旬~7月上旬、冬は12月中旬に支給されます。
ただし、新卒のボーナス支給時期は企業によって異なります。国家公務員は夏が6月30日、冬が12月10日と規則で定められており、地方公務員も同様の時期に支給されることが多いです。
新卒のボーナスは将来を見据えて賢く使おう
新卒のボーナスは支給額や時期が学歴や企業規模、業界によって異なり、夏は寸志程度、冬は基本給の1〜2カ月分が一般的です。手取り額や税金も把握した上で、貯金・投資、自己投資、家族へのプレゼントなど、自分の将来や生活に役立つ使い道を考えることが大切です。
就活の際は、ボーナス支給額の大小で志望企業を決めるのではなく、自分が将来描く理想のキャリアを築ける環境かどうかを総合的に見て判断しましょう。
『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。
PROFILE
キャリタス就活編集部
『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。
「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。


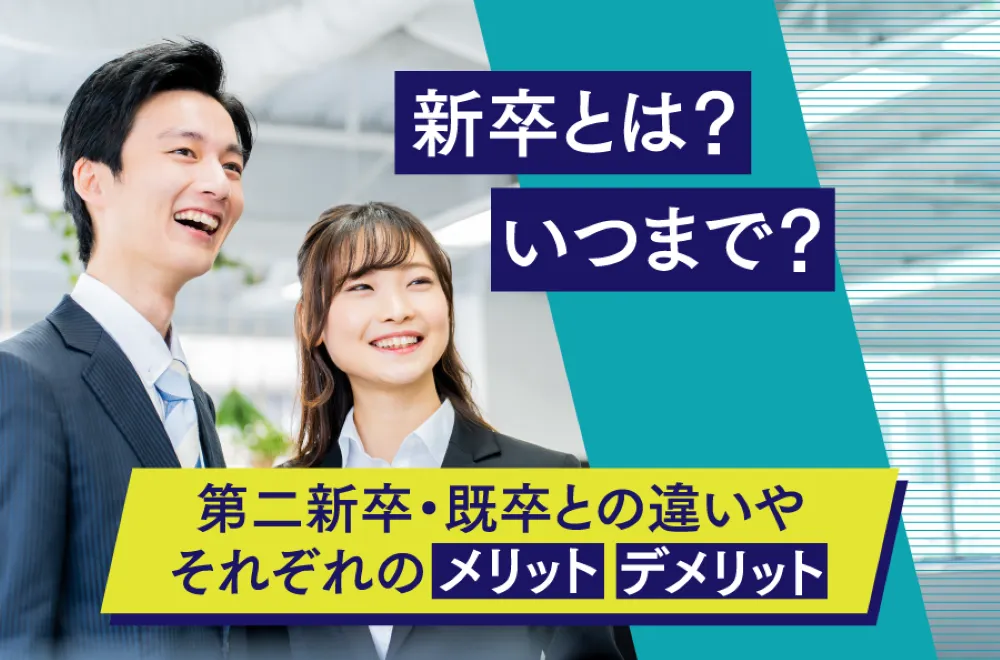

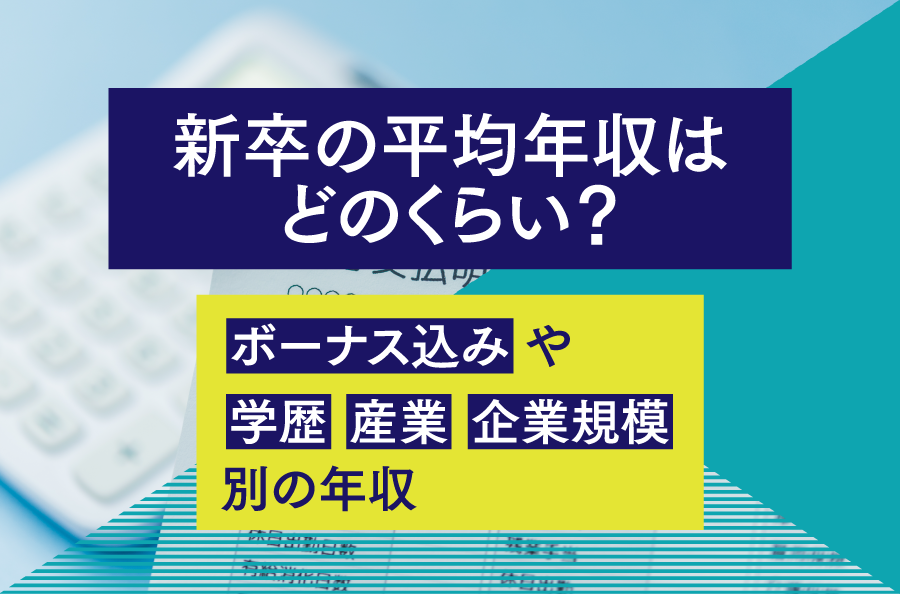







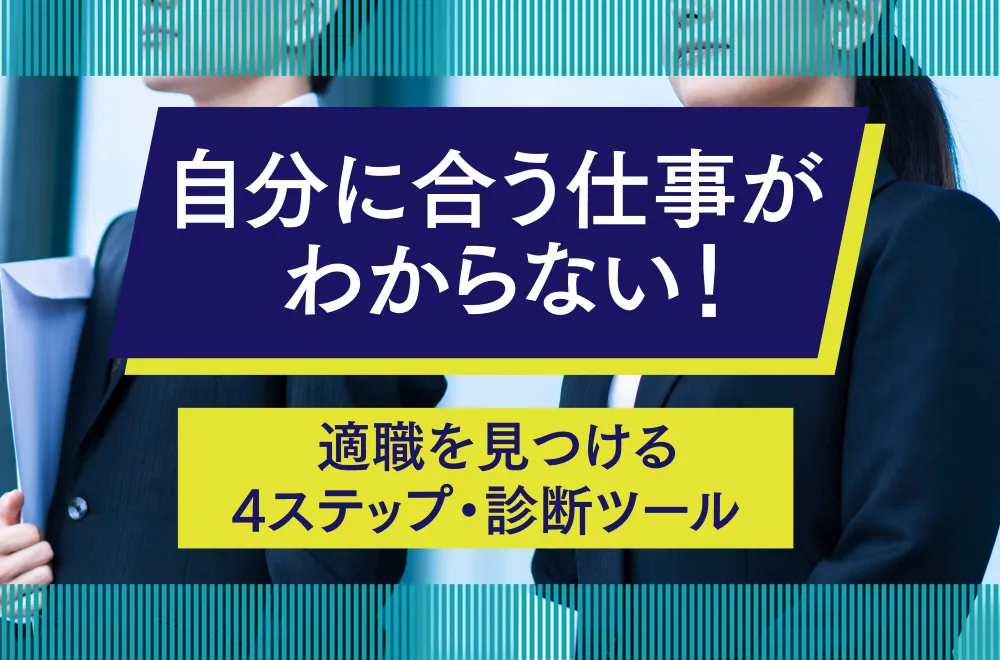





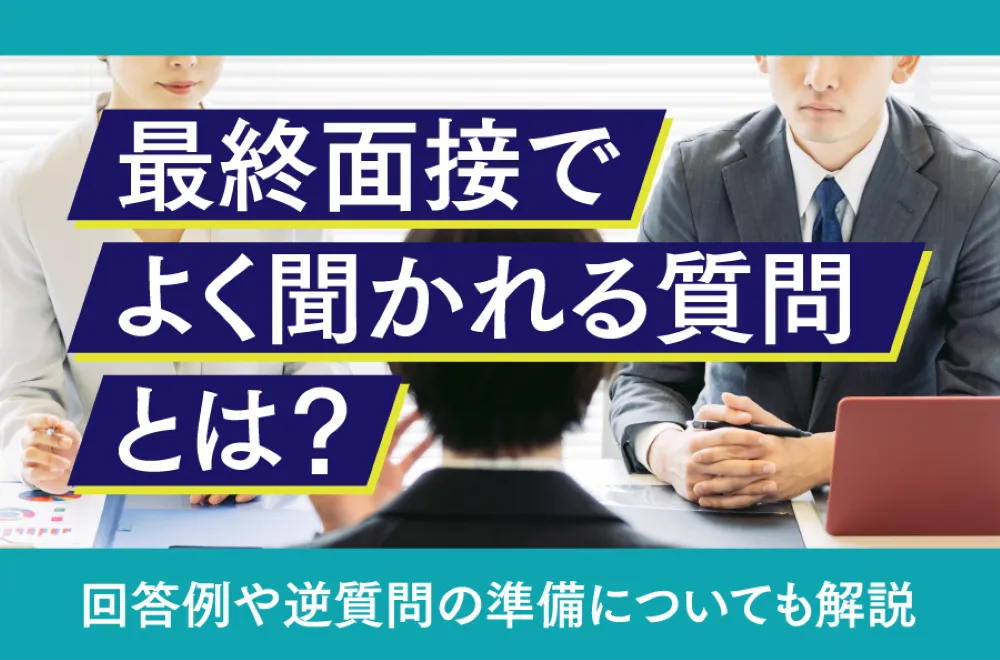
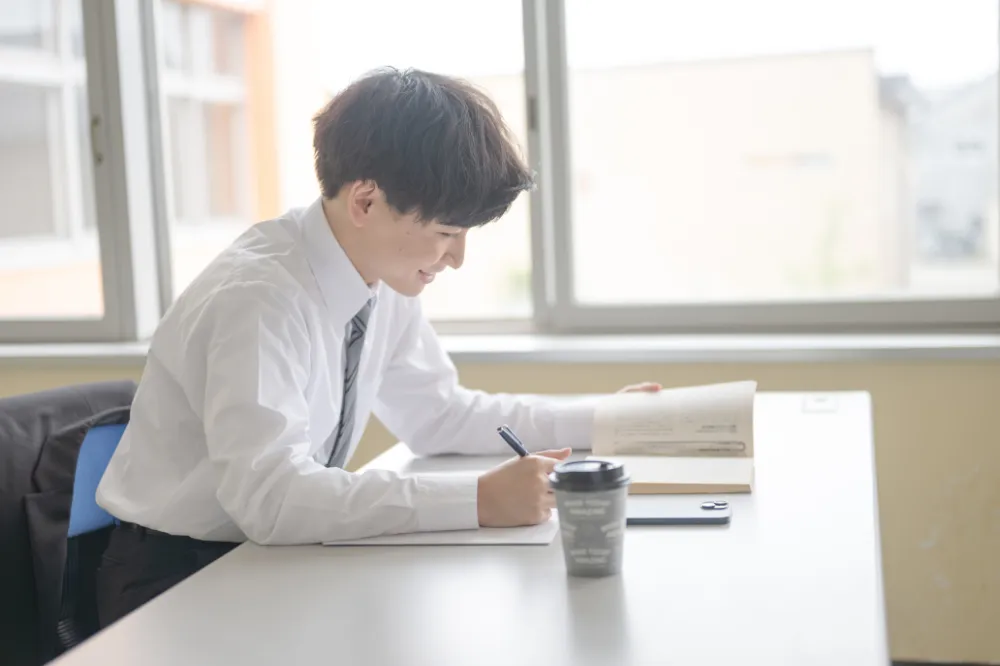
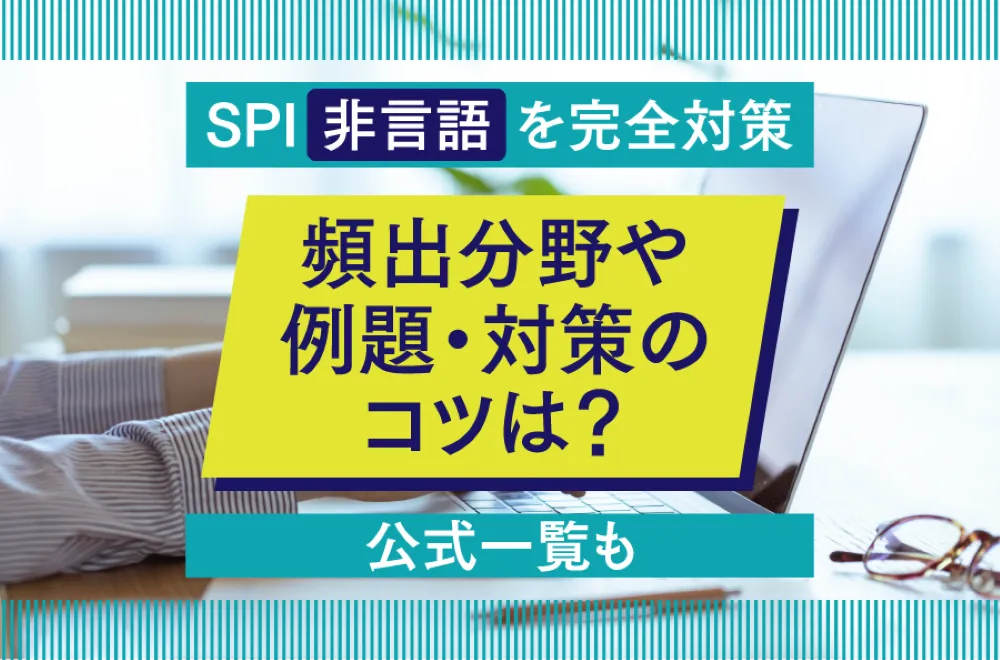
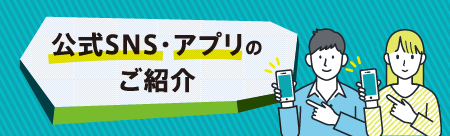
 LINE
LINE
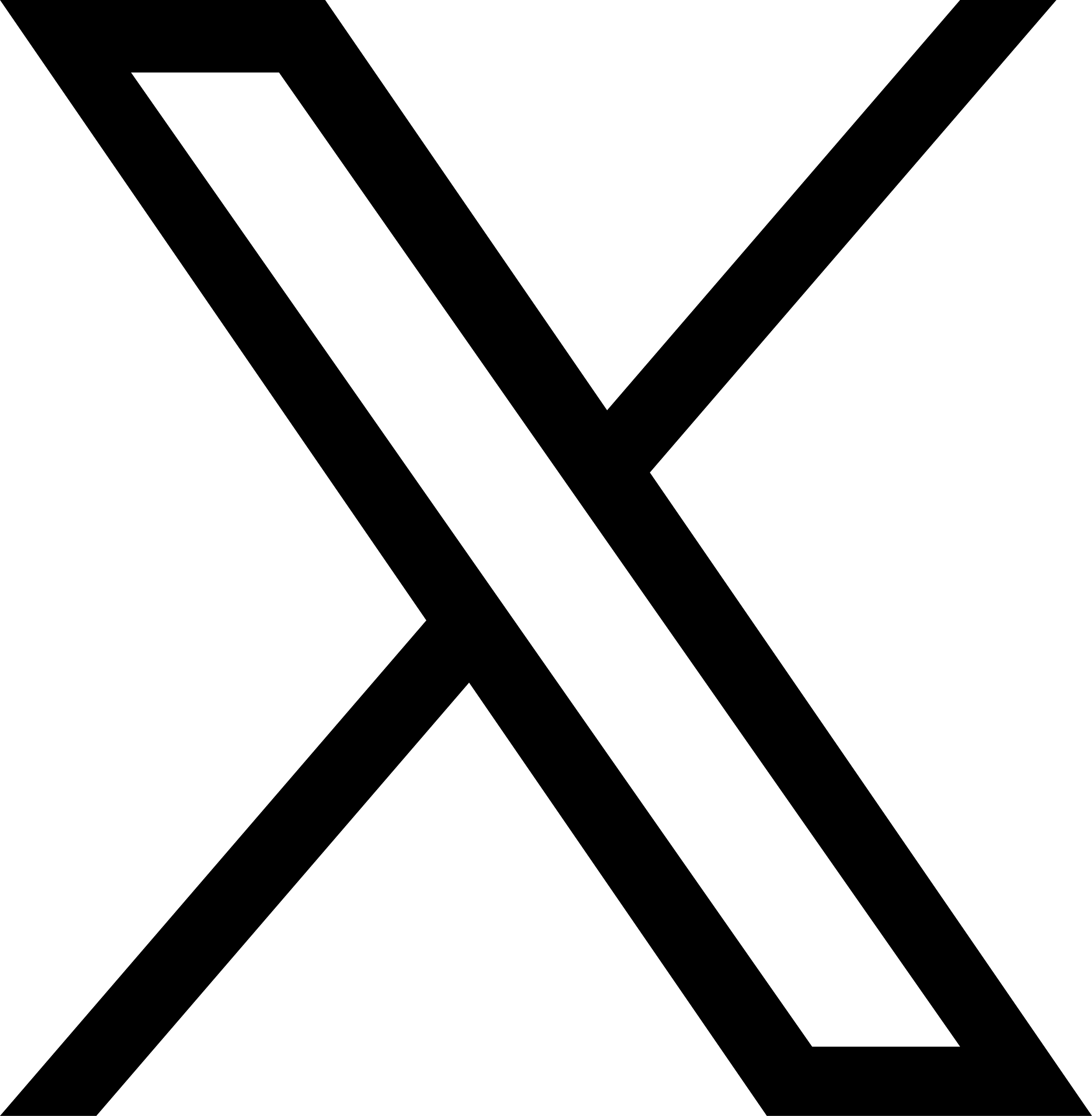 X
X
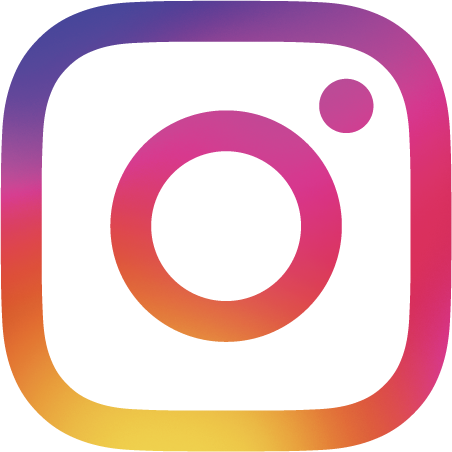 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube