グループディスカッションの役割はどれを選ぶ?役割の種類や決め方を解説
就活ノウハウ公開日:2025.10.08

この記事でわかること
- グループディスカッションには、司会や書記など主に5つの役割がある
- 自分の強みや特性を生かせる役割を担当し、グループに貢献することが重要
- 役割ごとの特徴や評価ポイントを理解した上で役割決めを行おう
就活の選考におけるグループディスカッションには、役割を決める進め方と決めない進め方があります。企業から役割決めについて指示がある場合は、その指示に従いましょう。役割を決める場合、司会や書記、タイムキーパー、発表者などが一般的です。この記事では、自分に最適な役割を見つけるために、それぞれの特徴と役割の決め方を解説します。
そもそもグループディスカッションとは?
グループディスカッションとは就活の選考方法の1つで、数人の応募者がグループで特定のテーマについて話し合い、結論を導き出す形式の選考です。
通常、4~8人程度のグループに分かれて、与えられたテーマについて30~40分程度で議論を行います。議論の最後にはグループで導いた結論の発表を求められます。企業はこのディスカッションを通して応募者のやり取りを観察し、限られた時間内で効率的に議論を進める力やコミュニケーション能力を評価します。
■企業がグループディスカッションを実施する目的
企業がグループディスカッションを実施する最大の目的は、多くの就活生を短時間で効率的に評価することです。グループディスカッションはコミュニケーション能力やチームワーク、問題解決力、論理的思考力といった、実際の業務でも重要なスキルを見極めるのに適しています。
企業は就活生の議論を通して、能力や振る舞いを評価し、次の選考段階に進む候補者を絞り込んでいます。
■グループディスカッションの流れ
一般的なグループディスカッションの流れは以下のとおりです。

はじめに担当者から説明を受け、テーマ確認やグループ分けを行います。そのあと、グループごとに自己紹介や役割決めを行い、テーマに沿って意見を出し合いながら議論を進めます。最終的に発表者がグループの結論を発表します。参加者には協力して結論を導き出す姿勢が求められるため、段取りや役割の理解が重要です。
グループディスカッションの対策については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

グループディスカッション(GD)攻略のコツは?よく出るテーマや対策も解説
就活におけるグループディスカッションは、チームで働く上で必要な能力が試される選考方法の1つです。各役割を理解し、出題テーマや採用担当者が見ているポイントを押さえた事前対策をすることが重要です。本記事では、グループディス…
グループディスカッションの役割の決め方
グループディスカッションの役割の決め方には大きく分けて「立候補制」「指名制」の2つがあります。どちらがおすすめかは場合によって異なるので、状況によって判断していくことが大切です。
■立候補制
立候補制は参加者が自分の得意な役割や挑戦したい役割に自ら手を挙げて決める方法です。参加者が自分の意思で役割を選ぶため、モチベーションが高まりやすい傾向にあります。自分の得意なスキルを発揮したいと考える人には適した決め方といえるでしょう。
ただし、立候補制では役割が重複する場合もあり、その際は参加者同士で話し合いながら役割の調整が必要です。
また、積極的でない人は役割を得られない場合があることも理解しておきましょう。
■指名制
指名制は特定の人がほかの参加者に役割を割り振る決め方です。基本的には初対面の相手のスキルや能力はわからないため、立候補制がメインとなりますが、どうしても役割が決まらない場合は司会が指名制で決めるケースがあります。
この決め方では、指名された人が与えられた役割に不安を感じる場合もあるでしょう。そのため、指名する側は相手の意向を尊重し、柔軟に対応することが大切です。
実際に議論を進める際は、指名された人が役割を果たしやすいように、周囲の参加者がサポートし合うとよいでしょう。たとえば、書記担当のサポートをする場合、議論の要点をまとめた発言をするといったことが挙げられます。
役割決めは何分くらいで行うのがベスト?
グループディスカッションの時間にもよりますが、役割決めをする際は1分~3分をめどに決めるようにしましょう。
これは、限られた時間の中でもっとも重要な「議論」の時間を確保するためです。役割決めだけで多くの時間を消費してしまうと、テーマに対する結論を導き出す時間がなくなってしまいます。
もし立候補がない場合は、指名制に切り替えるなど臨機応変に対応し、効率よく進めましょう。
グループディスカッションの役割は5種類!それぞれの評価ポイントも

グループディスカッションにはどのような役割があり、それぞれどのような人が向いているか、事前に把握しておくと、安心して本番に臨めるでしょう。またそれぞれの評価のポイントを理解することで、自身の強みに適した役割を見つけることができます。ここでは、グループディスカッションの5つの役割について詳しく解説していきます。
■ファシリテーター・司会
ファシリテーター・司会は、議論の進行を担当する役割です。主に話し合いの流れを管理し、参加者全員が意見を出しやすい環境を整えます。話が脱線した際には、元の議題に軌道修正したり、議論の内容を集約する力が求められます。
周囲に気配りができる人やリーダーシップのある人に向いている役割といえます。
ファシリテーター・司会の評価ポイント
・参加者の意見を公平に扱い、全員の意見を結論に反映させられるか
・議論の進行手順を明確に示し、メンバー全員の同意を得られるか
・発言の少ないメンバーからも積極的に意見を引き出せるか
ファシリテーター・司会に向いている人は?
・参加者全員の意見を引き出せる人
・リーダーシップがある人
■タイムキーパー
タイムキーパーは、議論の時間管理を担当する役割です。限られた時間内で効率的に議論を進めるために、個人で考える時間、議論する時間、結論をまとめる時間、発表の練習時間などといった各セッションの時間を適切に配分し、進行をサポートします。
グループディスカッションでは時間配分が重要になるため、事前に議題ごとの時間を設定し、進行中は参加者に残り時間を伝えたり、議論が白熱して予定通りに進まない場合に残りの時間配分を調節することが求められます。
タイムキーパーは「やること」が明確なため、時間管理が得意な人だけでなく、全体の流れを俯瞰して見られる人におすすめの役割です。
タイムキーパーを担当の評価ポイント
・円滑に議論するために司会をサポートできるか
・残り時間を考慮して適切なタイミングで次の議論へ移行させられるか
・議論に積極的に参加しながらも、時間管理を徹底できるか
タイムキーパーに向いている人は?
・時間管理が得意な人
・先読みして行動するのが得意な人
■書記
書記は、議論で出た意見や結論を記録する役割です。あとから内容を振り返れるよう、議論の内容を整理しながら正確にメモを取る力が求められます。情報を整理する力や論理的思考力に優れた人に適した役割といえるでしょう。
また、このポジションは発言が苦手な人や、初めてグループディスカッションに参加する人におすすめな役割です。
書記の評価ポイント
・他人が見返しやすいようにきれいな字で記録できるか(手書きの場合)
・議論の流れをしっかり理解し、発表者が参考にしやすいように要点をまとめられるか
・記録しながらも積極的に議論に参加し発言できるか
書記に向いている人は?
・情報の要点を簡潔に整理できる人
・集中して人の話を聞ける人
■発表者
発表者は、議論の結果を面接官やほかのグループに伝える役割です。議論で得られた結論を、PREP法(※)などを用いてわかりやすく、かつ魅力的に伝える力が求められます。発表のあとに質疑応答がある場合は、予期せぬ質問に柔軟に対応できる能力も必要になります。
コミュニケーション能力が高く、プレゼンテーションが得意な人に向いている役割といえます。
※結論、理由、具体例、結論の順序で話を構成するフレームワーク
発表者の評価ポイント
・発表の際にハキハキと自信をもって発表ができるか
・議論の流れと結論を論理的にわかりやすく説明できるか
・質問に対して的確かつ冷静に回答できるか
発表者に向いている人は?
・人前で話すことが得意な人
・積極性があり自信をもてる人
■役割なし
役割がない参加者は、特定の役割をもたずに自由に発言することで、議論に新しい視点を提供します。議論の活性化を図るため、アイデアを積極的に出すほか、出た意見に対する同意や不同意を明確に伝える姿勢が大切です。
同時に、役割のあるメンバーを助ける動きも求められます。進行役が議論をまとめやすいように補足を加えたり、書記役が書き漏らした点をフォローしたりと、周囲をサポートしましょう。特別な役割がなくとも重要なポジションです。
自分の意見を明確に伝えられる人や相手の意見を傾聴できる人、全体を俯瞰して気を配れる人が適しています。役割がない場合でも積極的に議論に参加することが大切です。
役割がない場合の評価ポイント
・積極的に議論に参加し、議論を前に進められるか
・新しい視点やアイデアを提案し、議論を深められるか
・ほかの役割の人をサポートし、議論を円滑に進められるか
役割がなかったら採用担当者からの評価は下がる?
役割がないことで評価が下がることはありません。
重要なのは積極的に議論に参加し、チーム全体で結論を導き出すことに貢献する姿勢です。役割なしの参加者は役割に縛られず、積極的に発言できるので、むしろ目立ちやすいポジションともいえます。
役割がある人のサポートや独創的なアイデアの提供など、自分なりの方法でチームに貢献することで評価につながるでしょう。
【タイプ別】グループディスカッションでおすすめの役割
グループディスカッションの際、自分にはどの役割が合っているのかわからないという人も多いのではないでしょうか。ここでは就活生のタイプ別におすすめの役割を紹介していきます。
■議論することに苦手意識がある
おすすめの役割
・書記
・タイムキーパー
議論が苦手な方におすすめの役割は、書記やタイムキーパーです。どちらもディスカッションへの直接的な発言が少なくても役割を遂行でき、比較的負担が軽く参加しやすいポジションです。
書記は議論の内容を記録する役割のため、議論の流れを把握し整理する力が求められます。タイムキーパーは、時間を管理する役割で、ディスカッション全体の進行を見守るポジションです。むやみに苦手な役割に挑戦する必要はないので、自分の適性に合った役割からやってみましょう。
■できる限り面接官に好印象を与えたい
おすすめの役割
・ファシリテーター、司会
・発表者
できる限り面接官に好印象を与えたい場合は、ファシリテーターや発表者の役割が適しています。どちらもほかの役割と比べると、積極的な姿勢や主体性などアピールできるポイントが多く、それらを自然に伝えやすいため、面接官にも好印象を与えられる可能性が高まります。
ファシリテーターは議論を進行する役割のため、リーダーシップやコミュニケーション能力が求められます。また、発表者は、明確な表現力と堂々と発表する自信が不可欠です。企業が求める人物像としてよく挙げられる「主体性」「協調性」「責任感」「論理的思考力」などを効果的にアピールできるでしょう。
グループディスカッションの役割によって有利・不利はある?
基本的に役割による有利・不利はありません。
グループディスカッションで大切なのは「チーム全体で結論を導き出すことにどれだけ貢献できたか」です。自分の役割をうまく果たせればプラスの評価、果たせなければマイナスの評価がつく可能性があります。自分の特性をもっとも生かせる役割を選ぶことが重要です。
【ケース別】グループディスカッションの役割決めを円滑に進めるための対処法

グループディスカッションでは、役割決めの段階でトラブルが発生するケースあるでしょう。そんなときに慌てずに対処できるよう、ケース別の解決方法を紹介していきます。
■誰も立候補せず役割が決まらないケース
初めて顔を合わせるメンバーが集まってグループディスカッションを行うため、お互いの様子を伺って、なかなか立候補者が出ないこともあります。限られた時間の中で役割を決めて議論を進める必要があるため、この場合は自ら立候補するのがおすすめです。
■担当したい役割が被ってしまったケース
担当したい役割が被ってしまった場合は、冷静な対処が重要です。お互いの立候補した理由を聞いた上で、どちらがその役割により適しているかを客観的に判断しましょう。解決しない場合は、柔軟に役割を譲り、代わりに発言で貢献するのも1つの方法です。
もっとも避けるべきなのは、役割争いで時間を浪費してしまうことです。迅速に役割を決め、議論に集中できるように進めましょう。
■苦手な役割を任されたケース
指名制や希望が重なってしまい苦手な役割を任された場合は、ほかのメンバーに役割を代わってほしいと伝えましょう。「〇〇が得意なので〇〇を担当させていただけませんか」と正直に伝えることが大切です。
ただし、自分がやりたい役割をやるために断り続けるのは、協調性がないという印象を与えてしまいます。どの役割でもこなせるように事前に練習しておくと、本番でも問題なく対応できるでしょう。
■役割を決める必要がないという意見が出たケース
グループ内に、「役割を決める必要がない」という考えをもつ人がいる場合もあります。
参加者全員が主体的に意見を出し合い、サポートし合えるグループであれば、役割分担がなくても議論を円滑に進められます。
必ず役割決めが必要というわけではないので、このような場合は無理に役割を決めず、議論の流れに沿って進めても問題ありません。ただし、議論を効率よく進めるには役割を決めたほうがスムーズに進むケースもあるため、慎重に進めましょう。
役割問わず意識したいグループディスカッションでの注意点
グループディスカッションに参加するにあたってどのような点に注意すべきなのでしょうか。ここでは、役割に関係なく参加者全員が意識したい注意点について紹介します。
■無言の時間が続かないようにする
無言の時間が続くと、議論の流れが途切れ、参加者が発言しにくい雰囲気になりがちです。発言しやすい雰囲気を作るためにも無言を避け、積極的に話題を提供するとよいでしょう。また、ほかの参加者の意見を引き出す質問を投げかけるのも効果的です。自分から発言することで場の雰囲気を活性化し、議論を前進させることができます。
■人の意見を否定しない
グループディスカッションでは、人の意見を否定せずに受け入れつつも、意見に対して率直に議論をする姿勢が重要です。否定的な態度は、相手を不快にさせるだけでなく議論の進行を妨げる可能性があります。ほかの参加者の意見を尊重しながら、自分の考えを前向きに述べることを心がけましょう。
参加者全員が安心して意見を出し合える環境作りを心がけることが大切です。
■論点に沿った発言をする
議論を効果的に進めるためには、論点に沿った発言を心がけましょう。議論が脱線すると、時間が無駄になるだけでなく、結論にたどり着けない可能性もあります。自分の発言が論点に合っているかを常に意識することが大切です。
また、誰かの発言により話題が逸れそうなときは、元のテーマに戻るよう自然に促します。これは司会でなくてもできるので、気がついた際に行いましょう。
■クラッシャー行為をしない
クラッシャー行為とは、他人の意見を無視する、議論を意図的に混乱させるなどの不適切な行為を指します。このような行為は、チームの協力を阻害し、全体の成果を損なう原因になりかねないため避けましょう。
グループディスカッションでは、全員が協力し合う姿勢をもつことが大切です。もし自分の意見が受け入れられないと感じても、感情的にならず、冷静にほかのメンバーの意見を聞き入れる姿勢を示しましょう。
チーム内にクラッシャーがいた場合の対応方法
クラッシャーは大きく3つのタイプに分けられます。それぞれのタイプの特徴と対応方法を確認しましょう。
■自己主張が強いタイプ
自分の意見が強く、議論を主導し周囲の発言機会を奪うことがあるタイプです。司会が冷静に介入し、意見を肯定的に受け止めつつ、「ほかの方の考えも聞いてみましょう」と促しましょう。
■相手の話を否定するタイプ
ほかの人の発言に対して否定的な反応を示し、議論を停滞させやすいタイプです。「それも1つの視点ですね」と受け流し、代案を促すなど前向きな方向へ議論を誘導しましょう。感情的な対立を避け、議論の目的を再確認することが効果的です。
■話を脱線させるタイプ
議題からそれた個人的な話や無関係な話を持ち出すタイプです。時間の浪費や議論を停滞させてしまう場合もあるため、相手の発言は尊重しつつ、本題に戻すように促すことが大切です。司会でなくてもチームの一員として軌道修正することで、議論をスムーズに進めることができます。
■時間内に話をまとめる
限られた時間内で議論をまとめる能力は、グループディスカッションにおいて非常に重要です。時間配分を意識し、議論が終盤に差しかかったら、話題をまとめて結論を導き出すことが求められます。
タイムキーパーが時間の管理をしっかりと行うだけでなく、ほかの役割のメンバーも時間内に議論を終わらせる意識をもちましょう。
また、議論の要点を個条書きにしておくと話をまとめる際に役立ちます。
グループディスカッションの役割に関するよくある質問
グループディスカッションの役割は兼任していい?
基本的には1つの役割に集中することが推奨されます。
複数の役割を兼任すると、どちらも中途半端になってしまい、十分な成果を出せない可能性があります。
ただし、グループの人数が少ない場合や、タイムキーパーと書記のように負荷の軽い役割同士であれば兼任も可能です。
グループディスカッションのテーマによって必要な役割は異なる?
基本的な役割(司会、タイムキーパー、書記、発表者)はどのテーマでも共通しています。
ただし、テーマの種類によっては追加で特定の役割が必要になる場合もあります。
たとえば、創造性を求められる新規企画テーマでは、「アイデアマン」(議論が活性化するように、多角的なアイデアを出す)といった役割を決めるケースがあります。
また、複雑な課題解決型のテーマであれば、「監視役」(論点がずれた場合に指摘する)がいることで、より質の高い議論ができるでしょう。
グループディスカッションで役割を決めずに進めるのはあり?
無理に役割を決める必要はありません。グループ内で話し合って「役割を決めない」と判断することも問題はありません。
ただし、役割を決めずにグループディスカッションをはじめると、議論が混乱しやすくなり、効率よく進められない場合がありえます。一般的には役割を決めておくことで、自由に議論するよりも効率よく進められます。
企業から「役割は決めずに議論してください」と指示があった場合はその指示に従いましょう。
グループディスカッションではどんな人が選考を通過しやすい?
その企業が求める人物像を体現している人は、選考を通過しやすいといえます。一般的にはチームワーク力があり、積極性と協調性のバランスが取れている人が通過する可能性が高いでしょう。
積極的にディスカッションに参加し、周囲と協力しながら結論を導き出せる人材が評価されるといわれています。また、自分の強みを生かしてチーム全体に貢献する姿勢も評価されます。
こういった一般的なポイントを踏まえた上で、その企業ならではの評価ポイントについてもしっかり情報収集しておきましょう。
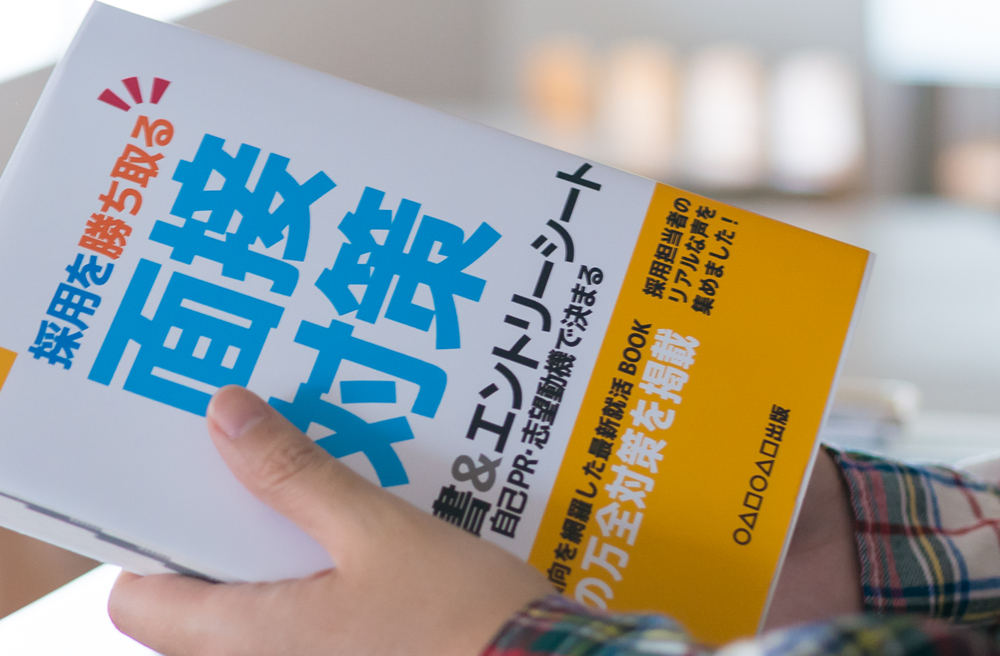
就活生必見!!「企業が求める人物像」を知り、面接対策を万全にしよう
就活生にとって、企業が求める人物像を理解することは面接対策の第一歩です。この記事では、企業がどのように理想の人物像を設定し、選考で何を重視するかを解説します。あなたの就職活動を成功させるための具体的なアドバイスとポイン…
グループディスカッションでのチーム人数が5人の場合の役割分担は?
5人グループの場合は、基本的に司会(ファシリテーター)、書記、タイムキーパー、発表者の4つの役割を分担し、1人は役割なしとなります。
役割がない人も発言や役割がある人のフォローを行い、グループ全体をサポートすることが重要です。
役割分担で時間をかけすぎないよう、まず司会を決めてからほかの役割を決めると議論がスムーズに進みます。
グループディスカッションの役割を理解して選考突破を目指そう
グループディスカッションでは、どの役割にも有利・不利はなく、自分の特性を生かせる役割を選んで積極的に貢献することが評価につながります。役割の決め方やグループディスカッションの進め方のコツを把握し、チーム全体の成功を意識した立ち回りを心がけることが重要です。自分に合う役割を理解した上で、自信をもってグループディスカッションに臨みましょう。
『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。
PROFILE
キャリタス就活編集部
『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、就職活動・就活準備をがんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ情報をお届けしています。
「面接がうまくいかない」、「そもそも就活って何からはじめるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。











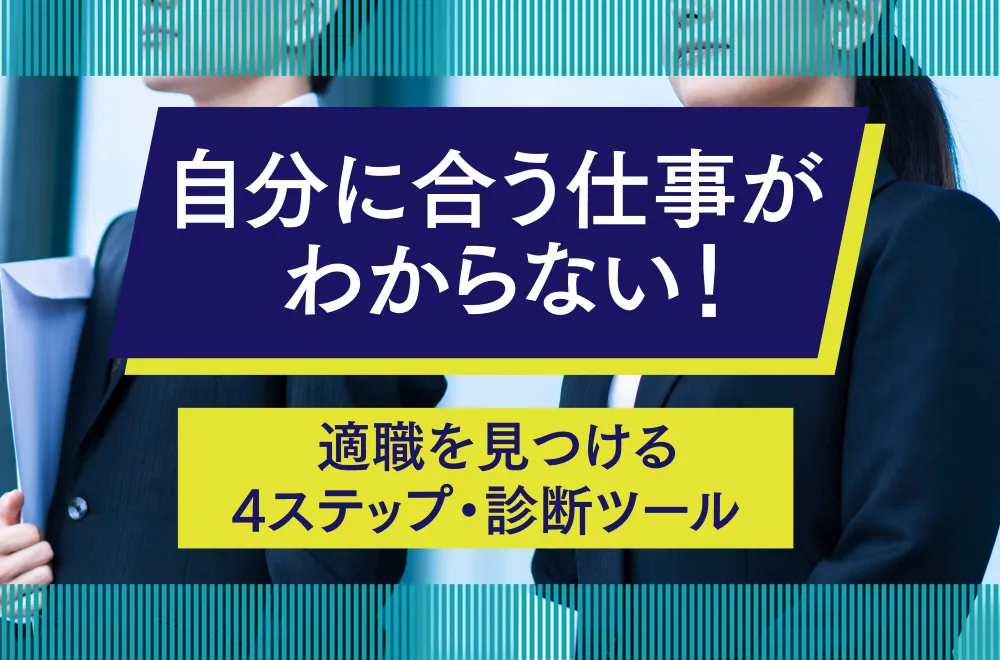

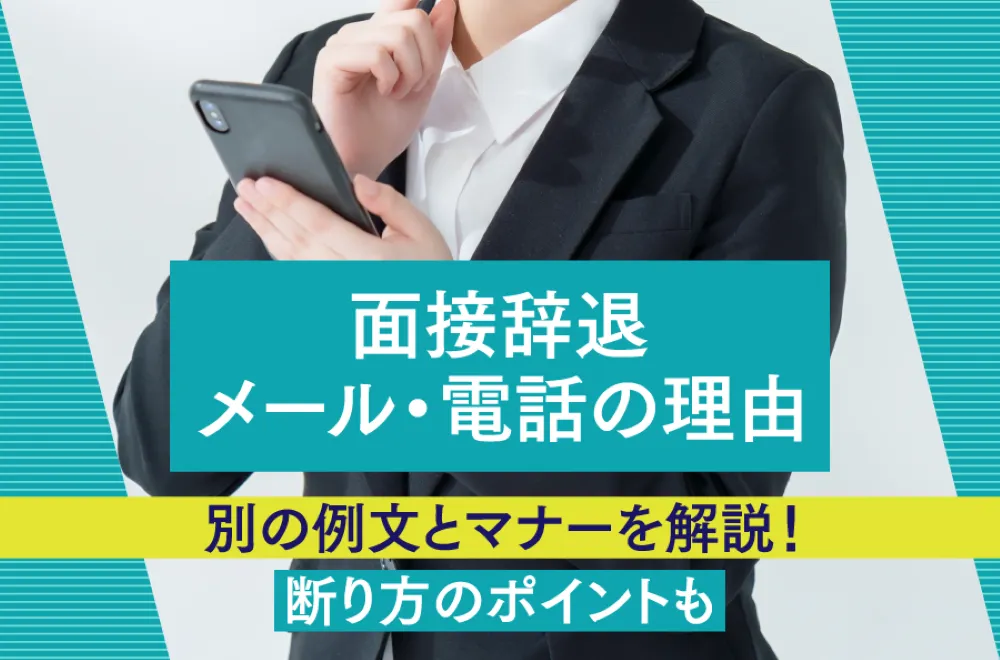





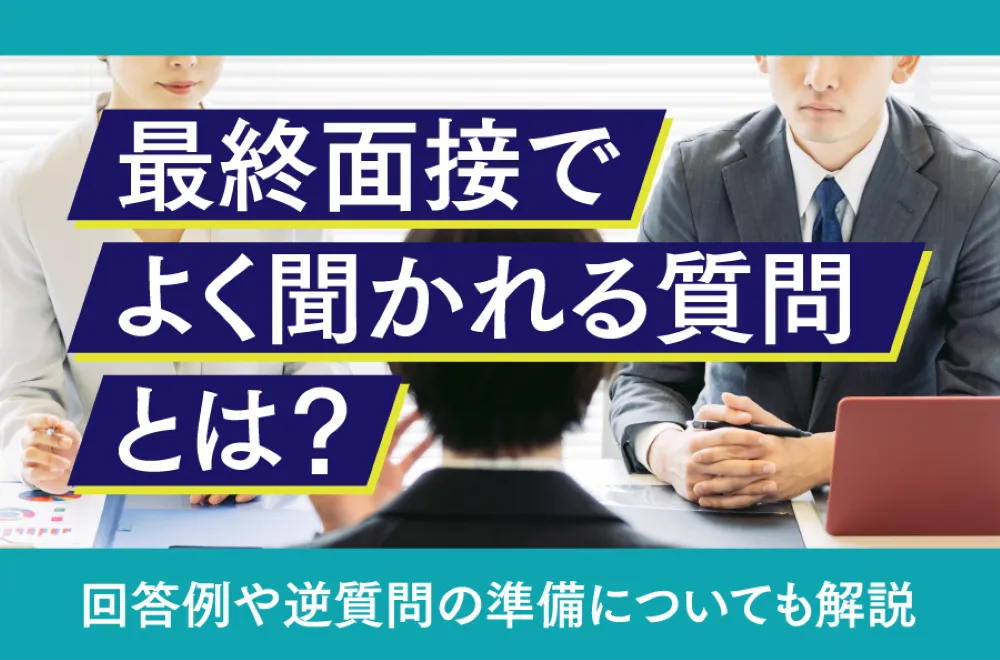
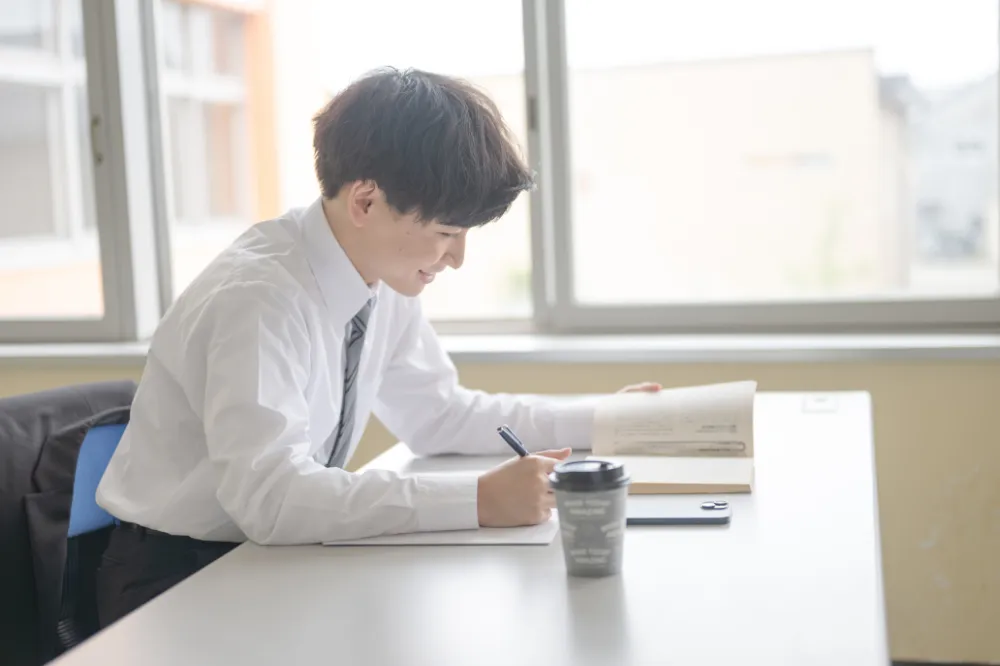
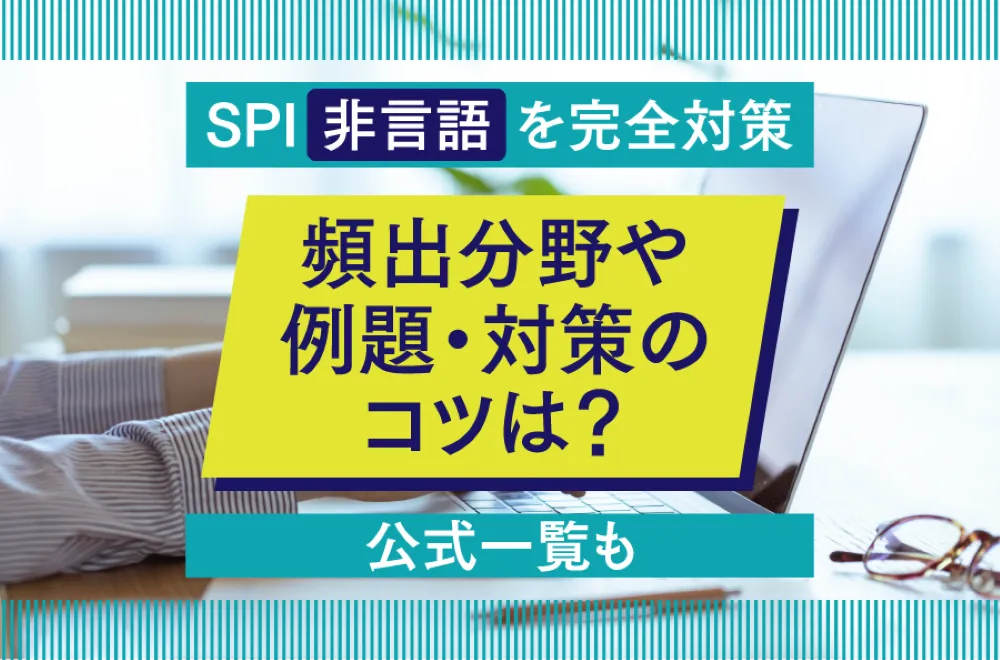
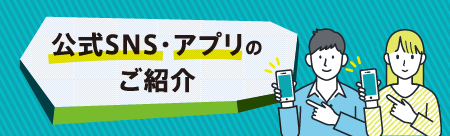
 LINE
LINE
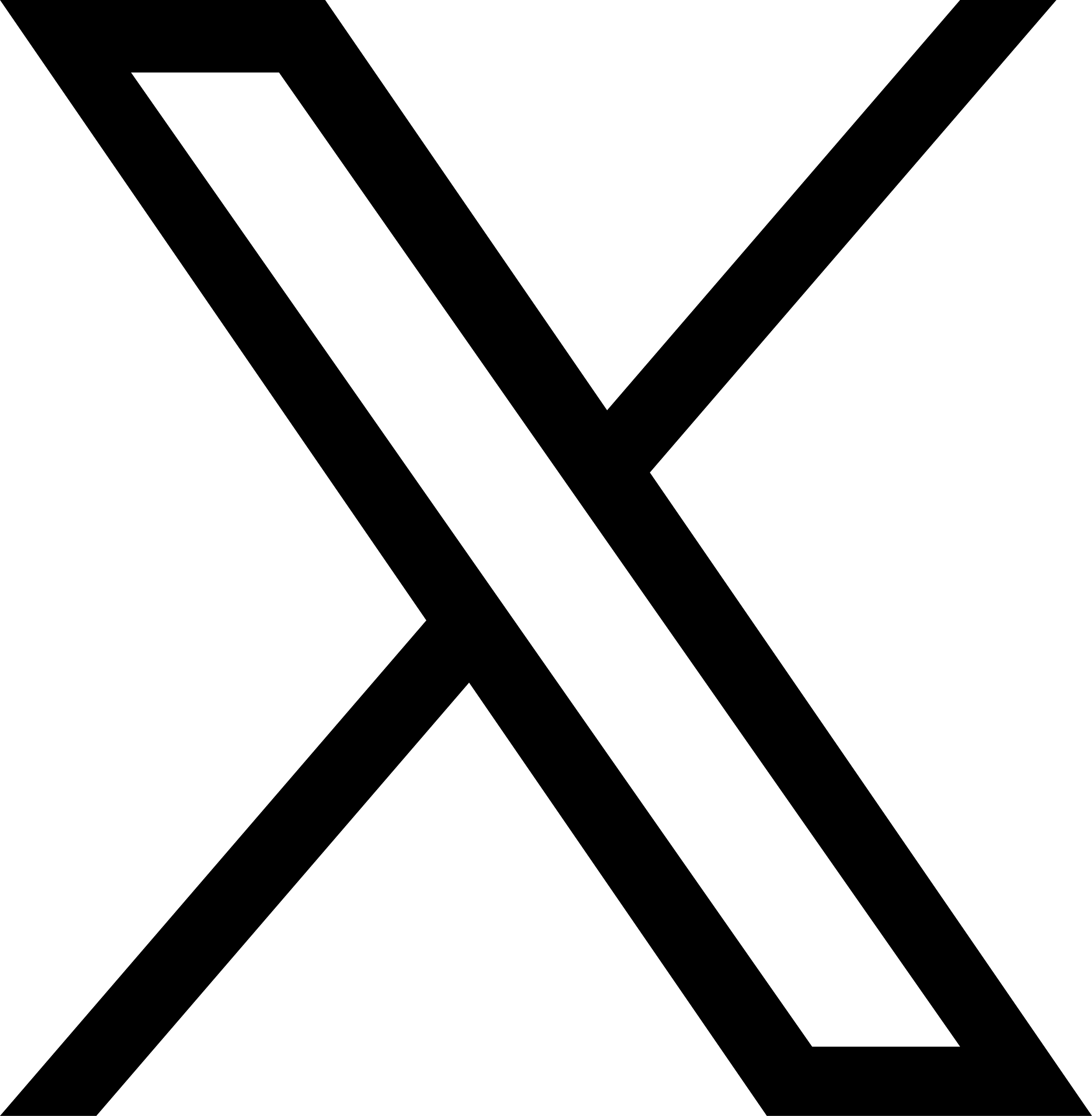 X
X
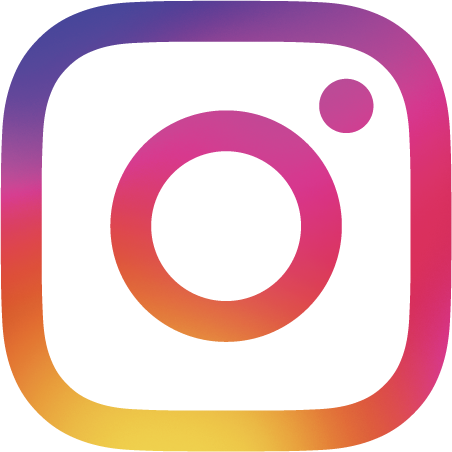 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube