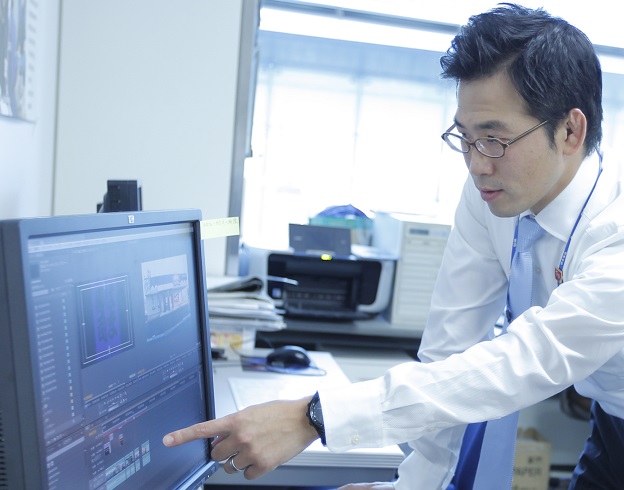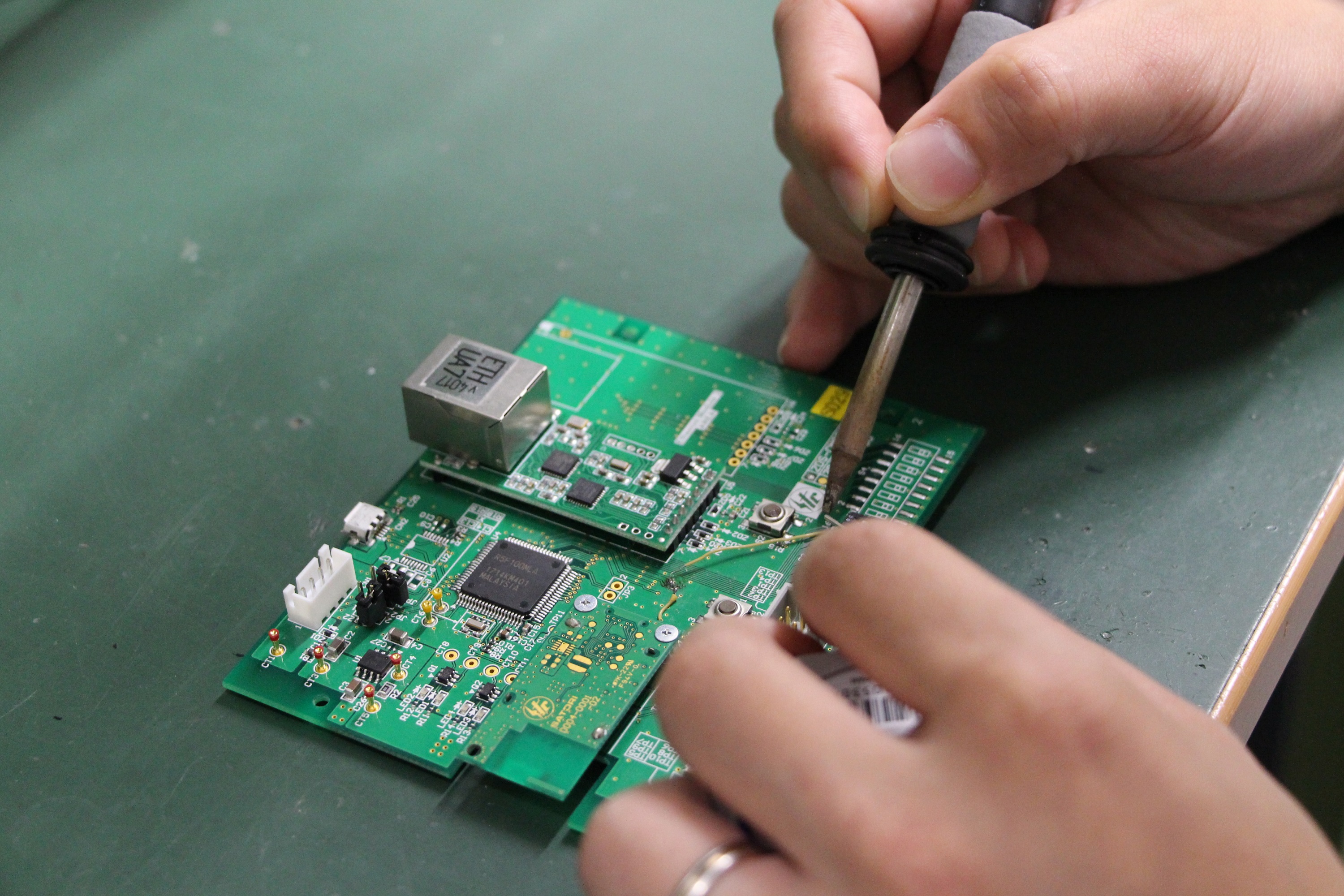東京都商社(食品)
株式会社ゼンショーホールディングス
- 4.19
-
5,271 フォロワー
- 海外事業展開に注力
『世界中の人々に安全でおいしい食を手軽な価格で提供する』
『食で世界を変える。』

目次
私たちの事業
私たちは、調達・製造・物流・販売までを一貫管理する「食の総合企業」です。
【調達・グローバルバイヤー部門】
食の入り口である「調達」部門は、お客様に安全・安心な食材を届けるために世界中の新たな国と地域で新規ルート開拓を行い、国によって異なる食文化や習慣、ニーズに合わせた視点も持ち合わせながら、こだわりぬいた食材を調達します。
【製造・生産部門】
仕入れた食材を安心・安全にこだわりながら生産・製造加工、さらに管理を行います。
【物流部門】
加工された食材の鮮度を落とすことなく、各店舗等に配送するためのコールドチェーンも自社で運営しています。
【国内外食・海外外食】
日本を代表する「すき家」をはじめとしたバラエティ豊かなブランドを多数展開しています。
お客様に自社でこだわりぬいた「食」をいつでも提供する。そのために人・モノ・カネをマネジメントし、日本だけでなく世界のどこでも安定した運営ができるよう努めています。
【小売事業】
外食のプロとして培った商品開発能力や調達能力を最大限活用し、食材の仕入れや管理を行っています。小売部門では、お客様に”安全で美味しい食品”を提供しています。
【介護事業】
「食で人生を彩るために」ゼンショーならではの外食事業で培ったマネジメント力を活かしながら、介護施設の運営を行っています。
【IT・技術部門】
お客様に最善のサービスを提供するために、技術革新の力で内製化を進め、ゼンショーの成長をさらに加速させています。
2021年10月には経済産業省が定める「DX認定取得事業者」にも認定されました。
【R&D部門】
高品質な食品をお客様に届けるため、また、より「おいしい」製品を目指して調理加工工程の最適化や、様々な技術の研究をしています。
【建設部門】
お客様が心地よく利用できる店舗を自社の経験をもとに建設しています。そして世界の国と地域で「食」と「職」を展開していきます。
【本部部門】
これらの各事業が最大限にパフォーマンスを上げられるよう、本部の各部門は常に改善を重ねてスムーズな会社運営ができるよう力を発揮しています。
(人事・法務・経理財務・広報 等)

私たちの特徴
企業理念
◆世界から飢餓と貧困を撲滅する◆
『世界から飢餓と貧困を撲滅する』
世界の飢餓貧困問題やSDGsについて、誰もが一度は気になったことがあるのではないでしょうか?
世界にはすべての人が食べることができる十分な食料があるにもかかわらず、
食料供給が過剰な国と不足している国とのアンバランスが
一部地域での飢餓を生んでいると言われています。
この世界的問題に対して創業時から一貫して、一時的なボランティアではなく
持続可能なビジネスの力で問題を解決しようとしているのがゼンショーホールディングスです。
私たちは世界の食事情を変えることのできるシステムと資本力を持ち、
「フード業世界一」企業となり、世界から飢餓と貧困を撲滅することを目指します。

組織の特徴
壮大な理念実現のために一体となり挑戦する
セクショナリズムを排除して年次やポジションに関係なく、現状を否定し打破しながら改善・改革を重ねることを重視しています。
若い社員にも新規事業や責任あるポストを任されることもあり、大きく成長できるチャンスが存在しています。
最近では、入社1年目の社員の改善提案が全国で採用されたことがあります。
お客様にとっても従業員にとってもより良くなる改善をこれからも行い、人と共に組織も成長していきます。

働く仲間
変化を前向きに捉えることが出来る人材
ゼンショーでは、求める人物像として下記を掲げています。
◆主体性を持って行動できる人
ゼンショーの仕事とは、会社から与えられるものではなく自らつくり出すものです。創意と挑戦心を持って主体的に行動できる人財をゼンショーは求めています。
◆変化に柔軟に適応できる人
国際社会は大きな時代の転換期を迎えています。
グローバルな視点でいち早く変化を捉え、固定概念に縛られず柔軟に適応していくこと、現状を否定し打破しながら自己進化を遂げていくことが求められます。
写真からわかる私たちの会社
私たちの仕事
仕事内容
●すべての人に安全でおいしい食を手軽な価格で提供できるチェーンストアの創造
●世界各国で機能する食のインフラの構築
論理的・科学的な思考を土台とし、技術革新によって商品・サービスを持続的に進化させていきます。
若手社員であっても自ら起案し実行していく企業風土があり、食というフィールドで創意と挑戦心を持って新たな価値を生み出していく仕事です。

職種別に仕事を知る
-

総合職コース ~”食のスペシャリスト”を目指して~
ゼンショーは”食”に関わる全ての工程を自社で行っており、働くフィールドは多岐にわたります。自身のキャリアプランに基づいて120以上の職種から様々な経験を通じ、食のスペシャリストを目指していただきます。
#人事 #計数管理 #財務 #経理 #総務 #経営企画 #広報 #プロモーション
#商品開発 #品質管理 #土地物件開発 #国内外食 #海外外食 #小売 #製造 等…… -

グローバルバイヤーコース ~”食”のインフラを世界へ~
貿易実務や受発注業務から、現地での新規ルート開拓など、バイヤーとして活躍を目指していただくコースです。将来的には、新たな地で商社機能を創っていただきます。
#バイヤー #貿易執務 #新規ルート開拓 -
IT・技術コース ~技術の革新で、お客様と従業員を笑顔にする~
お客様に最善のサービスを提供するために、技術革新の力で内製化を進め、ゼンショーの成長をさらに加速させていただきます。
#機械設計 #プログラマー #システムエンジニア #AI・IoT #DX #ロボット -

R&Dコース ~世界中のすべての人々の「おいしい」を追求し続けるために~
高品質な食品をお客様に届けるため、また、より「おいしい」製品を目指して調理加工工程の最適化や、様々な技術の研究をして会社を支えていただきます。
#育種研究 #調理技術開発 #食材加工研究 #健康栄養研究 #嗜好研究 #食品安全 -

介護コース ~安全でおいしい食と快適な住環境を提供します~
ゼンショーは介護事業も展開しています。食に関するすべてをマネジメントしているノウハウを活かして、より居心地の良い施設を展開し、介護事業におけるゼンショーブランドの早期確立を目指していただきます。
#施設運営 #食事改革 #新規オープン #管理本部 -
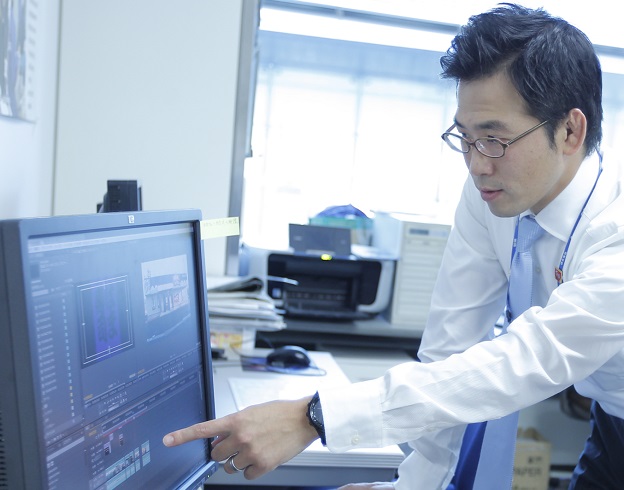
法務コース ~円滑に事業展開をしていくために~
ビジネスを展開していく上で企業法務全般に関わる、専門性の高い分野で活躍していただきます。
#法務 -

建設コース ~お客様に食を提供していく環境づくり~
食のインフラを広げていくために、店舗建設などにおいて専門分野で培った能力を活かしていただきます。将来的には全世界の施工チームと連携して活躍していただきます。
#建築 #施工監理 -

水産(フィールド)コース ~世界中の人々の健康な生活を一次産業から支える~
お客様に安心・安全でおいしい食をお手軽価格で届けるため、ゼンショーは一次産業の開拓・拡大をしていきます。そのために水産業・畜産業・農業に力を入れており、活躍できる人財を求めています。
#水産業 #畜産業 #農業
福利厚生・研修・社内制度
- 住宅手当・家賃補助あり
- 社宅・独身寮あり
- 企業独自の育児休業あり
- 家族手当あり
- 財形貯蓄制度あり
- 社内預金・持株会あり
- 資格取得支援制度あり
福利厚生・社内制度
●社会保険完備(健康・厚生年金・労災・雇用保険)
●借り上げ社宅制度、家賃補助制度
●財形貯蓄
●社員持株会
●車両補助金
●転勤補助金
●スタッドレスタイヤ補助金
●インフルエンザワクチン補助金
●健康保険、厚生年金
●慶弔見舞金
●退職金
●確定拠出年金
研修制度
<入社前研修>
●自社理解ワーク
●内定者ネットミーティング英語研修(随時)
<入社後研修>
●新卒社員研修
●グループ研修
●社内研修
※配属先により研修内容が変わる場合があります。
その他、年次やキャリアに応じて各種研修を実施しております。
自己啓発支援
●英語学習支援
年1回のTOEIC試験受講や、公募制による語学講座などを社内で受講することが出来ます。一部、選抜制による語学研修もあります。
●第二外国語学習支援
公募制により中国語・スペイン語などのオンライングループレッスンを受講することが出来ます。
メンター制度
【Brother・Sister制度】
上司とは別に相談できる相手を持てるよう、新入社員2~3名に対して先輩社員1名がメンターとなっております。
職場環境
-
平均残業時間
(月間)28.9 時間 -
平均有給休暇取得日数
(年間)9.9日
-
役員および管理職に占める女性の割合
役員: 7.1%
管理職: 10.4% -
育児休業取得者数/対象者
男性:取得者9名(対象者35名)
女性:取得者7名(対象者7名)
最終更新日:
社員について
-
平均年齢38.6歳
-
平均勤続年数8.3年
-
新卒採用者数の男女別人数(過去3年間)
2024年度:男性89名、女性33名
2023年度:男性48名、女性14名
2022年度:男性89名、女性21名
最終更新日:
会社概要
| 創業/設立 | 1982年6月 |
|---|---|
| 本社所在地1 | 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビルMAP |
| 事業所 | 本部:東京都港区 工場:国内30カ所 物流拠点:国内26カ所 システムセンター:国内2カ所 (2021年12月末時点) 海外法人:各国・各地域 店舗数:10,078店舗(2022年3月末時点) |
| 代表者 | 代表取締役会長 兼 社長 小川 賢太郎 |
| 資本金 | 269億9,600万円(2023年3月末) |
| 売上高 | 7,799億6,400万円(2023年3月期) |
| 従業員数 | 社員:17,324名(2023年3月現在) |
| 子会社・関連会社 | 【外食事業】 (株) すき家・(株) なか卯・(株) ロッテリア (株) ココスジャパン・(株) ビッグボーイジャパン (株) ジョリーパスタ・(株) 華屋与兵衛・(株) TAG-1 (株) はま寿司・(株) 久兵衛屋 (株) エイ・ダイニング 他 【小売事業】 (株) ユナイテッドベジーズ・(株) ジョイマート 【介護事業】 (株) 輝・(株) ロイヤルハウス石岡 シニアライフサポート (株) (株) エンネルグ・(株) アイメディケア 【海外事業】 ≪中国≫ 泉膳(中国)投資有限公司 ≪ブラジル≫ Zensho do Brasil Comercio de Alimentos Ltda. ≪タイ≫ Zensho(Thailand)Co.,Ltd. ≪マレーシア≫ Zensho Foods Malaysia Sdn. Bhd. ≪メキシコ≫ Zensho Food de Mexico S.A. DE C.V. ≪台湾≫ 台湾善商股分※有限公司 ※字体は人偏(にんべん)に「分」 ≪インドネシア≫ PT. Zensho Indonesia ≪ベトナム≫ Zensho Vietnam Co.,Ltd. ≪香港≫ Zensho Hong Kong Co.,Ltd. ≪アメリカ・カナダ・オーストラリア≫ Advanced Fresh Concepts Corp. ≪マレーシア≫ TCRS Restaurants Sdn. Bhd. 他にも物流機能や製造加工を担う機能会社などもあります。 ◆グループ会社数:133社 |
| 上場区分 | 国内上場 |
| 上場市場 | 東証 |
| 沿革 | 1982.06:当社を設立し、神奈川県横浜市鶴見区に横浜工場併設の本社を設置 1982.11:すき家(牛丼店)ビルイン1号店として、生麦駅前店(神奈川県横浜市鶴見区)を開店。 1999.09:東京証券取引所市場第二部へ上場。 2000.07:(株)ココスジャパンの株式を取得 2001.09:東京証券取引所市場第一部銘柄指定。 2002.10:回転寿司事業の運営を行うため、(株)はま寿司を設立。 2004.02:グループ会社の本部機能を集約し、本社を現在地(東京都港区港南2-18-1)へ移転。 2005.03:(株)なか卯の株式を取得。 2006.05:食の安全に対する取り組み強化のため、中央分析センターを設立。 2006.08:物流の効率化を目的として、(株)グローバルフレッシュサプライを設立。 2007.02:事業分野拡大のため、青果販売の(株)ユナイテッドベジーズの株式を取得。 2007.07:すき家の沖縄県出店による全47都道府県への出店達成。 2008.06:ITによる事業の効率化を目的として、(株)グローバルITサービスを設立。 2011.12:製造機能拡充のため、(株)GFFを設立。 2012.11:小売事業の拡大のため、(株)マルヤの株式を取得。 2014.01:事業分野の拡大のため、(有)介護サービス輝(現:(株)輝)の株式を取得。 2016.04:はま寿司の京都府出店による全47都道府県への出店達成。 2017.09:ココスの鹿児島県出店による全47都道府県への出店達成。 2021.10:経済産業省が定める「DX認定取得事業者」に認定。 |
キャリタス就活編集部 特別情報
この企業が掲載されているランキング
 はキャリタス就活会員限定コンテンツです。
はキャリタス就活会員限定コンテンツです。閲覧には、キャリタス就活へのログインが必要です。
この企業が受けている認定・選定




★★★(3段階)



DX注目企業


ホワイト500

ブライト500
関連情報
有価証券報告書「従業員の情報」に記載されている内容を抜粋しています。本情報は、決算期が2022年4月~2023年3月末までの有価証券報告書を対象としています。
()
|
従業員数(人)
-
[ - ] |
|
従業員数(人)
|
平均年齢(歳)
|
平均勤続年数(年)
|
平均年収(円)
|
|---|---|---|---|
|
従業員数(人)
-
|
平均年齢(歳)
-
|
平均勤続年数(年)
-
|
平均年収(千円)
-
|