LGBTとは?職場に求められる配慮や法規制は?【弁護士が答えます】
就活ノウハウ公開日:2025.10.01

近年、法整理や情報発信の加速により世間のLGBTに関する理解は広まりつつある一方で、職場での差別や偏見はまだあるのが実態です。実際に差別等が原因で自殺に追い込まれてしまったり 、裁判に発展したケースもあります。今後社会に出る上でも「自分には関係ない」と思うのではなく、すべての人が共に安心して働いていける環境をつくっていくために、どのようなことが求められるのか理解することが大切です。本記事ではLGBTの概要や今後皆さんが働きはじめた際にLGBTの被害者、加害者にならないためにどうする必要があるのか弁護士が解説します 。
そもそもLGBTとは?どれくらいの割合でいる?
LGBTとは、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の頭文字を並べた言葉で、性的マイノリティの総称のひとつです。同性を好きになったり、身体の性と自認の性が異なる人のことを指します。
国内における調査では人口の約3~10%がLGBTであるといわれています。またこれら数値はアンケートから抽出されたデータのため、自身がLGBTであることを答えたくないと考える人も一定数いると推測すると、この割合はさらに高いことが予想されます。
LGBTに対して企業に求められる配慮とは?
近年、LGBTに対する国民の理解度は高まっています。その一方でLGBTに配慮した取り組みを実施している企業はまだまだ多くないのが現状です。
その状況をふまえ、国は2023年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」を公布・施行しました。これは国民のLGBTに対する理解度を向上させることで寛容な社会の実現を目指すことを目的としています。
この法律において、事業主は、LGBTの理解の増進に自ら努めるとともに、国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものと定められました。
厚生労働省のLGBT理解増進に向けた主な取り組みの一例として、以下のようなものが挙げられます。
■公正な採用選考の実施
■性的マイノリティを考慮した職場におけるハラスメント防止
■企業への取組事例等の調査
■社員への教育・研修の実施 など
また国が推進する取り組み以外にも、各企業において独自の取り組みを行う企業も出てきてます。たとえば社内規則や就業規則に性的マイノリティに対する差別の禁止を明文化する企業や、LGBTに関する研修を全社員に行うなど問題解決に積極的に取り組む企業もあります。
このように性的マイノリティの方の尊厳を守り、安心して過ごせる社会を実現するため、国民全体の理解度を深める施策に協力することが企業に求められています。
LGBT差別に対する法規制 はある?
先ほど説明した法律はあくまでも努力義務のため、LGBT差別を禁じる明確な法律はありません。
※本記事の執筆時点の情報です。
ただ、特定の場面を前提とした個別の法律によって、LGBT差別に対する規制が設けられています。労働の場においても、LGBT差別に対する規制が設けられています。
職場内でのハラスメントを一般的に規制する法律としては、労働施策総合推進法(「パワハラ防止法」と呼ばれます)が存在します。そして、パワハラ防止法を受けて作成された厚生労働省の指針には、以下の内容が示されています。
①労働者の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動はパワハラにあたること
②労働者の性的指向・性自認を暴露することはパワハラにあたること
②は、「アウティング」といわれる行為です。労働者がもつ性的指向や性自認について、本人の同意なく他者にそのことを暴露することもハラスメントにあたるということになります。侮辱的な意図を含まなくとも、性的指向・性自認に関する情報を誰かに話すだけで違法になり得ます。
ハラスメント被害が発生した場合の対応
企業は、ハラスメント相談窓口の設置義務を課されています。労働者がハラスメント被害を訴えた場合、企業は、関係者から事実を聴取するなど、適切な対応を講じなければなりません。
この記事を読んだ方の中で今後、LGBT差別を受けてしまった場合、企業のハラスメント窓口に相談をし、労働環境の是正を求めることが望ましいでしょう。
他方で、あなたのふとした行動がきっかけで、LGBT差別の加害者の立場になることもあるかもしれません。もしそうなってしまった場合は、企業からの事実聴取等に真摯に協力し、改善の意思を示すべきでしょう。
誰もが安心して働ける社会を目指しましょう
多様性に関する社会の意識は目まぐるしく進展しています。
そのため、悪意はなくとも、自分がいつの間にか差別の加害者になってしまう危険性があります。差別を受ける側にしてみれば、加害者に悪意があろうとなかろうと、不当な扱いを受けたことに変わりはありません。「知らなかった」では済まされない場合もあるため、まずはLGBTの方への理解を深め、発言や行動には配慮を行いながら働くことが大切です。
PROFILE
定禅寺通り法律事務所
下大澤 優弁護士
退職代行、残業代請求、不当解雇、パワハラ・セクハラなど、数多くの労働問題を取り扱っています。これまでにも、発令された配転( 転勤) 命令の撤回、未払残業代の支払など多くの事例を解決しています。








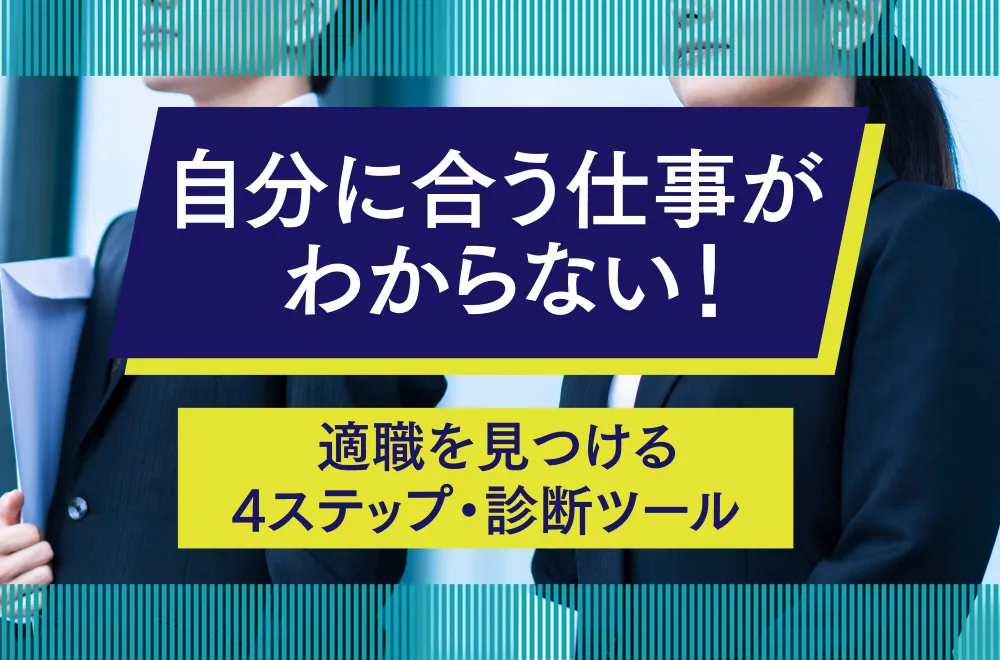

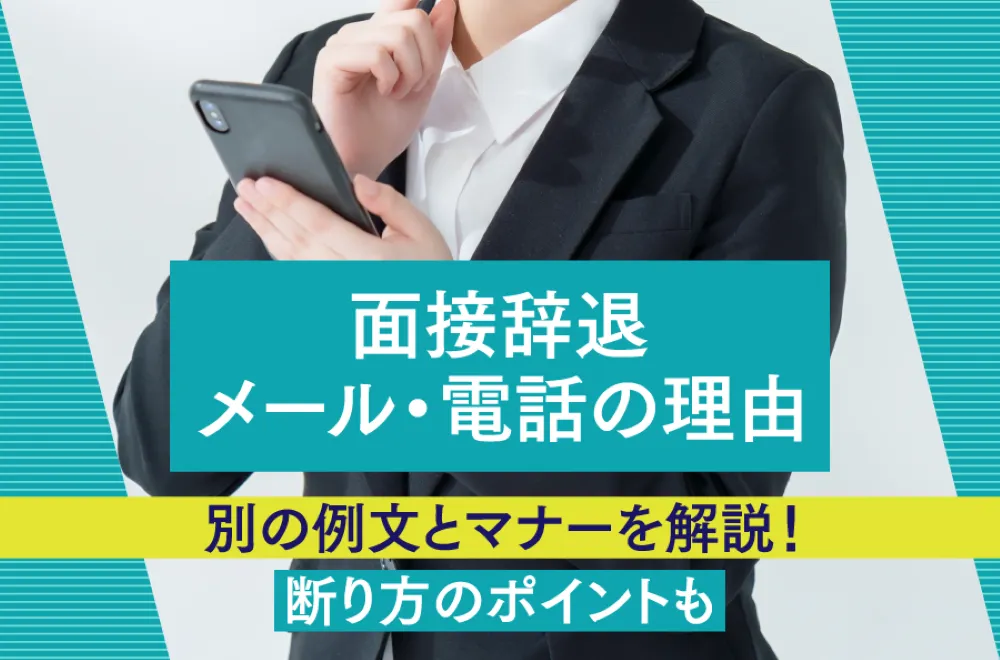





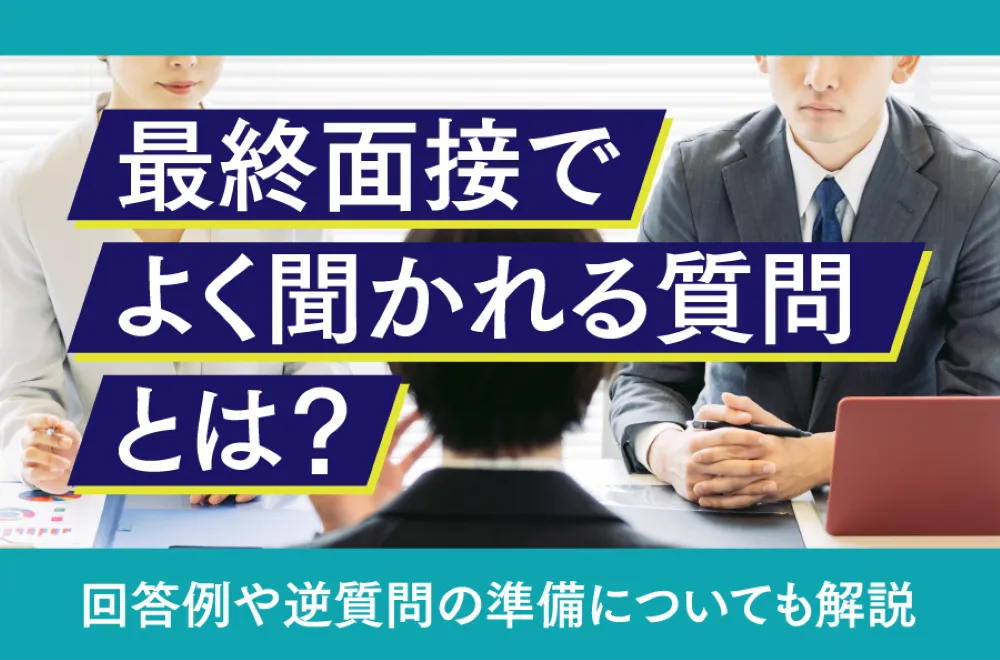
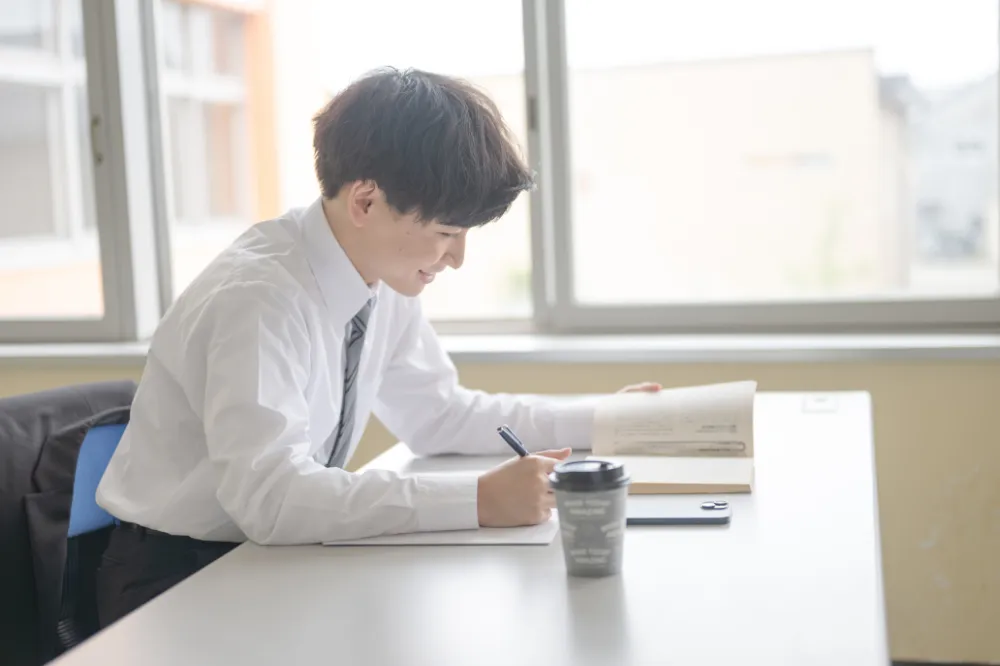
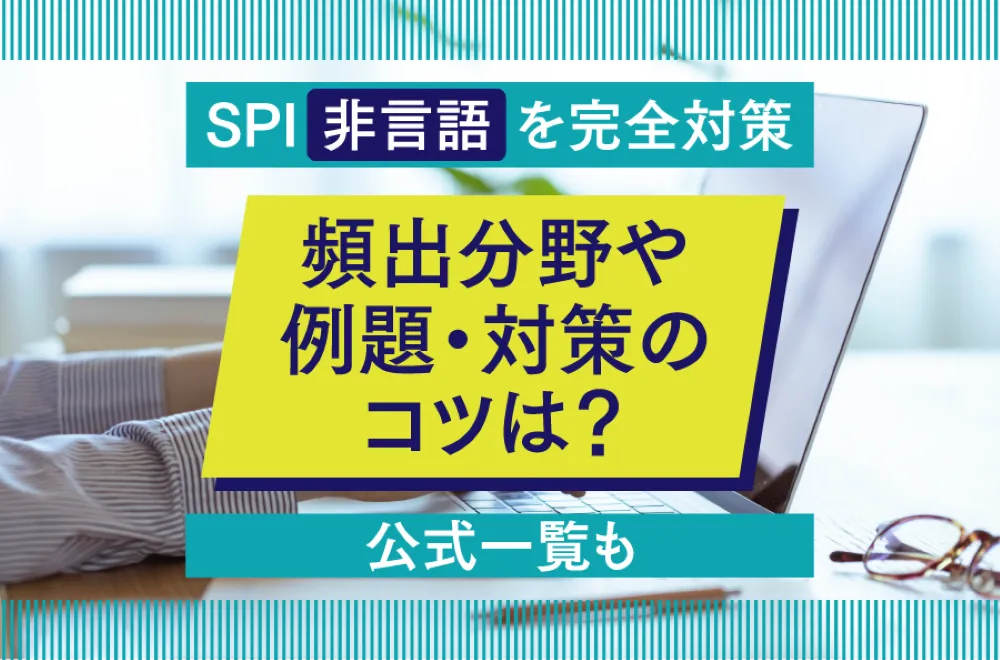
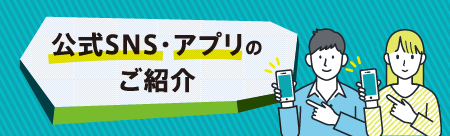
 LINE
LINE
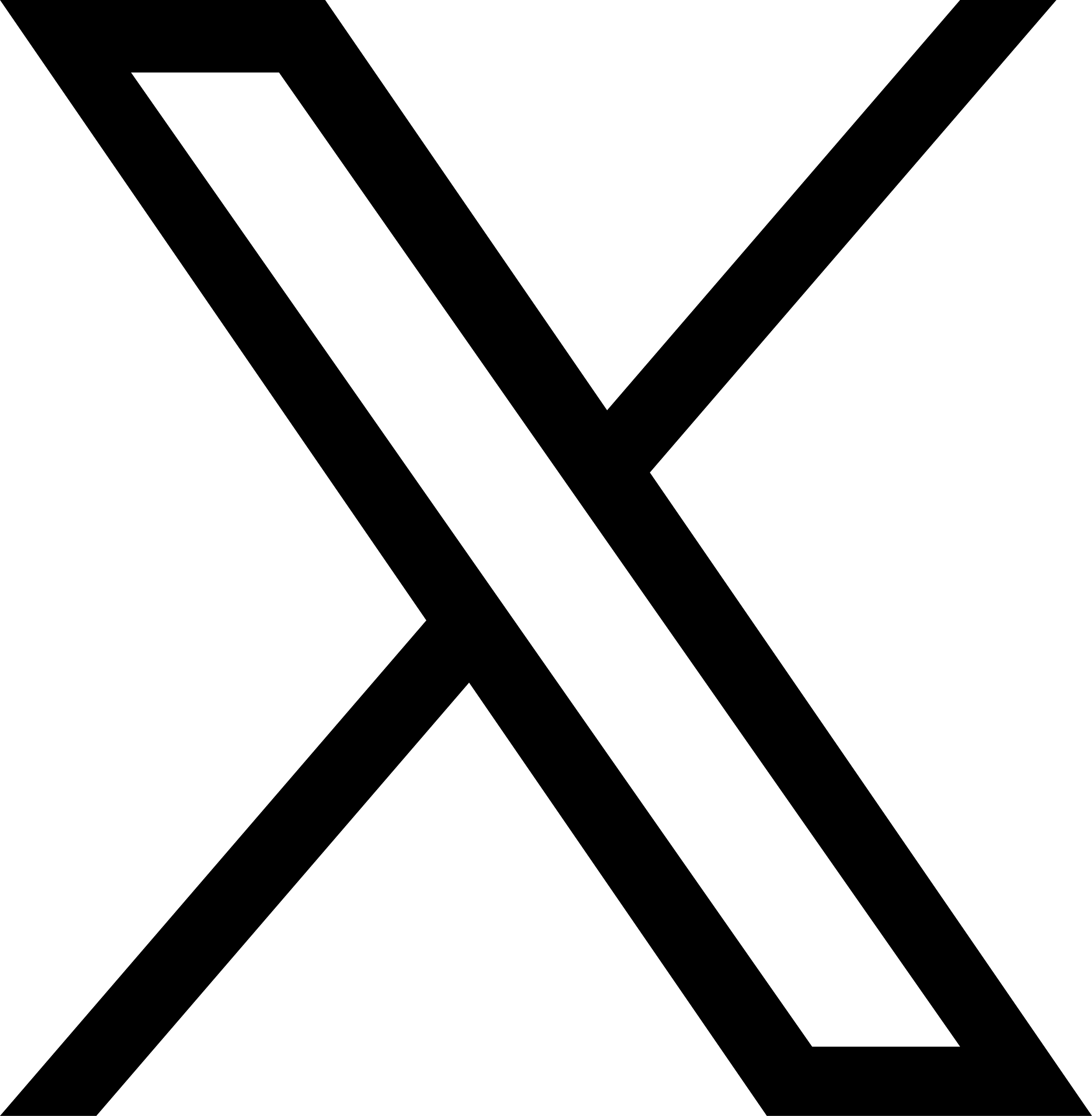 X
X
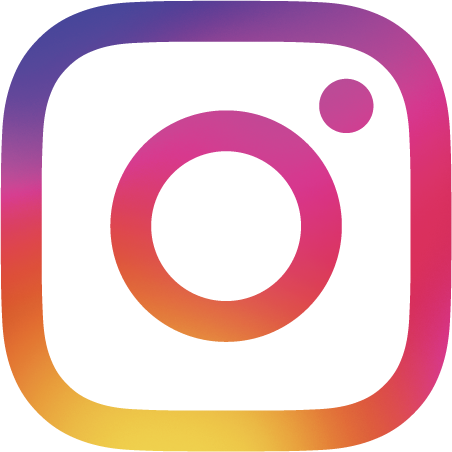 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube