グループディスカッション(GD)攻略のコツは?よく出るテーマや対策も解説
就活ノウハウ公開日:2025.02.12

就活におけるグループディスカッションは、チームで働く上で必要な能力が試される選考方法の1つです。各役割を理解し、出題テーマや採用担当者が見ているポイントを押さえた事前対策をすることが重要です。本記事では、グループディスカッションの参加が初めての方や苦手意識のある方でも高評価を得られるようにわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
グループディスカッション(GD)とは
グループディスカッションは、就活の選考方法の1つで、数人の応募者がグループで特定のテーマについて話し合い、結論を導き出す形式の選考です。
通常、5~6人程度のグループにわかれてテーマについて30分程度で議論を行います。議論の最後にはグループで導いた結論の発表を求められる場合も多いです。企業はこの中で応募者のやり取りを観察し、限られた時間内で効率的に議論を進める力やコミュニケーション能力を評価します。
■企業がグループディスカッション(GD)を実施する理由は?
企業がグループディスカッションを実施する理由は、多くの就活生を短時間で評価できる点にあります。グループディスカッションでは、協調性やコミュニケーション能力、論理的思考力など、チームで働く上で必要になる基本的な資質や能力が見られます。
この選考を通じて、企業は就活生の能力や振る舞いを見極め、次の選考段階に進む候補者を絞り込んでいます。以下では、企業が注目している評価ポイントを詳しく解説します。
グループディスカッション(GD)で企業は何を見ている?受かる人の特徴

企業はグループディスカッションで応募者の「入社後の仕事ぶり・自社への貢献度」を見極めています。チームの目標達成に向けて、どのように貢献できるかを見ようとしています。具体的には、以下のようなポイントが評価対象となるケースが多いです。
企業が見ている評価ポイント
・コミュニケーション能力があるか
・論理的思考力ができるか
・リーダーシップがあるか
・協調性があるか
他者の意見を正確に理解し、自分の意見を簡潔かつわかりやすく伝えるコミュニケーション能力や、筋道を立てて考える論理的思考力が、グループディスカッションでは重要な評価ポイントです。
さらに、限られた時間内で解決策を導き出すために議論を効率的に進められるリーダーシップも評価対象となります。企業ではチームでの業務が多いことから、全員の意見を尊重しながら合意形成を目指せる協調性も高く評価されます。
グループディスカッション(GD)で評価されるコツ
グループディスカッションで評価されるためには、どのようなポイントに気をつければよいのでしょうか。ここでは、グループディスカッションで高く評価されるためのコツを解説します。
■アクティブリスニングする
アクティブリスニングとは、相手の話を積極的に聞き、深く理解しようとするコミュニケーションスキルです。グループディスカッションでは、発言者の話をただ聞くだけでなく、深く理解しようと意識的に取り組むことが大切です。
また、非言語的なコミュニケーションも評価対象となります。たとえば、話している人に目線を向けたり、適度に頷いたりするなど、ボディランゲージを活用して「話を聞いている」という意思を伝えましょう。さらに、背筋を伸ばし笑顔を心がけるなど、参加している姿勢を態度で示すのも効果的です。
■時間を守る
時間を守ることは、グループディスカッションで評価されるための重要なポイントです。限られた時間内で効率的に結論を出す力は、社会人に求められる基本的なスキルの1つといえます。
結論を時間内にまとめるだけでなく、最後のプレゼンテーションも時間内に収めるのが大切です。そのためには、メンバー全員で時間を意識しながら協力して議論を進めることが求められます。
■チーム全員が協力し合える雰囲気を作る
グループディスカッションでは、チーム全体で協力し合える雰囲気を作るのが重要です。異なる意見をもつ人同士が協力して成果を出すことが求められます。
意見が一致しない場合は、納得していない人の考えを丁寧に聞き取り、全員が納得できる形に調整することが大切です。チーム全体を見渡しながら議論をまとめる姿勢は、企業側から高く評価されるポイントとなります。
さらに、柔軟な姿勢を見せるのも重要です。1つの結論や自分の意見に固執せず、よりよいアイデアを模索する姿勢が評価されます。たとえば、「その考え方すごくいいですね」「そちらのアイデアを掘り下げてみましょう」といった言葉を使うことで、議論を前向きに進めるきっかけを作れます。
このような柔軟で前向きな態度が、チーム全体の成果を引き上げることにつながります。
■議論がスムーズに進むようにフォローする
グループディスカッションでは、議論をスムーズに進めるためにフォローする姿勢が重要視されます。話題が逸れた際は、軌道修正を行い、議論を適切な方向に戻すことでチーム全体の進行をサポートしましょう。
また、発言が苦手なメンバーがいる場合、質問して意見を引き出してあげることも大切です。うまく説明ができない場合は「賛成か反対か」という簡単な質問から回答を促してあげるのもよいでしょう。このように、チーム全体を俯瞰しながら適切に調整する力は企業から評価されます。
■自分の意見をきちんと主張する
自分の意見をきちんと主張することは、グループディスカッションで重要なポイントです。ほかの人の意見をしっかり聞いた上で、自分の考えを簡潔にまとめてわかりやすく伝えることが求められます。
意見を述べる際は、堂々と自信をもって発言しましょう。ただし、長時間話し続けることや、ほかの意見を否定するような発言は避けるべきです。適切なタイミングでバランスよく発言し、チームの議論を前向きに進める姿勢を心がけるのが大切です。
これらのコツを押さえつつ、さらに以下の4点を意識することで、グループディスカッション全体を通して担当者によりよい印象を与えられるでしょう。
グループディスカッション全体を通して意識すべき点
・他者の意見を尊重し受け入れる姿勢を大切にする。攻撃的な態度はNG
・予想外の状況や問題に対しては冷静に対処する。感情的になることはNG
・社会人としてふさわしい言葉遣いで話す
・姿勢や表情、声のトーンなど、非言語のマナーにも気を配る
グループディスカッションで高評価を受けるための具体的な対策は以下をご覧ください。
グループディスカッション(GD)の進め方
一般に、グループディスカッションは以下のような流れで進められます。

1.担当者より説明・グループわけ
グループディスカッションは担当者の説明からはじまり、テーマやグループわけが共有されます。議論をスムーズに進めるために全体の流れをしっかり理解することが大切です。また、評価基準や注意点も説明される場合があるため、聞き逃しを防ぐためにメモを取るとよいでしょう。
2.自己紹介
グループにわかれた後、メンバー同士の自己紹介を行います。名前や学校名、専攻などの基本情報を簡潔に伝えましょう。またディスカッションへの意気込みを一言添えると好印象です。初対面のメンバーと和やかな雰囲気と関係性を作ることがポイントです。
3.役割決め
次に、グループディスカッションで担う役割を決めます。役割には、たとえば議論を進行する「司会」や時間を管理する「タイムキーパー」などがあります。
役割の決め方は、司会を最初に決めて司会が役割を指名する方法と、それぞれが役割に立候補する方法の2つがあります。メンバーの得意分野や希望を考慮して決めましょう。
また、例外として企業担当者から「役割は決めずに進める」という指示が出される場合もあります。企業側から提示される指示やルールに注意して進めてください。
4.テーマの定義とタイムスケジュールを確認
役割が決まったら、テーマの定義確認とタイムスケジュールの設定を行います。まず、テーマについてあいまいな部分や解釈にズレが生じそうなポイントを確認し、全員で認識を揃えましょう。たとえば、「この言葉は『〇〇』という意味で使うことにしましょう」といったように具体的にすり合わせます。
次に、限られた時間内で効率的に議論を進めるためにタイムスケジュールを設定します。議論は30~40分で指定される場合が多いです。たとえば、40分間のディスカッションなら、自己紹介に4分、議論に28分、発表準備に8分程度を目安にするとよいでしょう。
進行中はタイムキーパーが中心となり、必要に応じて時間配分を調整します。
5.ディスカッション
ディスカッションでは、各メンバーが与えられたテーマについて意見を述べ、議論を深めていきます。自分の考えを伝えるだけでなく、ほかのメンバーの意見にもしっかり耳を傾けることが大切です。また、具体的な事例やデータを取り入れることで、議論の説得力を高められます。
意見が対立する場面もあるかもしれませんが、メンバーの意見を尊重し、冷静な話し合いを心がけることで建設的に議論できます。
6.結論をまとめる
議論が終わったら、グループとしての結論をまとめて発表の準備をします。これまでの議論を振り返り、全員が納得できる形で意見を整理することが大切です。書記が記録した内容を基に、議論の中から重要なポイントを抽出し、論理的にまとめましょう。
結論は短くわかりやすい言葉でまとめるようにします。発表者がスムーズに説明できるようにグループ全体で十分に準備しましょう。また、発表後に質疑応答がある場合も想定し、予想される質問への準備を進めておくと安心です。
7.発表する
最後は議論で導いた結論をグループごとに発表します。発表者は、グループ全体の意見を代表して、わかりやすく伝えることが求められます。発表の際は声のトーンや話すスピードに気を配り、聞き手に伝わりやすい話し方を意識しましょう。
また、結論を伝える際は、5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)のフレームワークに沿って説明すると、論理的かつ簡潔に意見を伝えることができます。
グループディスカッション(GD)における役割
グループディスカッションにおける役割には、主に「司会」「タイムキーパー」「書記」「発表者」があります。それぞれやることや評価されるポイント、注意点を確認していきましょう。また、役割がない場合の対応についても紹介します。
■司会
やること:
・メンバーが発言しやすいように環境を整え、メンバーの意見を引き出す
・進行状況を把握し、必要に応じて議論をまとめる
評価されるポイント:
・ファシリテーターとしての調整力
・議論の方向性を示すリーダーシップ
注意点:
・自分の意見ばかり押しつけない
・他者の発言を遮らず、平等に意見を促す
■タイムキーパー
やること:
・制限時間内で結論を導けるよう時間を管理する
・進行に遅れが出た際は調整する
評価されるポイント:
・効率的な議論を進めるための時間管理能力
・臨機応変な時間調整
注意点:
・時間配分だけに集中しすぎず、議論全体を把握し、議論にも参加する
・残り時間を適切なタイミングで伝える
■書記
やること:
・議論の内容を正確に記録する
・必要に応じて進行状況や議論の要点を整理する
評価されるポイント:
・筆記・タイピング等でスピーディーかつ正確にメモを取るスキル
・議論の要点を端的にまとめる文章構成力
注意点:
・記録だけに集中しすぎず、議論にもしっかり参加する
・メモをほかのメンバーに共有するタイミングを見極める
■発表者
やること:
・グループの結論をわかりやすく発表する
・結論に至るプロセスや根拠を論理的に説明する
評価されるポイント:
・聞き手が理解しやすいように意見を伝える力
・適切な声のトーンや話すスピード
注意点:
・原稿を読み上げるだけにならない
・グループ全体の意見を代表する意識をもつ
■役割なし
やること:
・発言や質問で議論を活性化させる
・役割のあるメンバーをサポートする
評価されるポイント:
・議論を活性化させる発言力
・ほかのメンバーへのサポート力
注意点:
・他人任せにせず、自分の意見を積極的に述べる
・ほかのメンバーの役割を奪うような行動をしない
メンバーの一人ひとりが「自分の得意分野で能力を発揮して、グループにどう貢献できるか」を考えてグループディスカッションに臨むのが大切です。自分ならではの役割を果たすことで、ディスカッションの質を向上させられます。
グループディスカッションの役割について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
\あわせて読みたい/
ずばり人事の本音を聞いてみた「グループディスカッション、司会じゃないと受かりませんか?」株式会社三井住友銀行
グループディスカッション(GD)の事前対策

グループディスカッションは、テーマや課題が直前まで明らかにならないこともあります。そんな中でも実力を発揮するためには、事前の準備が非常に大切です。ここでは、具体的な対策方法を詳しくご紹介します。
■意見の整理方法を知っておく
グループディスカッションで実力を発揮するために、意見を整理する方法を身につけておくことが大切です。限られた時間内で考えをまとめるには、「SWOT分析」のようなフレームワークが役立ちます。
SWOT分析は、外部環境と内部環境を「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つの要素で整理する方法です。具体的には、強みや弱みで内部的な要素を把握し、機会や脅威で外部的な要因を分析します。
たとえば、「既存サービスの改善案を考える」といった議題の場合、「長年の実績があり、信頼性が高い」という「強み」がある、「競合企業が新規参入している」という「脅威」がある、などの切り口から情報を整理していきます。
事前にこうしたフレームワークの手法を活用できる準備をしておけば、議論をスムーズに進められるでしょう。
■論理的思考力を身につける
論理的思考は、グループディスカッションで自分の意見を効果的に伝えるために欠かせません。普段から物事を多角的に捉え、原因と結果を整理する習慣を身につけましょう。
たとえば、日常の出来事に対して「なぜそうなったのか」「どのような要因が影響したのか」を考えるのが効果的です。このように原因を深掘りし、結果との関係を明確にすることで、考察力や論理的な視点が養われます。
こうした習慣を積み重ねることで、議論の場でも筋道の通った説得力のある意見を述べられるでしょう。
■即興力を養うために練習を繰り返す
グループディスカッションでは、その場で意見をまとめたり発言したりする即興力が求められます。この即興力を養うためには、練習を繰り返すことが重要です。模擬のグループディスカッションに積極的に参加し、実践を重ねることで即興力を磨けます。
また、繰り返し練習することで、緊張や不安を和らげる効果も期待できます。事前にさまざまなシナリオを想定して練習しておけば、予期しない状況にも冷静に対処できるようになるでしょう。
さらに、練習を通して時間の体感力を鍛えておくこともできます。本番では、限られた時間内で意見を整理する力が求められるため、普段の練習から「この内容を話すのに何分かかるか」を意識し時間感覚を養いましょう。
■時事問題や業界の問題を積極的に収集しておく
時事問題や業界の課題を積極的に収集しておきましょう。グループディスカッションはその場での即興力を見るため、テーマが事前に知らされないことも多いです。
普段からニュースや新聞、WEB記事などで最新情報に目を通し、問題に対して一般的にどのような考え方があるのかを把握しておくと、議論の際に役立ちます。また、問題に対する自分の意見を整理しておくことで、議論の際にも自信をもって発言できるようになります。
グループディスカッションを攻略する上で、過去の体験談を参考にするのも効果的な対策です。『キャリタス就活』では過去に選考に参加した先輩たちのリアルなグループディスカッションに関する体験談をチェックできます。企業ごとにグループディスカッションの内容(テーマや進行の傾向など)を確認できるので、自分が志望する企業の体験談を探してみてください。閲覧には学生認証が必要になるため、大学のメールアドレスを登録しておくとスムーズです。
グループディスカッション(GD)でのNG行為

グループディスカッションでは、どのような行動が評価を下げる原因になるのでしょうか。ここでは、グループディスカッションで避けるべきNG行為と、その理由について解説します。
■自己主張が強い
自己主張が強すぎる発言や、感情的・攻撃的な態度は、グループディスカッションでよい印象を与えません。ほかの人の発言を遮ったり、反対意見を攻撃的に否定したりすると、協調性が欠けていると判断される可能性があります。
まずは相手の意見をしっかり最後まで聞き、その上で自分の考えを伝えることが大切です。また、自分の意見が採用されなくても、不機嫌になるのではなく、ほかの意見を尊重しながら建設的な議論を続ける姿勢が求められます。
■一言も話さない
一言も話さない行為は、グループディスカッションではもっとも避けるべきです。発言しないことで、自分だけでなくチーム全体の評価が下がる可能性があります。
緊張して話しにくい場合は、最後の発表者役を積極的に引き受けるなど、自分なりにチームへ貢献する方法を見つけましょう。少しでも発言を行い、チームの一員としての役割を果たすことが大切です。
■姿勢や行儀が悪い
姿勢や行儀が悪いと、周囲に不快感を与えるだけでなく、自己管理能力が低いと見なされる可能性があります。背筋を伸ばし、相手の目を見て話を聞く姿勢を意識しましょう。
たとえば、腕を組んだり足を組んだりする仕草は、無意識のうちに相手に拒絶的な印象を与えることがあります。また、ひじをつく、ペンを回す、音を立てるといった癖は、注意を散らせる原因となるため、事前に直しておきましょう。選考においては小さな所作にも気を配ることが大切です。
■議論の停滞・逸脱を打開しない
議論が停滞・逸脱してしまうのは、グループディスカッションでよくある状況です。そのような場合、停滞や逸脱を打開するために努力する姿勢を見せることが大切です。たとえばテーマや目的を全員で再確認することで、焦点を明確にし、議論が再び動き出すきっかけとなります。
停滞した場合は、違う角度から問題を見直してみると、新しいアイデアが生まれることもあります。結論を出さないまま終わってしまうことのないように、落ち着いて状況を整理し、柔軟な発想でアプローチしましょう。
グループディスカッション(GD)で取り上げられるテーマ例と対策
グループディスカッションでは、多種多様なテーマが取り上げられます。課題解決型のテーマやディベート型のテーマなど、形式や目的に応じた柔軟な対応が求められます。テーマを正確に理解するとともに、出題者がそのテーマを選んだ意図を考えることも重要です。以下で、それぞれの形式に合わせた対策を事前に確認しておきましょう。
■抽象的なテーマ
抽象的なテーマは、明確な答えが存在しない議題を指します。このようなテーマでは、まずテーマの定義を明確にし、議論の方向性を整理することが求められます。テーマを見失わずに論理的に考え、意見をまとめる力が必要です。
■抽象的なテーマ例
・理想のリーダー像とは
・理想のキャリアとは
・働くことの価値とは
・よい会社の条件とは
| 見られているポイント |
・協調性 ・論理的思考力 ・創造的思考力 |
|---|---|
| 具体的な対策 |
・テーマの定義づけを具体的に行う ・具体的に条件設定を行う ・5W(When, Where, Who, What, Why)を明確にする |
| 注意点 |
・議論が脱線しないよう、テーマを常に意識する ・抽象的な言葉(例:「理想」)の具体的な意味を決めておく |
■課題解決型のテーマ
課題解決型のテーマでは、具体的な課題に対して解決策を話し合います。このテーマの場合、課題を正しく捉えた上で、現状を分析し、実現可能な解決策を考えることがポイントです。チームで多様なアイデアを出し合い、実現可能な解決策を議論しましょう。なお、具体的な数値や事例を用いると説得力が増します。
■課題解決型のテーマ例
・コンビニの売上を1.5倍にする施策
・スーパーが競合と差別化して売上を伸ばす施策
・都会のポイ捨てを減らすための施策
・キャッシュレス決済を普及させる施策
| 見られているポイント | ・分析力 ・課題解決能力 ・提案力 |
|---|---|
| 具体的な対策 |
・明確な目標を設定する ・多様なアイデアを出す ・具体的な数字や事例を用いる |
| 注意点 |
・1つの解決策に固執せず、複数の選択肢を検討する ・現実的で実現可能な提案を心がける |
■資料分析型のテーマ
資料分析型のテーマでは、与えられたデータを分析して解決策を導き出します。資料から得られる情報を正確に理解し、データに裏付けられた具体的かつ現実的な提案を導き出しましょう。資料に記載されていない情報を推測するのは避け、データを正確に読み取ることがポイントです。
■資料分析型のテーマ例
・A大学の志願者増加策を考案する
・新商品の売り出し方や価格帯を考案する
・ファミリーレストランの経営戦略を考案する
・空きテナントに入れる店舗を選定する
| 見られているポイント |
・資料の読解力 ・分析力 ・課題解決能力 |
|---|---|
| 具体的な対策 |
・資料を素早く正確に読み取る ・グラフや表の傾向を的確に把握する ・重要なデータや数値を抽出し、メモを取る |
| 注意点 |
・数値の単位や比較対象を正確に理解する ・一部のデータだけでなく、全体的な傾向を見る ・資料に書かれていない憶測や推測を避ける |
■ディベート型のテーマ
ディベート型テーマでは、主に「賛成・反対」「正しい・間違い」「必要・不要」「どちらがよいか」など、意見をわけて議論し結論を導きます。論理的に主張を展開しつつ、相手の意見を尊重し建設的な議論を進めることが求められます。事前にテーマの基礎知識を学び、具体的なデータや事例を用意しておくことが理想です。
■ディベート型のテーマ例
・消費税は減税すべきか
・定年退職の年齢は引き上げるべきか
・幼児から習い事をさせるべきか
・学校において制服は必要か
・住むのは都会か地方のどちらか
| 見られているポイント |
・論理的思考力 ・プレゼンテーション能力 ・柔軟性 |
|---|---|
| 具体的な対策 |
・テーマに関する基礎知識を事前に学習する ・具体的な事例や統計データを用意する ・相手の反論を予測し、それに対する意見を準備する |
| 注意点 |
・感情的にならず、客観的な視点を保つ ・一方的な主張に終始せず、相手の意見にも耳を傾ける |
■フェルミ推定型、ケーススタディ型のテーマ
フェルミ推定型は、限られた情報から数値を推測するテーマで、論理的思考力や計算力が求められます。一方、ケーススタディ型では、過去の事例を基に解決策を議論する形式です。実際の業務に近い議論をすることで、実践的な分析力や課題解決能力を見極められます。どちらのテーマでも問題を要素分解し、適切なフレームワークを活用して、チーム全員で意見をまとめることが大切です。
■フェルミ推定型、ケーススタディ型のテーマ例
・日本にある電柱の本数は(フェルミ推定型)
・大阪府内の全焼肉店の1日の売上は(フェルミ推定型)
・残業時間を減らすための施策(ケーススタディ型)
・若者の車離れを止める方法(ケーススタディ型)
| 見られているポイント |
・論理的思考力 ・前提知識 ・数値の計算力 ・発想力 |
|---|---|
| 具体的な対策 |
・問題を小さな要素に分解する練習をする ・日頃から身の回りの数値を概算する習慣をつける ・基本的な統計データ(人口、面積など)を把握しておく |
| 注意点 |
・感覚的に推測をせず、論理的な根拠を示す ・細かい数値にこだわりすぎず、論理的に概算する ・グループメンバーと積極的に意見交換する |
ディスカッション終了後の振り返り方法
グループディスカッションが終了した後は、振り返りを行うことが大切です。議論した流れに沿って自分の発言や行動を振り返り、どの部分がよかったのか、どの部分に改善が必要なのかを考えてみましょう。
1人で反省するのが難しければ、大学のキャリアセンターや友達、ご家族など人の力を借りて、話しながら振り返るのがおすすめです。他者からのフィードバックを柔軟に受け入れる練習にもなります。
また振り返りの結果は、必ず記録に残しておきましょう。自分で気がついた点、他者と話してフィードバックしてもらったことなどをメモしておけば、次回の参考にしたり改善状況をチェックしたりするのに役立ちます。
グループディスカッションを振り返る作業は、自分の強みや課題を客観的に把握し、改善を重ねていく力を養う重要なプロセスです。これにより、次回の選考での評価アップを目指せるだけでなく、社会人としてチームで業務を進める上で必要なスキルを磨くことにもつながります。
「グループディスカッション=成長の機会」と捉えて、前向きに取り組んでいきましょう!
グループディスカッションは事前の対策が必須
グループディスカッションは、自分の魅力を伝える絶好のチャンスです。終わった後は振り返りを丁寧に行うことで、次回の選考時はさらに成長した姿を見せられます。本記事で紹介した評価されるコツや事前対策を確認して、自信をもって臨みましょう。
『キャリタス就活』では学生の皆さんが安心してキャリア選びに臨めるよう、多数の企業情報やサポートを提供しています。特に就活の悩みを解決する「就活成功ガイド」では業界研究や面接対策など就活に役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。あなたの就活にぜひ『キャリタス就活』をご活用ください。

PROFILE
キャリタス就活編集部
『本音をきく、本気でこたえる。』をテーマに、新卒就職活動・就活・準備を頑張がんばる皆さんに向け、インターンシップ・キャリア情報やES・面接対策など、さまざまなシーンに役立つ就活情報をお届けしています。
「面接がうまくいかない」、「そもそも就活ってなにから始めるべき」など、皆さんの本音に寄り添った記事を配信しておりますので、是非ぜひこの機会にご活用ください。









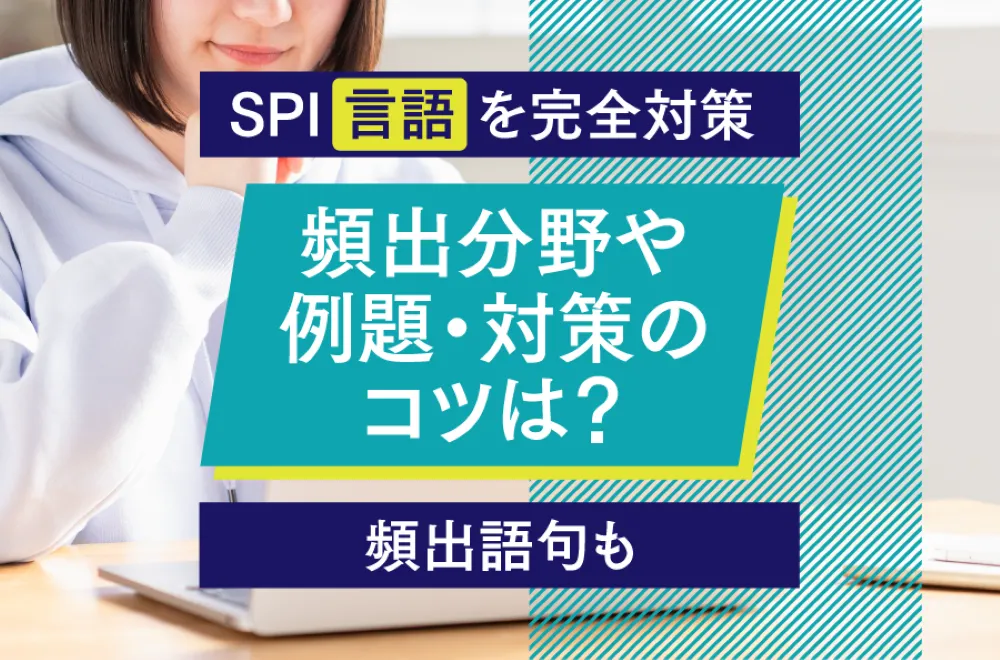





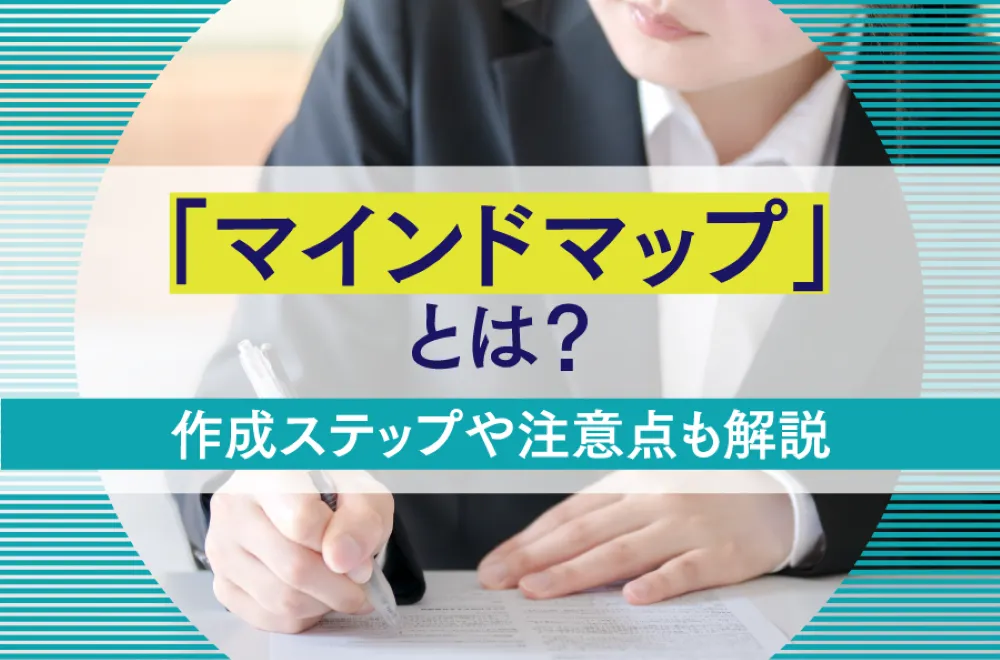
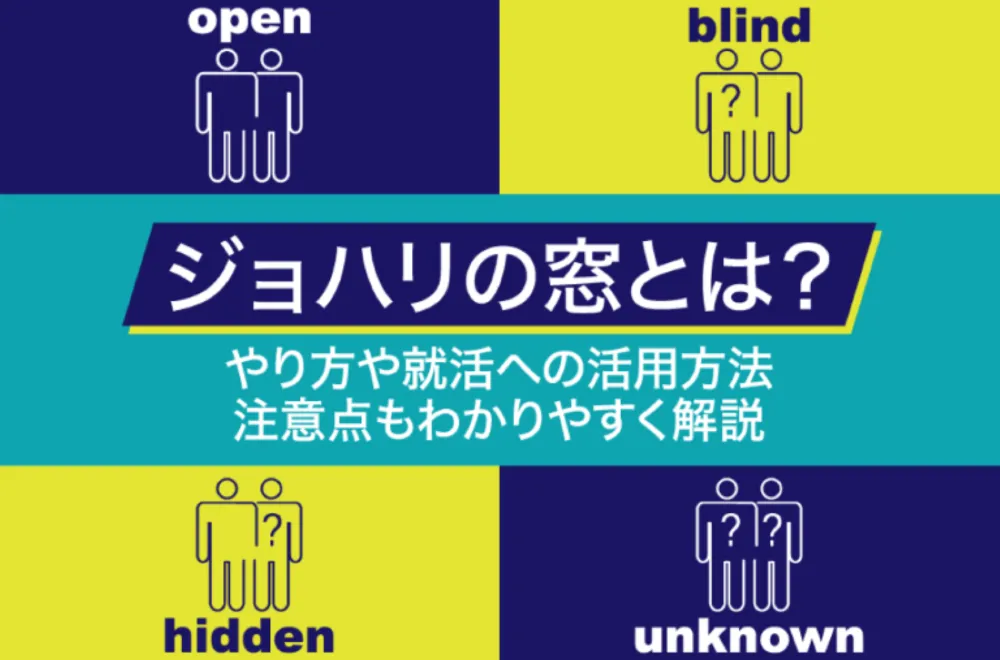
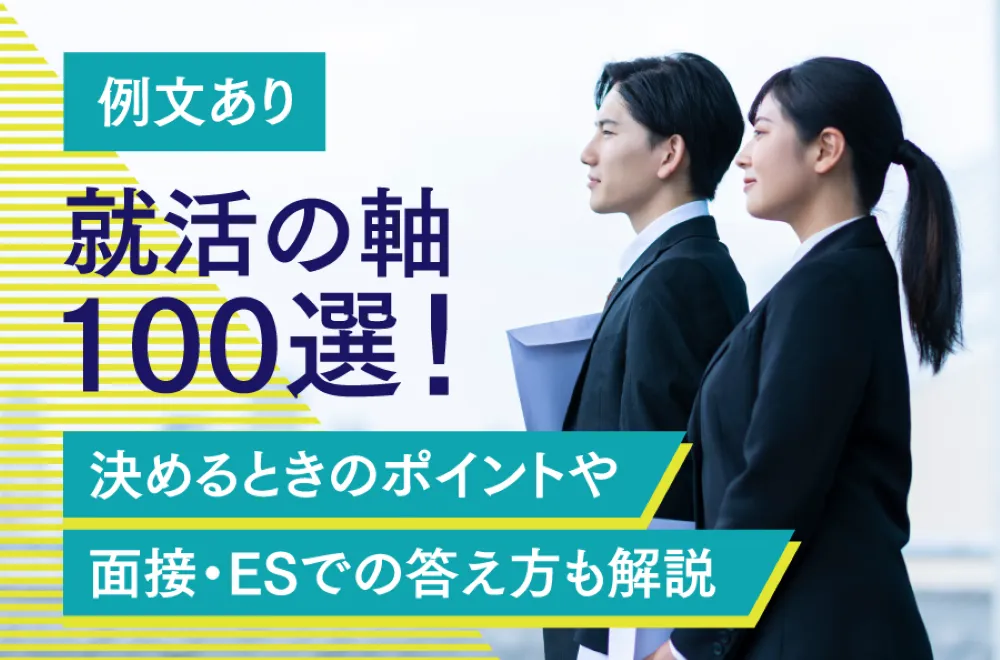

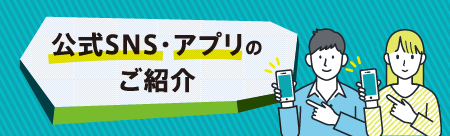
 LINE
LINE
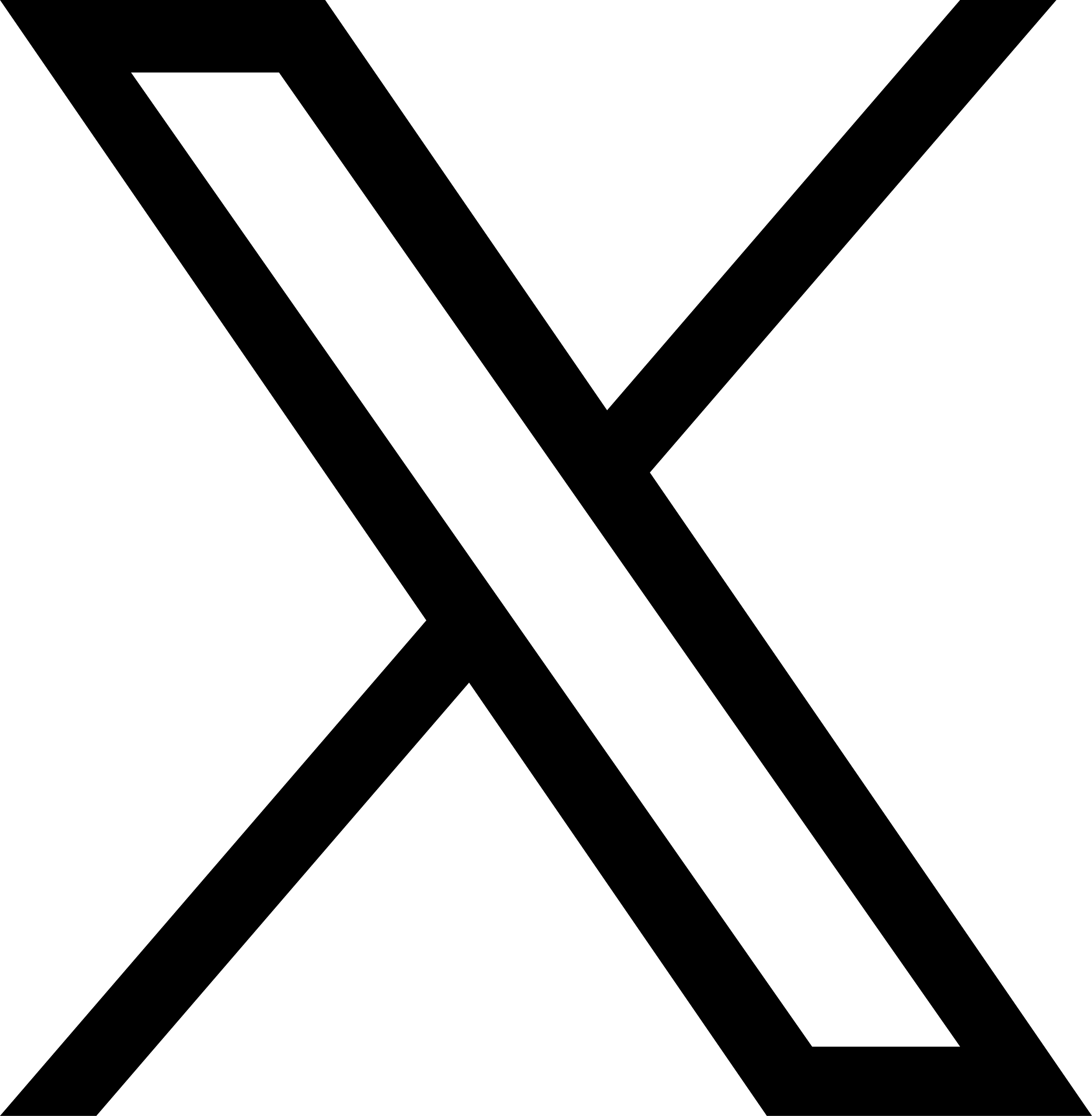 X
X
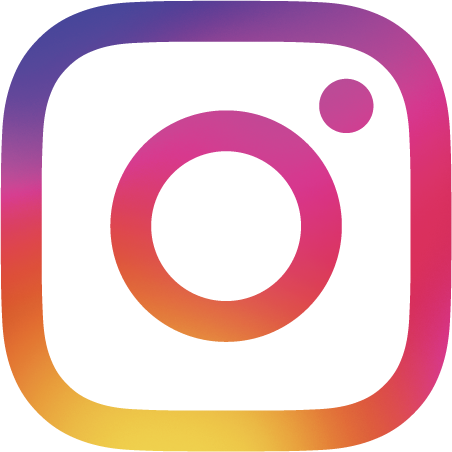 Instagram
Instagram
 YouTube
YouTube