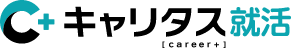第7章
国内金融の存在感と今後への期待
再び存在感を高める日本の金融機関
21世紀の到来とほぼ同時に金融制度改革の一連のプログラムを終えたわが国では、金融ビジネスの新しいフェイズがスタートしました。大手銀行の統合などによって業界地図を塗り替えた日本の金融機関は、デフレと景気低迷が続くなか、新時代を勝ち残るための体力強化に向けて地道な努力を続けてきたと言えます。
その間、米国の低所得者向け住宅ローン債権の証券化商品の価格下落による世界的な金融危機や、それが要因となって起こったリーマン・ショック、さらにはギリシャの財政危機を引き金とする欧州債務危機など、金融機関の経営を揺さぶる出来事が起こりましたが、日本の銀行、証券会社、保険会社は大きなダメージを被ることはありませんでした。 それどころか、たび重なる危機によって体力を消耗した欧米の大手金融機関と入れ替わるように、日本の金融機関は海外市場において、その存在感を高めたと言えます。また、わが国の株式市場も長く続いた低迷を脱し、平均株価も金融危機が懸念されたころの2倍を超える高値を維持するようになりました。
日本経済はバブルのころの活力を取り戻しつつあるという見方も出始めるなか、金融ビジネスは今後どのような活動に力を入れて国民や産業界の期待に応えていくべきなのでしょうか。

家計資産とリスクマネー
いくつもある課題のなかで、もっとも大きいと思われるのは、およそ1,700兆円にのぼる国民の金融資産(家計資産)を、証券市場にシフトさせるという取り組みです。現在、資産の半分以上が預金として銀行などに預けられ、証券投資に向けられた資産は15%ほどしかありません。逆の見方をすれば、銀行は負債(借金)を背負いすぎているということになります。
一方、経済大国となった日本では、成長途上だったころに比べると、産業界の資金需要はそれほど多くありません。つまり、利ざやをきちんと取れる貸し手が少ないのにも関わらず、銀行の負債ばかりが増えているのです。
では、本当に産業界は資金を必要としていないのでしょうか。需要が先細っているのは、実は「銀行が融資しやすい資金」なのです。銀行が伝統的に行ってきた審査にパスする融資案件が少ないとも言えます。それ以外の資金、たとえば新たに事業を始めるための資金や、研究開発のための長期資金、低迷する事業を立て直す起爆剤になるような資金、あるいは途上国に莫大な投資をするための資金などの需要は、掘り起こせばいくらでもあるのです。
こうした資金は「リスクマネー」と呼ばれ、間接金融のモデルでは提供しにくい資金と言えます。しかし、さまざまな運用ニーズを持つ資金を自由に呼び込むことのできる直接金融のモデルなら、リスクマネーを必要な先に届けることができます。ベンチャー企業の成功例が米国に多いのは、家計資産の約半分が証券で運用され、リスクマネーを供給しやすい環境が整っているからだと言えるでしょう。
仮に家計資産の4分の1が債券や株式、投資信託などによって市場に流れ込めば、そこに活力のある資金の循環が生まれ、産業界に新たなパワーをつくり出すことが可能になります。
そうした資金の移動を促すために、政府は「貯蓄から投資へ」を国民に呼びかけ、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をスタートさせました。さらに限度枠を広げるといった政策を通じて証券ビジネスを後押ししています。銀行もNISA口座を積極的に推進し、投資信託の販売においては証券会社に引けを取らない実績を築きつつあります。

問われる「企業を評価する力」
間接金融を担う銀行などがリスクマネーの出し手になるわけにはいきませんが、従来とは異なる与信審査を行うことによって、融資先を広げていくことはできます。たとえば、企業の技術力や特許の保有数、ビジネスモデル、人材などから将来性を判断し、それを“担保”に融資を行うという方法です。
こうした取り組みはメガバンク、地方銀行を問わずさまざまな形で進められています。「財務諸表(会計データ)だけに頼るな」「現場を見て歩け」「経営者と話をしろ」という号令は、どこの銀行の営業現場でも聞くことができます。銀行は審査の手順をマニュアル化し、一定の基準を順守することで不良債権の増加を抑えてきたため、それを超える審査能力を営業担当者がすぐに持つことは難しいと思われますが、そうした能力の強化が急速に進むであろうことは間違いありません。「自分たちをよく見て、応援してほしい」という銀行への期待が中小企業を中心に高まっています。そのため、企業の特徴や状況を個社別に評価する取り組みは、今後さらに加速すると予想されます。
では、ここでポイントを整理してみましょう。
- 日本の金融機関は欧米の金融機関と比べて、相対的に体力を強めました。
- 日本の産業界にはリスクマネーの供給が不足しています。
- 国民の金融資産を証券市場にシフトさせれば、多様な性格の資金の供給が可能になり、産業界に新たなパワーをつくり出すことができます。
- 政府も家計資産のシフトを政策の重要テーマとして掲げ、それを推進する政策を打ち出しています。
- 銀行は行員一人ひとりの「企業を評価する能力」を養うことによって、産業界の期待に応えようとしています。
未来社会のために何ができるのか
そのほか、金融機関にはそれぞれの本業を通じた地域・社会への貢献や、地球環境の保全に向けた取り組みも期待されています。
オフィスや工場などでの事業活動によって排出される温室効果ガス(CO2など)の低減や、電力消費を抑えた設備、太陽光発電の導入などの計画をはじめ、地球温暖化の防止などにつながる研究開発を、通常より低い金利の貸し出しで支える「環境融資」も、そうした期待に応える取り組みのひとつです。
また、環境や社会への貢献およびコーポレート・ガバナンスに対する経営の姿勢を評価し、それを投資判断の材料に加える国際的な取り組みも、年金などを運用する機関投資家や生命保険会社、投資信託などの開発・運用を手がける投資運用会社などの間に広がっています。こうした投資法はEnvironmental、Social、Governanceの頭文字から「ESG投資」、あるいは「SRI投資(Socially Responsible Investment)/社会的責任投資」と呼ばれます。
加えて昨年は、日本の生命保険会社と損害保険会社がスチュワードシップコードの導入を宣言して注目を集めました。スチュワードシップコードとは機関投資家に向けて定められた行動規範で、2010年に英国が導入を決め、2014年2月に“日本版”を金融庁が作成しました。
そこでは、大量の株式を保有する機関投資家は、投資先企業の状況を把握し、対話を通じた問題改善や議決権の活用、さらには議決権を行使する際の内容の公表を行うことなどを通じて、投資家責任を果たすように求めています。これまで機関投資家の多くは、運用を重視し、「もの言わぬ株主」として投資先企業の経営に影響を与えることはありませんでしたが、スチュワードシップコードの導入をきっかけにそうした姿勢を変更し、株主として経営を監視する立場を明確にしていくと思われます。
「金融機関は未来社会のために何ができるのか」を問い直しながら、本業を通じて社会に貢献するとともに、その成果を事業の成長につなげていく取り組みが、今後さまざまな形で広がっていくと考えることができます。