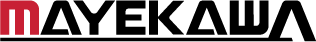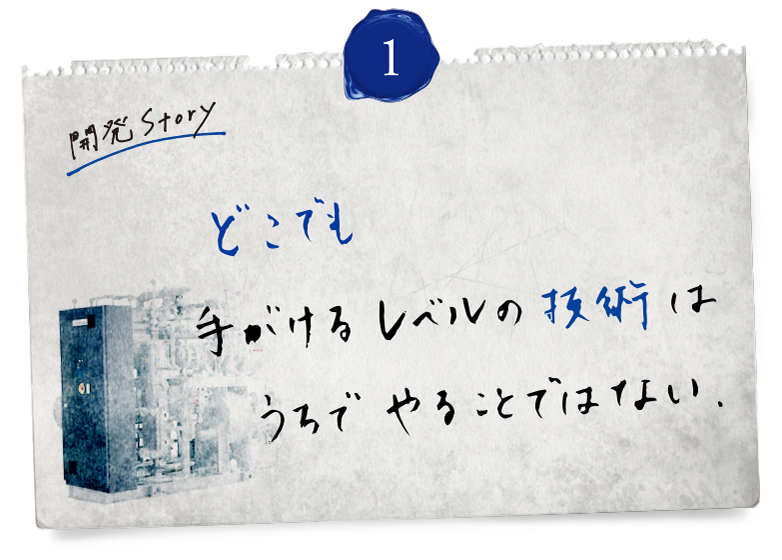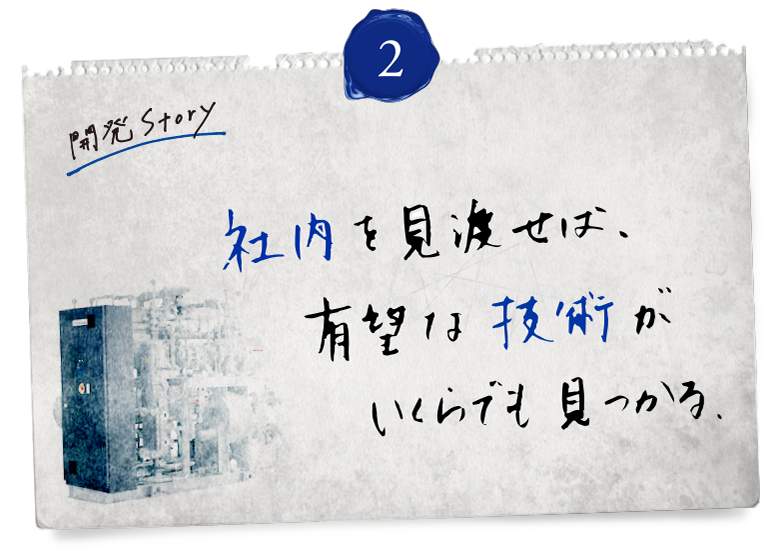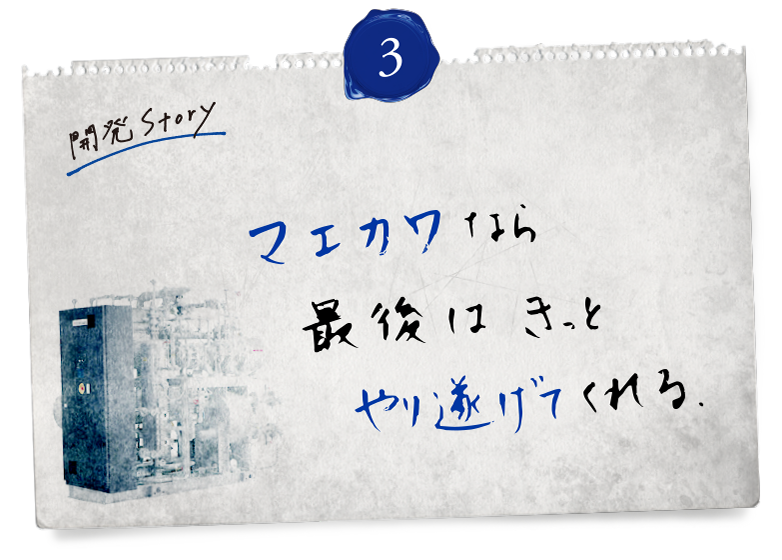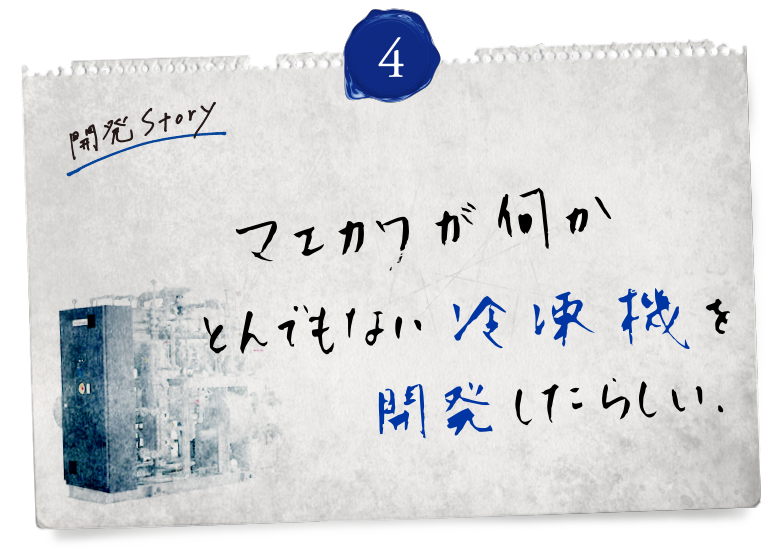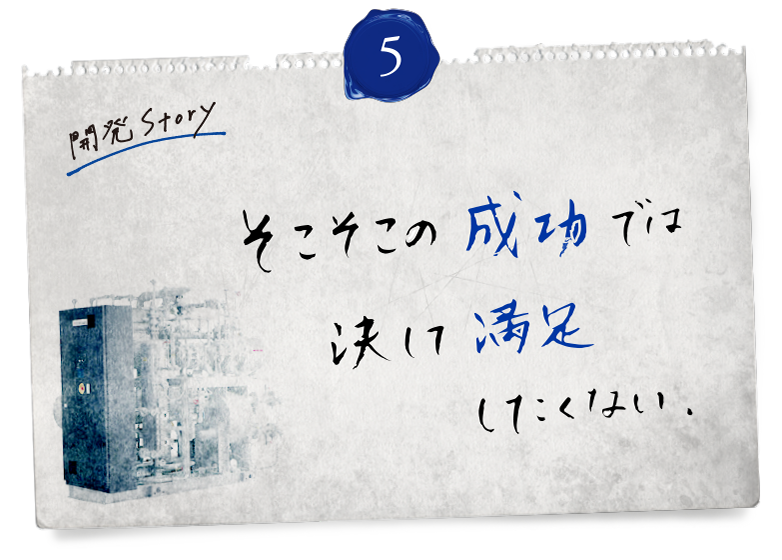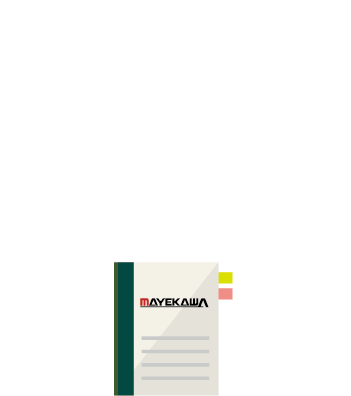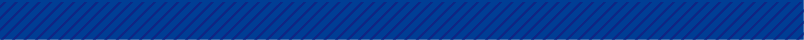地球環境の問題に先進技術で応える。その使命感から開発が始まった自然冷媒冷凍機「NewTon(ニュートン)」。「その気になれば、マエカワにできないことはない」と集まった技術者たちが開発に挑んだ。扱いの難しいアンモニアという冷媒をどう封じ込めるかという点をはじめ、いくつもの難関を越えて今までなかった冷凍機の開発に成功した。そこには「困難な課題だからこそ挑んでいく」という技術者たちの熱い思いが込められている。
また、マエカワは、一見高価な製品でありながら、ライフサイクルコストのメリットを提案するという営業戦略で市場を果敢に開拓してきた。長年にわたるお客様との厚い信頼関係のもと、「マエカワならきっと期待をかなえてくれる」という声に開発から生産、営業、サポートの各メンバーが一体となって応えることで、高い付加価値をもたらしているのだ。
フロン冷媒が世界規模で全廃の方向に進む中、「NewTon」が果たすべき使命はますます大きくなっている。マエカワの壮大な挑戦はこれからが本番だ。

「NewTon」は、地球温暖化対策の切り札として世界から注目されているといっても過言ではない。発売当初の2008年には、洞爺湖サミット国際メディアセンターにて日本を代表する環境技術として世界に紹介された。また、「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」など数々の賞を受賞してきた。そして、何よりも数多くの冷凍・冷蔵施設で続々と採用され、その実力は折り紙付きである。
「NewTon」の何が未来志向なのかを理解するには、冷凍機における冷媒、すなわち冷却物質について知る必要がある。
産業用の冷凍機は元々、自然冷媒であるアンモニアを用いるのが主流であった。しかし、アンモニアは刺激性の強い劇物であり、取り扱いを誤ると爆発の危険がある。その後、化学的に安定した性質を持つフロン類が登場し、一躍、冷媒における主役の座を占めた。ところが、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因物質であると指摘されたことから今日、フロン類の全廃に向けて代替物質の利用が模索されている。
ちなみに、代替物質については大きく二つの潮流がある。一つは欧州でみられる自然冷媒の流れだ。一方、米国では代替フロンと呼ばれる物質が主流となっている。日本はどうかというと、自然冷媒および代替フロンの両方に可能性を求めている状況である。
冷媒をめぐって各国の思惑が交錯する中、マエカワの社内でもさまざまな見解があった。多くの人が代替フロンへの支持に傾いていた一方で、次のような少数意見も根強くあった。
「どこでも手がけている代替フロンで少しばかり優位に立ったとしても、その程度の技術はすぐに陳腐化してしまうだろう。すると結局は価格競争の波にのまれてしまうのでは。こんな程度の技術開発はうちがやることではない」。
価格競争にさらされない革新技術を追求する過程で、社内の数名が議論を深めるために新たな冷凍機のプロトタイプ(試作品)を作ろうと言い出した。 「社内に蓄積されている先進技術を結集して、『その気になれば、ここまでできるぞ』というところを提案しようじゃないか」。
「それはおもしろい」とリーダー格の技術者数名が手を挙げた。それぞれ圧縮機やプラント設計、モーターなどの専門家で、とりあえずワイガヤ(ワイワイガヤガヤの略。元は本田技研工業が提唱)の話し合いが始まった。2006年頃のことである。
マエカワでは、圧縮機の専門家だからといって、それだけしか知らないとは限らない。ジョブローテーションを通じて、開発から製造、保守などさまざまな部門を経験しているマルチタイプが多い。だからこそ、互いの専門について共通言語で議論ができるのが強みだ。また、縦割りの組織と異なり、組織を横断した人のつながりも見逃せない。革新的な技術、価値とは往々にしてこうした企業風土から生まれるものだ。
ワイガヤの中で出てきた開発方針は、製品開発の常識をくつがえすものだった。それは「製品コストを度外視する」というものである。
「マエカワが今、到達できる最高のものをめざそうじゃないか」。
一見、途方もない考えのようだが、圧倒的な競争優位の製品を生み出すには固定概念を打ち破るしかない。まして世界初、世界一をめざすのであれば、ものづくりのセオリーなど蹴飛ばす覚悟が必要だ。他人と同じことをしない。これがマエカワ流の開発である。
開発メンバーがまず取り組んだのが、社内技術の棚卸しである。社内を見渡せば、有望な要素技術が無数にあることを彼らは知っていた。それを結集させることで、世界のどこにもない冷凍機の開発をめざしたのである。
棚卸しで見つけた技術の一つが、IPMモーターである。これはモーターの回転部に永久磁石を用いることで熱損失を少なくした構造が特徴で、高いエネルギー効率での運転が可能だ。しかし、回転する永久磁石の位置制御が難しかったことから、マエカワでは日の目を見ずにいた。
また、アンモニアが充満した環境下で腐食しないモーターを開発するのも容易ではなかった。当初は専門メーカーに開発を依頼したものの、「うちではとても無理」と断られてしまった。ならばと、腐食に強いアルミコイルや被膜技術などを自社内で考案し、独自のモーターを開発することとなった。

加えて、アンモニアの扱いも大きな問題であった。万一漏出した場合のリスクは甚大だ。この課題については、アンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接冷却方式を採用し、アンモニアを機械室に封じ込めることで安全性を徹底的に追求した。さらに従来、冷媒に必要なアンモニアの量は500∼600kgにも及んだが、熱交換器の改良などを通じて最新機種ではチャージ量を25分の1以下の20kgに激減させることに成功したのである。
開発の過程では、当然ながら資金の確保も重要であった。いくらコスト度外視といっても資金をむやみに使うわけにはいかない。そこで環境省の競争的研究資金に応募して研究の資金を獲得するといった工夫も重ねた。
技術の棚卸しを通じて開発の方向性が定まってくると、社内で話題となり、「おもしろそうだ」と開発に協力する技術者が一人二人と増えていった。不思議なことに、上からの指示で動くわけではない。各自の判断で協力するわけである。そして、社員同士がアイデアをすり合わせて開発の課題を一つひとつクリアしていった。
構想からおよそ二年がかりの試行錯誤を経て、いよいよプロトタイプが完成した。
「思った以上におもしろいものができたじゃないか」。
この段階で数人の技術者によるワイガヤから、社内の公式プロジェクトへと昇格した。製品名は「NewTon(ニュートン)」と決まった。すると、営業担当が耳寄りな情報をもたらした。
「お得意先である大手食品会社が『NewTon』に関心を持っていて、冷凍倉庫の増設にともなって1号機を採用してもよいと言っているのだが…」。

渡りに船の話を得て、早速1号機の導入が進められた。守谷工場の中には「製品の完成度が十分でなく時期尚早ではないか」と危惧する声があったものの、開発メンバーは何としてでも成功させる覚悟で臨んだ。
1号機が稼働を始めたのは、2008年3月のことである。案の定、懸念が現実となり不具合が次々と生じた。開発メンバーはその都度、深夜、休日を問わず現場に駆けつけ、対応に追われることとなった。不具合の調整が中々進まない時、内心「もしかすると、うまくいかないかもしれない」という不安に駆られることもあった。しかし、だれもが腹をくくっていた。「『NewTon』がどうしてもうまくいかなければ、従来製品に総入れ替えすればよい。その時は自分が潔く責任をとる」と。
立ち上がり時にさんざん駄々をこねた「NewTon」だったが、開発メンバーが不退転の覚悟で改良改善に取り組んだ結果、ついに安定稼働を実現した。これもお客様の温かいご理解があったからこそである。マエカワではお客様の懐に飛び込んでご要望に応える製品開発を進める。不思議なことにお客様も一緒になって取り組むことがある。例えて言えば、マエカワとお客様との「共創」なのである。
「一時はどうなるかと、正直なところ冷や冷やしていた」というのが、お客様の本音であったかもしれない。しかし、長年にわたって築いてきた信頼関係のもとで「マエカワなら最後はきっとやり遂げてくれる」と信じていただけるお客様が数多くいらっしゃる。だからこそ、お客様の思いに応えて、さらに一歩先に進んで期待を上回る価値を生み出す。それがマエカワのものづくりだ。
1号機の安定稼働を受けて、お客様の系列企業でも相次いで採用が決まっていった。すると、導入先の担当者から驚きの声が次々に社内にもたらされた。
「電気代が信じられないくらいダウンしたよ!」
実は当初の開発計画では、省電力の目標は従来比20%減というかなり野心的な数字であった。「節電性能はすでに限界に達しているのに、さらに大幅削減なんて本当にできるのか?」と、開発メンバーの間ですら疑問視する向きがあった。ところが、「NewTon」が稼働すると、省電力の効果は従来比の20%減どころか、30%減、さらには40%減に達するケースも出てきた。冷蔵倉庫は消費電力の60∼70%を冷却設備で占める。それだけに省電力は利益向上に直結するため、お客様にとってはまたとないメリットだ。
「マエカワが何かとんでもない冷凍機を開発したらしい」。
「NewTon」のうわさは、食品業界などの間でたちまちのうちにクチコミで広まっていった。営業部門には問い合わせの電話やメールが殺到した。
「よし!いよいよ本格的に販売開始だ」。
開発メンバーの意気は上がった。ところが、ここに来て高いハードルが立ちふさがった。販売価格をめぐって営業担当と激論になったのである。コストを度外視して開発した新冷凍機の価格は従来品の3倍から4倍と提示されたからだ。
「冗談だろ? そんなに高い製品、だれが買うものか。いくら性能が良いといってもせいぜい2割増しがいいところ。その価格ではとても売れないよ」。
営業サイドの厳しい意見に開発メンバーは意気消沈した。いくら性能が良いものを開発しても、営業が売ってくれなければ意味がない。一時は「プロジェクトはもはやこれで終わりか」、といった空気すら漂った。
その時、「おい、ちょっと待てよ」と流れを押しとどめた者がいた。当時、事業を統括していた幹部社員だ。
「開発の仕事とは何だ? 社内で少しばかり文句を言われたくらいで、しょげてどうする。そんなことで時代をリードする製品ができると思っているのか。キミたちの任務は世の中を変える製品を作り出すことだろ。せっかく凄い機械が誕生しかけているんだ。技術者としての信念を曲げずに突き進んでみろ。高額の製品をどう売っていくのか、それをやってのけるのが営業の仕事。互いの真剣勝負だ」。

このひと言が社内の空気を変えた。開発と営業がそれぞれの言い分を主張し合うのではなく、問題をどう解決するのか、協力して考えるようになった。相場の何倍もする高価な新製品を売るのは一筋縄ではいかない。営業に加えて開発や生産、保守などのメンバーが集まって議論を重ねた。お互いの情報や知恵を持ち寄り、意見をすり合わせる中で営業戦略を練っていったのである。
その結果、マエカワが編み出したのは奇想天外なものだった。「製品の価格が高いのならば、トータルで提案すればいい」という発想である。つまり、製品単体では高額となるものの、機械の据え付けや保守を含めてトータルで提案することで、結果的にライフサイクルコストが抑えられる点を強調した営業手法である。
これを可能にしたのはマエカワの社内体制にあった。一つの製品を生み出す際、開発から製造、施工、納品、保守までを社内で一貫して手がけている。このワンストップでの対応こそが強みであり、「NewTon」の営業戦略にいかんなく発揮されたのだ。
実際、この対応戦略は市場の開拓を図る上で大きな威力となった。「トータルサポートする」ことに加えて、お客様にとって導入しやすい冷凍機を存分にアピールできたからである。というのも、アンモニアを用いた冷凍機は従来、運転に際して保守の技術者をつけることが求められた。しかし、フロン冷媒の普及とともに保守ができる人材は大幅に減っていた。これに対して、「NewTon」は工場で試運転を行った後、お客様の現場に設置するだけで安全な運転が可能であった。保守担当者なしで稼働できる点は、お客様が機種の選定にあたって、この上ない利点だったのである。
2007年に販売を開始した「NewTon」は、2016年には販売台数1,000台を突破した。しかも、発売から9年が経つにもかかわらず、世界のどこにも競合の製品が登場していない。いや、開発することができないのだ。それだけ圧倒的な技術的優位を持った製品なのである。
「NewTon」が短期間でこれだけ普及を果たした背景には、省エネルギー性能や環境保全対応などの特長とともに、継続した技術改良を挙げることができる。そこには「そこそこの成功では決して満足したくない」という技術者たちの熱い思いがある。発売4年後のバージョンアップでは、主要なモジュールである熱交換器を大幅に改良することで、アンモニアのチャージ量を100kgから25kgへと激減させ、機械の安全性をより向上させた。そして、三度目のリニューアルとなる昨年、熱交換器をよりシンプルな構造にする挑戦が行われ、アンモニアのチャージ量をさらに20㎏へ減らすことになった。
現在、日本国内にとどまらず海外から引き合いが相次いでいる中で、グローバル展開という大きな挑戦が始まっている。そのため、製品開発とともにサービス体制の強化が進む。広域での対応に向けて、IoT(もののインターネット化)を活用した遠方監視システムや保全診断システムの採用も進む。また、AI(人工知能)を活用して分析する予知保全を実行している。今後、米国や欧州、アジアなどの巨大市場を開拓していくことで、世界ブランド「MAYEKAWA」の確立に向けてステイタスを上げていくこととなる。
オゾン層の破壊や地球温暖化といった問題を解決するため、フロン冷媒であるHCFC-22が世界規模で全廃される見込みである。そこで自然冷媒を用いた「NewTon」は、まさに未来を先取りして地球環境の保全に貢献していく。壮大な挑戦はこれからが本番だ。先進技術で世の中の役に立つ。これに勝る仕事はほかにない。